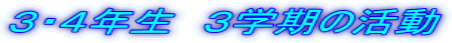

小千谷新聞2011年12月24日号に「日本食文化 世界遺産賛同団体に 岩沢まごころ市!」という記事が掲載されました。「世界遺産」と「岩沢まごころ市」とがどのようにつながっているのか、とても不思議に感じ、そこから3学期の追究活動が始まりました。まず、小千谷新聞に尋ねたところ、
「農林水産省から依頼された唯一の市内の団体であり、この記事を読んだ市民にも郷土料理や世界無形遺産に関心を高めてほしい」
という意図があったようです。市民に贈ったメッセージだったのでしょう。
次に、記事に登場する農林水産省に問い合わせたところ担当者から
「今回の世界遺産への登録に向けた取組をきっかけに、全国各地で日本食について考える場をもっていただくことが、この取組の目的の一つです。 ぜひ、授業で取り上げていただき、子どもたちが何か気付きを得るきっかけとなれば幸いです。」
という回答をいただきました。その後連絡を取り合う中で、「日本食をユネスコ無形文化遺産」に登録を申請するプロジェクト(日本食文化の世界遺産化プロジェクト)の担当者から2月下旬に東京から小千谷へおいでいただき出前授業をしてもらえることになりました。
そこで、世界を経験した方々に触れ、世界的な事象を学ぶ機会を2月に集中させて設けることにしました。
● 外之沢で優婆尊と再会&雪掘り(1月16日)
校区内の外之沢(そでのさわ)へ行き、吉蔵寺跡のお堂へ行き、優婆尊と再会しました。その後、外之沢の冬の暮らしの様子をペアで聞きに行きました。合わせて除雪ボランティアも!
★ 世界の食=世界を知ろう!〜小千谷新聞記者のお話〜(2月7日)
小千谷新聞記者から、JICA(国際協力機構)派遣でブラジル・アルゼンチン・タンザニアにおけるのべ10年以上にわたる活動や「日本食文化 世界遺産賛同団体に 岩沢まごころ市!」に込めた思いについて話していただきました。
● 国際理解ワークショップ「安さのヒ・ミ・ツは子どもたち…?」(児童労働と貧困の現実)(2月13日)⇒WSの様子
新潟県立大学生9名による、児童労働を題材に、子どもたちが働かざるを得ない状況を生み出す「貧困」について考える国際理解ワークショップを通して「貧困」問題の解決のための取り組みを考えました。
★ ユネスコ無形文化遺産「小千谷縮」の工房を訪ねよう!(2月15日)
ユネスコ無形文化遺産「小千谷縮」の工房へ行き、実際のいざり機の見学、社長や講習者から小千谷縮に関するお話を聞かせていただきながら、文化を保存する価値、食文化のユネスコ無形文化遺産への登録との共通点を考えました。
● 青柳勧さんから世界に一歩踏み出す勇気を学ぼう!(2月21日)
水球男子日本代表の青鉼勧主将(ブルボンKZ監督兼選手)から、海外(スペイン・イタリア・モンテネグロ)プロリーグでの経験談、日本代表としてプレーする気持ちなどを話しながら3〜6年生に水球の魅力や一歩踏み出す勇気の大切さを伝えてくださいました。
→ 夏には水球教室?
夏には水球教室?
★ 岩沢で生まれた郷土食を守り、伝えよう! (2月27日)
農林水産省Nさんによる出前授業を通して、日本食文化の特徴を学ぶと共に、郷土食を守るために岩沢まごころ市が担う役割、さらには、3〜5年生の子どもたち一人一人ができることについて考えました。まごころ市の方々も多くの「岩沢のごっつお」持参で活動に参加し、貴重な体験談を語ってくださいました。
● 絵紙で彩る「ひいな祭り」見学(2月28日)
小千谷独特のひな祭りを現代に再現した平成地区商店街で開催されている「ひいな祭り」に行き、江戸末期から明治時代にかけ、織物商人や出稼ぎ農民が江戸や大阪の土産として持ち帰ったとされるたくさんの雛人形、押絵、浮世絵を見学しました。
→ (平成23年の様子)
(平成23年の様子)
★ 「春来い火祭り」の準備作業と本番(3月10日)
3・4年生7名は、5年生とともに準備作業を行いました。函山城狼煙乃会の方々が作り、学校前の雪原に設置したアルミ缶で作った「リサイクル灯明」に蝋燭を入れ、火を付けました。およそ1時間足らずの間にほぼ着火を終え、雪原を2年振りに美しく輝かせました。
● 「小さな小さな ふるさとの博物館」見学(3月14日)
小千谷市内に先頃オープンした「小さな小さな博物館」(正式名称=郷土の歴史と文化の心を伝える 日本・雪国・越後・おぢや発「ふるさとの小さな小さな博物館」)に行きました。会場は昭和34年築の一般農家住宅を一部改造した建物で、古文書と古布を組み合わせた素敵な展示方法でした。館長さんのお話では、「温故知新を念頭に置き、古くて新しい発見のある展示になるように工夫を凝らしています」とのことです。