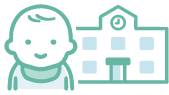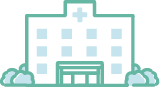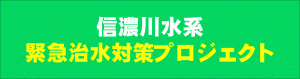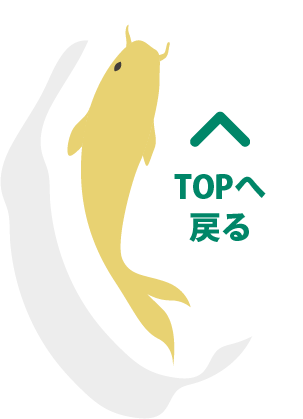本文
小千谷市土砂災害・洪水ハザードマップ
ハザードマップの概要
小千谷市では、土砂災害や信濃川の洪水のおそれのある地域を表示した「小千谷市土砂災害・洪水ハザードマップ」を配布しています。
表面に土砂災害、裏面に信濃川の洪水ハザードマップを掲載しています。
大雨や台風、地震等に備えて、あらかじめ避難経路や指定避難所、指定緊急避難場所を確認してください。
令和7年8月変更のポイント
土砂災害:吉谷・山辺地区において、上片貝地内に砂防堰堤設置に伴い、土砂災害特別警戒区域の減と警戒区域の変更。
洪水:須川、焼田川の最大浸水想定のハザードマップを作製。
土砂災害ハザードマップ
黄色や赤色で表示している土砂災害(特別)警戒区域では、大雨などにより土砂災害が発生するおそれがあります。
市から避難情報が発表されたときは、早めの避難を心がけてください。
災害発生時に避難する際に、土砂災害(特別)警戒区域内にある避難経路を使用する場合は、十分に注意して通行してください。
以下は、表面に掲載した地区別の土砂災害ハザードマップです。
裏面に掲載した洪水ハザードマップは、土砂災害ハザードマップの下に掲載しています。
区域の指定状況及び確認
土砂災害警戒区域等の指定状況や区域図を新潟県のホームページで確認できます。
洪水ハザードマップ
信濃川
信濃川洪水ハザードマップは、1000年に一度程度の確率で洪水浸水が想定される区域をお知らせするものです。
信濃川が氾濫するおそれがある場合、市から避難情報を発表しますので、早めの避難を心がけてください。
県管理河川
県管理河川のハザードマップは、想定し得る最大規模の降雨で、洪水浸水が想定される区域をお知らせするものです。
越水や破堤した場所によっては、ハザードマップで着色されていない場所でも洪水浸水の可能性がありますので、市から避難情報が発表されましたら、早めの避難を心がけてください。
| 片貝地区 | 須 川 | 小千谷市洪水ハザードマップ(須川)はこちら [PDFファイル/2MB] |
| 千谷、高梨、五辺地区 | 焼 田 川 | 小千谷市洪水ハザードマップ(焼田川)はこちら [PDFファイル/2.99MB] |
今後ハザードマップを作成する河川
新潟県から最大浸水想定区域が公表され、今後小千谷市がハザードマップを作成する河川です。
最大浸水想定区域などの情報は新潟県のHPから確認することができます。
| 山辺、城川、西小千谷、千谷地区 | 茶 郷 川 | 最大浸水想定区域図などはこちらから |
| 山辺、西小千谷地区 | 湯 殿 川 | 最大浸水想定区域図などはこちらから |
過去に作成・配布した洪水ハザードマップはこちら
過去に作成・配布した洪水避難地図(洪水ハザードマップ)はこちらから(別のページへ移動します)
信濃川のほかに、茶郷川・湯殿川・表沢川、茶郷川上流部、須川、焼田川の洪水避難地図も掲載しています。
防災関係情報
以下のホームページから土砂災害や信濃川の水位などの防災関係情報を取得することができます。
独自に情報収集する際の参考にしてください。
新潟県土砂災害警戒情報システム
土砂災害に関する情報(土砂災害危険度判定図、県内各地の雨量情報は、土砂災害危険箇所情報、土砂災害警戒情報発表状況等)は、以下のURLで見ることができます。
土砂災害発生の危険性の確認や自主的に避難する場合の判断材料とするためにぜひご活用ください。
パソコン版
新潟県土砂災害警戒情報システムはこちらから(別の窓が開きます)
携帯版
アドレス http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/sabou_m/(下記QRコードからアクセスできます)

気象庁・新潟地方気象台
パソコン版
気象庁・新潟地方気象台のホームページはこちらから(別の窓が開きます)
国土交通省 防災情報提供センター
パソコン版
国土交通省 防災情報提供センターのホームページはこちらから(別の窓が開きます)
国土交通省 川の防災情報
パソコン版
国土交通省 川の防災情報はこちらから(別の窓が開きます)
携帯版
アドレス http://i.river.go.jp/(下記QRコードからアクセスできます)

新潟県河川防災情報システム
パソコン版
新潟県河川防災情報システムはこちらから(別の窓が開きます)
携帯版
アドレス http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen_m/(下記QRコードからアクセスできます)

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト
信濃川水系緊急治水対策プロジェクトはこちらから(別の窓が開きます)
ハザードマップQ&A
Q1 ハザードマップとはどのようなものですか?
ハザードマップとは、災害が発生した場合に備えて、住民の方々がすばやく安全な場所に避難できることを目的に、被害が想定される区域と被害の程度、さらに避難場所などの情報を地図上に明示したものです。
Q2 ハザードマップはどのような効果がありますか?
前もって災害の被害を知ることができる、普段から災害に対する危機意識を持つことができる、何をすべきか、何が必要か判断でき、素早く避難することができるなどの効果が考えられます。
福島県郡山市での平成10年8月集中豪雨では、避難指示が出てから避難を行うまでの時間が、洪水ハザードマップを見たことがある人は、見たことがない人に比べて1時間も早いという報告もあります。
Q3 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域とは何ですか?
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは、土砂災害が発生した場合、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがある区域です。宅地又は建物の売買等にあたり、相手方に説明することが義務付けられています。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)とは、土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域です。特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制などが行われます。
土砂災害防止法に基づき、新潟県が調査、指定した土砂災害警戒区域は県内に約14,117箇所、土砂災害警戒区域は8,940箇所あります。
Q4 いつ避難すれば良いのですか?
小千谷市から高齢者等避難や避難指示が発令されたら、直ちに危険な場所から避難して下さい。テレビやラジオから得られる気象情報や新潟県土砂災害警戒情報システム等の各種情報により自ら判断し、事前に自主的に安全な場所に避難することが、自分の身を守る最良の方法です。
Q5 どの様な場合に高齢者避難や避難指示が発令されるのですか?
土砂災害のおそれがある場合は、新潟県土砂災害警戒情報システムにより提供される、土砂災害の危険度情報(前ぶれ注意レベル・警戒レベル・危険レベル)や気象情報等により総合的に判断し、住民の生命に危険が及ぶと認められる時に発令されます。
洪水のおそれがある場合は、洪水警報や大雨警報が発令され、河川の氾濫、浸水などのおそれがあり、住民の生命に危険が及ぶと認められる時に発令されます。
Q6 高齢者等避難とは何ですか?
災害が発生するおそれがある状況において、避難に時間を要する人(高齢者、障がいのある方、乳幼児等)とその支援者に早めに避難を開始してもらうために発令するものです。
その他の人は、避難指示が発令されたら速やかに避難できるように、避難の準備をするとともに、地域の状況に応じて早めの避難が望ましい場所に居住されている方は、このタイミングで自主的に避難してください。
Q7 避難指示と緊急安全確保の違いは何ですか?
避難指示は、災害が発生するおそれが高い状況で、市長から必要と認める地域や居住者等に対し発令されます。
避難指示が発令された際には危険な場所から、安全な場所へ全員避難をする必要があります。
緊急安全確保は、災害がすでに発生、または発生直前であったり、すでに発生していてもおかしくない状況で命が危険な状況に対し発令されます。
直ちに安全な場所で命を守る行動をとる必要がありますが、状況によっては避難場所等への移動が危険な状況です。自宅内のより安全な場所に移動(自宅の上の階や、がけから離れた部屋に移動)をしてください。
なお、避難指示及び緊急安全確保の発令は、災害対策基本法第60条第1項により市町村長の権限として規定されています。
Q8 自助・共助・公助とは何ですか?
「自助」とは、家庭で日頃から災害に備えたり、災害時には事前に避難するなど、自分の身を自分で守ることを言います。
「共助」とは、地域の災害時要援護者の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行うなど、周りの人たちと助け合うことを言います。
「公助」とは、市役所や消防・警察による救助活動や支援物資の提供など、公的支援のことを言います。
災害時には、自助・共助・公助が互いに連携し一体となることで、被害を最小限にできると共に、早期の復旧・復興につながるものとなります。
Q9 避難行動要支援者とはどのような方ですか?
災害時に自力で避難することが困難であり、避難する際に支援が必要な方のことです。避難行動要支援者の方々から名簿登録の申込みをいただき、自主防災組織等に名簿を提供することで、地域と連携し避難支援を行います。
避難行動要支援者名簿に登録できる方などの避難行動要支援者避難支援制度の詳細は下記ページ確認してください。
Q10 災害用伝言ダイヤル(171)とは何ですか?
「災害用伝言ダイヤル」は、被災地への通話がかかりにくい状態(ふくそう状態)になった時、被災地内の家族、親戚、知人等と安否の確認や緊急連絡を取れるようにするものです。
全国どこからでもメッセージを録音・再生することができ、公衆電話や一般家庭のダイヤル・プッシュ回線の電話はもちろんのこと、携帯電話でも利用が可能です。
災害用伝言板ダイヤルのイメージはこちらから[PDFファイル/895KB]
詳細は、運営している携帯電話各社の災害伝言板ページをご覧ください。
NTTドコモ https://www.docomo.ne.jp/info/disaster/disaster_board/index.html
KDDI(au) https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/
ソフトバンク https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/boards/
ワイモバイル https://www.ymobile.jp/service/dengon/
楽天モバイル https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/disaster_board/
※なお、同ダイヤルは災害時のみ利用が可能なサービスであり、災害伝言ダイヤルの提供開始や録音件数などはテレビ・ラジオ等でお知らせされます。