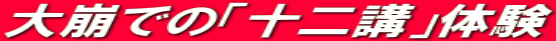

平成23年1月24日(月)朝、大崩に行きました。着いた後、集落の中を歩き、4m近くもある雪の壁に一同びっくり。2人の大崩の住民の方に名刺を渡しながらインタビューしました。
その後、大崩分館(旧大崩小学校)に行き、昨年5月の探検でもお世話になった大崩在住の伝統行事に詳しい方からから五穀豊穣・無病息災を願う神事「十二講」について教えていただきました。
以前、岩沢の第一区などでも行っていたそうですが、現在小千谷市内では、大崩集落、川井地区の一部で行われている程度だそうです。
最初に「十二講」についてのお話を聞きました。
以前は3月12日の朝食前に白山神社に家族(男性のみ)単位で行き、杉(楢;なら)の木で作った弓で、葦(あし)で作った矢を「十二はってん 山の神 山を平らに 矢をしめて」と言って矢を四方に放ったそうです。
男衆だけが参加し、子どもたちにはその日は藪に入ったり、弓矢に触ったりすることを禁じたそうです。この日は仕事は休みとしたそうです。
お供え物として、炊かない米を少量の水を加え、鉢ですりつぶしたもの(=団子よりは柔らかい?)を『わらづと=藁筒=納豆の入れ物みたいなの』に入れたものがあったようです。
<十二=神様(十二社)、はってん=発展、山を平らに=山の怒りがないように>
女性は家で赤飯を炊き、それを朝食とした
(女人禁制なのは、山の神が女だから)
この日以降は山に入ってもよい。
何百年も前から「十二講」を行っているらしい。
「十二講」について質問した後、実際に全員が葦で矢を作りました。矢に付ける紙や弓に「七・五・三」の印をつけるのは、縁起がよい数だからだそうです。 最後に、大崩分館の2階に上がって、弓で矢を放ちました。1回目はどの子も2〜3mしか飛ばなかったため、(2階の窓から)矢を拾いに行き、もう1回矢を放ちました。
2回目は10mくらい跳んだ子どももいました。
冬の大崩集落や大崩地区に古くから伝わる伝統行事などの貴重な体験をすることができました。
 |
 |
| 大崩の住民に名刺を渡しながらインタビューをしました! |
 |
 |
| 学校の近くよりも雪が多いね! |
あと少しで大崩分館だ! |
 |
 |
| 名刺を私ながら挨拶をしています |
葦で矢を作るんだよ |
 |
 |
| 矢に「七・五・三」の模様をつけるんだよ |
矢に切れ込みを入れて紙を取り付けます |
 |
 |
| ちょっときつめに紐を張ろう! |
弓にもに「七・五・三」の模様をつけるんだよ |
 |
 |
| こうやって飛ばすんだよ! |
 |
 |
| 遠くまで飛ばすぞ! |
 |
 |
| 2回目は、もっと飛ばすぞ! |
 |
 |
| 願いを込めて・・・ |
楽しい十二講だったね! |
 |
 |
| 滑りそうだよ、気をつけて! |
|
<「ふだんとごつたく」(篠田朝隆・著)より>
山の神のお祭りで供物(くもつ)から司祭(しさい)まで一切が家の男衆でやった。山の神は女でみにくい顔をし、女が手をかけるとうらやむと言われていた。決まった供物はしとぎ(からこ餅)で、ひたした米の柔らかくなった物をつぶして団子にした。祭具は弓で、杉の枝の皮をはぎ、ぬいごの縄で弦(つる)を作り、弧(こ)には七五三の黒模様をつけ、弓は葦(あし)でつけ木を羽根にした。祭り場は家の前が多く、祠(ほこら)のある家は村外れまで雪を踏み分けて行った。供物に塩引き魚も加わり、祭文(さいぶん)は、「十二八天山の神、山を平らに矢を締めて」と、唱えられ、天頂(てんちょう)、そして東西南北に矢を放った。この日まで山へ入ってはいけないと言われていた。
|




















