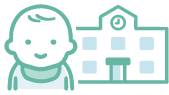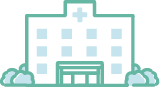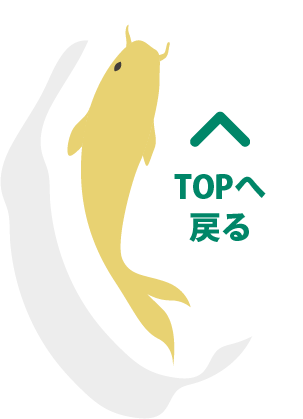本文
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度についてご案内します。
対象となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。手続きは不要です。)
- 65歳~74歳で、一定の障がいがある方(加入の際は申請が必要です。)
資格確認書について
75歳になられる方は、75歳の誕生日の前月に小千谷市から郵送します。
令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
なお、令和6年12月2日の被保険者証廃止に伴って、限度額認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行も廃止となりました。
今後は資格確認書へ任意記載事項として区分を記載します。
区分が記載された資格確認書が必要な方は、下記の持ち物をご用意の上、市役所市民生活課の窓口で申請してください。
※対象となるかご不明な場合は、事前に国保年金係(電話:0258-83-3516)へご確認ください。
持ち物
- 身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 資格確認書
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
資格確認書を紛失した場合
市役所市民生活課の窓口で再交付の手続きをしてください。
持ち物
- 身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
医療費の自己負担割合
医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。
| 所得区分 | 負担割合 | 判定条件 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
|
| 一般II ※令和4年10月1日~ |
2割 |
住民税課税所得が28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、
|
| 一般I | 1割 |
住民税課税世帯で、同一世帯に3割負担または2割負担の被保険者がいない方 |
| 住民税非課税世帯 (区分II) |
世帯全員が住民税非課税の方 |
|
| 住民税非課税世帯 (区分I) |
世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が次のどちらかに該当する方
※年金収入が806,700円未満のときは0円として計算します。 |
医療費の自己負担限度額(月額)
同一月に支払う医療費の自己負担限度額は次のとおりです。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者III※ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <4回目以降は140,100円> |
|
| 現役並み所得者II※ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <4回目以降は93,000円> |
|
| 現役並み所得者I※ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <4回目以降は44,400円> |
|
| 一般II | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方 <年間144,000円上限> |
57,600円 <4回目以降は44,400円> |
| 一般I | 18,000円 <年間144,000円上限> |
|
| 住民税非課税世帯(区分II) | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯(区分I) | 15,000円 | |
※現役並み所得者III:住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
※現役並み所得者II:住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
※現役並み所得者I:住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
医療費が高額になったとき(高額療養費)
同一月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として後日支給されます。
支給対象となる方には、受診月のおおむね3か月後に新潟県後期高齢者医療広域連合から支給申請案内が送付されます。
申請は初回のみで、2回目以降は初回に指定いただいた口座へ振り込みます。
後期高齢者医療広域連合について
後期高齢者医療制度は、新潟県内全ての市町村が加入する「新潟県後期高齢者医療広域連合」が運営主体です。
市町村は、各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。