| 2021�N3��25���i�j |
| ���C�����s���܂��� |
 |
 |
|
�@����3��25���i�j�̌ߑO���ɁA���C�����s���܂����B8���̋��E�����A�ސE�E�h�]�ňٓ��ɂȂ�܂����A2�����ĔC�p�Ƃ��ė��N�x�����Z�ŋΖ����܂��B
�@�ЊL���ł̋Ζ����Ō�ɂȂ�6���̋��E�����A�X�e�[�W�ŕʂ�̈��A�����܂����B���̌�A�����̑�\�����������A�S�Z�����Ŏ蔏�q���Ȃ���u�Z�Z�搶���肪�Ƃ��I�`�����搶���肪�Ƃ��I�`�v�ƃG�[���𑗂�܂����B�ԑ�����̌�A�q�ǂ������̗�̊Ԃ�ʂ���6�����ޏꂵ�܂����B�q�ǂ��������܂𗬂�����A�]�o�E���ɕ���������p�������A�ʂ��ɂ��݂܂����B
�@���N�x�́u�`�[�����������v�̃����o�[�ł̊������A�������Ō�ƂȂ�܂��B��N�ԁA��ς��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2021�N3��25���i�j |
| �Ђ܂��w�N�A���Ƃ��߂łƂ��������܂��I |
 |
 |
|
�@3���Ƃ͎v���Ȃ��悤�Ȑ�̂��ƁA3��24���i���j�ɁA��74�Ə؏����^�����s���܂����B�Ђ܂��w�N26�����S��������āA���Ə؏�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�ݍZ���́u���j���̌��t�v�ł́A�e�w�N�Ƒ��Ɛ��Ƃ̎v���o�₨�j���̌��t���A�f���œ͂����܂����B���̌�̑��Ɛ��́u��o�̌��t�v�ł́A1�N����6�N�܂ł̎v���o�Ƃ��ꂩ��̌��ӂ��A���X�ƌ���܂����B�����āA�����O�������́u�Ђ܂��̖v�������������܂����B���l���̕ی�҂̕��X�́A�ڌ���}����p�������܂����B
�@�Ō�̊w��������ݍZ���̏j�����I�������A�O���E���h�̐�ɁA�u�Ђ܂��w�N�v�ւ̏j�C�̉ԉ��苿���A���ꂢ�ȐF�̉������Ȃт��܂����B
�@�Ђ܂��w�N26�����A���C�ɕЊL���w�Z�𑃗����Ƃ��ł��܂����B����̂܂��܂��̊�������҂��Ă��܂��I
|
|
|
| 2021�N3��23���i�j |
| 3�w���I�Ǝ����A�����I���܂��� |
 |
 |
|
�@3��23���i�j��1���ɁA3�w���I�Ǝ����s���܂����B3�w���̎��Ɠ�����51���ŁA�N�Ԃł�208���i1�N����207���j�ł����B
�@�u3�w���́A�X�L�[�Ɛ}�H���A���Ɋ撣��܂����B2�N���ł́A�����Ɠ��ӂɂȂ肽���ł��B�c�v�u�ۓJ�̈��p�ŁA�`����`���悤��4�N���ɒ��J�ɋ����܂����B���w�Z�ł͂���ɐV�������ƂɃ`�������W���Ċ撣�肽���Ǝv���܂��B�v�c�I�Ǝ��ł́A1�E6�N���̑�\����A3�w�����̐U��Ԃ��V�N�x�̌��Ӕ��\������܂����B
�@�u�`���v�������p������A�V������g�Ƀ`�������W������ł����[������3�w���ɂȂ�܂����B������ی�҂̊F�l�̂������ł��B���肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2021�N3��22���i���j |
| 5�N���A���Ă��s�Љ�����c��Ɋ�t���܂��� |
 |
 |
|
�@5�N���́A�����̒��x�݂ɁA����J�s�Љ�����c��̕��X2���ɂ��Ă���t���܂����B���̂��ẮA�Љ�Ȃ���I�Ȋw�K�ŁA�����̈��B����̐��c�Ŏ��n�����Ă������������Ăł��B
�@���N�x�A�q�ǂ������́A�Љ�ȓ��ŐH�i���X�̖����w�K������A�R���i�ЂŌo�ϓI�ɍ����Ă�����X�������Ă��邱�Ƃ��w�肵�܂����B�����ŁA���B���番���Ă������������Ă��A��������̐l�ɖ𗧂Ăė~�����Ƃ����肢����A�u�t�[�h�o���N�v�Ɋ�t���邱�Ƃɂ����̂ł��B���ẮA�������c��o�R�Œ����n��̃t�[�h�o���N�ɓ͂����܂��B
�@�q�ǂ������́A�u���Ă������ɋꂵ��ł���l�̂��߂ɂȂ�Ɗ������B�v�u���т��ɐH�ׂ��Ȃ��l�����Ȃ��Ȃ鐢�̒��ɂȂ�Ɨǂ��ȁB�v�Ɗ��z�������܂����B��N�ł��ƁAPTA�o�U�[�Ŕ̔������蕟���{�ݓ��Ɋ�t�����肵�Ă��܂����B���B����̂��Ă��A�l�̖��ɗ��Ă��Ă悩�����ł��B
|
|
|
| 2021�N3��19���i���j |
| ��w�N�A����J�ɍZ�O�w�K�ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@�����̌ߑO���ɁA�����Ȃ̊w�K�̈�Ƃ��āA����J�s���̌����{�݂̌��w�ɍs���Ă��܂����B���w�����́A�u�ь�̗��v�Ǝs���}���قł��B
�@�u�傫�Ȃ��ꂢ�Ȍ�����ς�����ȁI�v�u�ь�Ɏ���Ȃ߂�ꂿ������I�v�ƁA�����������Ă����q�ǂ������B�����𓊂���Ƃ�������̋ь����Ă��܂����B
�@�s���}���قł́A�{�݂�������Ă��������A�{�̎���������Ă����������肵�܂����B�����āA���ۂɖ{��I�肵�܂����B
�@�A���ė�����A�q�ǂ������́u���x�͉Ƃ̐l�Ɩ{����ɍs�������ȁB�v�u�ь�����������ʂ�ʂ邵�Ă�����v�Ƙb���Ă��܂����B���ꂩ����A����J�s�S�̂ɂ������������ė~�����Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N3��17���i���j |
| ��搶�A���肪�Ƃ��������܂��� |
 |
 |
|
�@�����́A�p�ꋳ�琄�i�ψ��̐�搶�̋Ζ��ŏI���ł����B�T���搶�̑����10�����炨�߂��������A�S�Z�̊O���ꊈ���E�O����Ȃ̊w�K�Ɍg����Ă��������܂����B
�@���̎ʐ^�́A������1����4�N���̊O���ꊈ���ŁA�O���[�v�R�I���G���e�[�����O�̗������|�C���g�ŁA�q�ǂ������Ɖp��b�����Ă���ꂽ�Ƃ���ł��B�E�̎ʐ^�́A3����6�N���̊O����ȂŁu�l�����ăQ�[�������Ă���Ƃ���ł��B���ɂ��uNo�@���{��IEnglish�œ`���悤�Q�[���I�v�Ȃǂ����܂����B���ꂼ�ꗬ���傤�ȉp��ŁA�q�ǂ������ɘb�������Ă��������Ă��܂����B
�@��搶����́A�����̕����Łu���C��Hello!�ƈ��A�����Ă����Џ��݂̂�Ȃɉ��̂����T�y���݂ł����B���ꂩ����y�����O������w�у��x���A�b�v���ė~�����ł��BThank
you and see you!�v�Ƙb���Ă��������܂����B���N�x�͓��Z�ł̂��Ζ��͂Ȃ������ł����A�����C�ł��Ă��������B���܂ł��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2021�N3��16���i�j |
|
 |
 |
|
�@��T��3��12���i���j�̒��x�݂ɁA6�N����Ấu���肪�Ƃ��搶�̉�v���̈�قōs���܂����B���e�́A���Ċ���O���[�v�ł�������X�[�p�[�h�b�`�{�[���ł��B
�@���E����6�N���`�[���ŁA�����o�[�ウ��A�����i�B�l���F�����j��B�����i�����������F���y���݁j��2���������܂����B�ق�킩��B�������I���ƁA���̒j���E����6�N���j�q�ɂ��\�t�g�o���[�{�[���̍���������ь����܂����B�{�[�����J�[�u��z�C�b�v������A�����������邽�߂ɃX���C�f�B���O�L���b�`������ƁA��������̂P�`5�N���̊ϋq���吷��オ��I�݂�ȁA�C�����������������܂����B
�@6�N���́A�I�������u�ō��Ɋy���������B�܂���肽���B�v�u�搶���Ɋy����ł��炨���Ǝv�����̂ɁA�����������y���������B�v�Ƙb���Ă��܂����B�����ƁA���w�Z�̊y�����v���o�̂P�ɂȂ������Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2021�N3��12���i���j |
| �V�N�x�Ɍ����Ă̒����q�ǂ�����s���܂��� |
 |
 |
|
�@������3���ɁA�S�Z�ő�4���q�ǂ�����s���܂����B���ꂼ��̒����ɕ�����āA���N�x�̔��ȂƐV�N�x�Ɍ����Ă̏��������܂����B
�@�܂��A6�N���𒆐S�ɏW�����Ԃ�ᓹ�̕������E���A�Ȃǂɂ��āA�e�o�Z�ǂ̐U��Ԃ���s���܂����B�����āA�V�N�x�̖��������܂�ƁA���悢��i���5�N�����Ƀo�g���^�b�`�ł��B�V�o�Z�ǂ̕Ґ��̊m�F��������A���ۂɐV�ǒ���擪�ɕ��肵�܂����B�V�P�N��������o�Z�ǂł́A���ꂪ�}���ɍs���̂��E���ꂪ�莆�������ĐV1�N���̂���ɂ������ɂ������Ȃǂ����߂܂����B
�@���T����́A���ۂɐV�o�Z�ǂŕ���œo�Z���܂��B�q�ǂ��������m�⒬�̐l�ɂ����C�悭���������Ȃ���A���S�ɋC��t���ēo�Z���Ă��ė~�������̂ł��B�����̈��p�����I���A���̂܂ɂ����Ǝ��܂�2�T�Ԃ��܂����c�B
|
|
|
| 2021�N3��11���i�j |
|
 |
 |
|
�@���T��8�`10���̒��x�݂ɁA�T�N���̃X�|�[�c�ψ����ẤA�X�[�p�[�h�b�`�{�[�����s���܂����B1�O���[�v���̂��Ċ���ǑR�ŁA���ꂼ��1�������s���܂����B
�@�{�[���ɓ��Ă�ꂽ��A�O�ɏo��͕̂��ʂ̃h�b�`�{�[���Ɠ����ł����A����O��ɕ�����ĂԂ������̂ł͂���܂���B�@�{�[�����݂�Ȃ����œ�����B�i����̎q�ǂ��������Ɠ�����ƁA�R������w��������܂��B�j�A�G�ɂԂ�����A�G���������{�[������������L���b�`����ƁA�O�ɏo����������������B����2�_���傫���Ⴂ�܂��B���w�N���w�N���A��������{�[�����L���b�`����Ɓu�I�[�I�v�̊������オ��܂����B�X�|�[�c�ψ���I���̃z�C�b�X����炷�ƁA�ϋq�̎q�ǂ��������܂߂đ吷��オ��ł����B
�@5�N���̎q�ǂ������́u�U�N���₢���Ȋw�N�ƈꏏ�ɗV�Ԃ��Ƃ��ł��ėǂ������B�v�u�݂�Ȃ��y�������ɗV��ł�������A�听�����B�v�ƁA���z��b���Ă��܂����B�ݍZ���ɂƂ��āA6�N���ƈꏏ�Ɋ��𗬂��Ō�̎v���o�ɂȂ������Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2021�N3��10���i���j |
| 5�E6�N���A�L�����A����u������܂��� |
 |
 |
|
�@5�E6�N���́A�����3��9���i�j��3�E4���ɁA�����w�K�̈�Ƃ��ăL�����A����u������s���܂����B���ƁE⽍��Ƃ̖��V�@�G�搶���Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ��������āA���ۗ�������ɂ��ʂ�����e�����b���������܂����B
�@�u���{�l�́A�T�b�J�[���{�[��������X�|�[�c���Ǝv���Ă��邯��ǁA���[���b�p�̐l�����́A�{�[����D���X�|�[�c���Ǝv���Ă���B�v�u���[���b�p�̏��w���́A3�����̉ċx�݂ɗF�B�Ɠd�ԂŊC�O���s�ɏo�����܂��B�v�c�����̘b�����łȂ��A�C�^���A�̑�w�ŋ�������A�����̊O���ōu�������肵���o�������ƂɁA���{�Ɖ��Ă̍l������x�̈Ⴂ�Ȃǂ�b���Ă��������܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�����̍l����\�����邱�Ƃ͋�肾���ǁA�撣�肽���B�v�u�����͎c��̏��w�Z�����ł��c�����Ƃ��Ȃ��悤�ɁA��������Ɖ߂��������B�v�ƁA�u����U��Ԃ��Ă��܂����B��������l���E�v���M���邱�ƁA�`�������W�𑱂��邱�Ƃ��A�厖�ɂ��Ă����ė~�����Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N3��9���i�j |
| 3�N���A�����̌��w�K���s���܂����I |
 |
 |
|
�@3�N���́A���3��8���i���j��1�E2���ɁA�����w�K�̈�Ƃ��ĕ����̌��������s���܂����B����J�s�Љ�����c���2���̕����Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ��}�����A�Ԉ֎q�̌��Ƃ��N���^���̌������܂����B���ꂼ��̑̌��Ƃ��A�����鑤�Ɖ���鑤�̗�����̌����Ă݂܂����B
�@���N���^���̌��ł́A�����������Â炭�Ȃ�w�b�h�z����t������A���삪�����Ȃ艩�F�������Č����郁�K�l����������A�����Ȃ��Ă����Ԃɂ���т�t�����肵�āA�K�i�̏�艺��┢�ŏ��������̂��܂ޑ̌������܂����B�܂��A�Ԉ֎q�Œi����R�[����ʉ߂�����A�Ԉ֎q�������ŏ��~�E�i�[�ł��鎩���Ԃ������Ă����������肵�܂����B�@
�@�q�ǂ������́A�u����ȂɌ����Â炩������A���������ƒɂ������肷��Ƃ́A�v���Ă��Ȃ������B�v�u�����l�����������Ă��炷��ƁA�|���Ȃ��ȁB�v�u�̂��s���R�Ȑl�ɏo�������A���R�ɐ�����������悤�ɂȂ肽���B�v�ƁA�w�K��U��Ԃ��Ă��܂����B���̑̌����A����̐����ɂ������萶�������Ƃ����ł��ˁB
|
|
|
| 2021�N3��8���i���j |
| ���N�x�Ō�̊w�K�Q�ςƁA�w�N���k�����܂����I |
 |
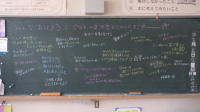 |
|
�@��T��3��5���i���j�̌ߌ�ɁA���N�x�Ō�̊w�K�Q�ςƊw�N���k�����܂����B�܂��A��2��w�Z�]���ψ����6���ɍs���A�ЊL���̖����̕��X�ɍ��N�x�̎�g�Ɨ��N�x�̕������ɂ��Ă��ӌ������������܂����B
�@�w�K�Q�ςł́A�e�w�N���H�v���Â炵�āA���������̐����̔��\���A����⓹���Ȃǂ̊w�K�����A�w�N�s���Ȃǂ��s���܂����B�����āA1�N�Ԃ̎q�ǂ������̐����̎p�����Ă��������܂����B���2���̎ʐ^�́A2�N����5�N���̕ی�҂̊F����́A�q�ǂ������ւ̉��������b�Z�[�W�ł��B�i1�N��������܂����B�j�w�N���k��̎��ɘb������ꂽ��A�����������肵�Ă��邱�Ƃ��A���Ɏc���Ă��������Ă��܂����B
�@�q�ǂ��������A�u���b�Z�[�W�����āA�܂�������C�����ɂȂ�܂����B�v�u�݂�Ȓ��ǂ��Ă����ˁB�ō��w�N�ł��撣���ĂˁB�Ƃ��A���낢�돑���Ă���Ă���B�v�ƁA�ƂĂ����ł��܂����B�����̊F����𒆐S�Ɏ��g��ł��������A��ς��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2021�N3��5���i���j |
| 1�N���A�y���݂Ȃ���^�����Ă��܂� |
 |
 |
|
�@1�N���́A2���ɃX�L�[���Ƃ�Z����Ɍ����Ẵ_���X����i���������ƁA���낢��ȓ�����g���đ̈�����Ă��܂��B
�@���̎ʐ^�́A�̈�p�_���g����2�l�g�ʼn^�����Ă���Ƃ���ł��B�ċz�����킹�āA����Ɩ_��|���Ȃ��悤�Ɏn�����Ɗ撣���Ă��܂����B����̂��Ƃ��z�����Ė_����������A�_�b�V���ő���̖_�����̂ł��B�܂��A�E�̎ʐ^�́A�����ێ��S�����Ă���Ƃ���ł��B2�`�[���ɕ�����āA�����̂����ۂ�����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���A�G�̃����o�[�̃n���J�`�̂����ۂ����ɍs���܂��B�����l���Ȃ���A�y����ł��܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�v������������������NJy���������B�v�u�܂������ȉ^�����������ȁB�v�Ƙb���Ă��܂����B�ǂ�ǂ�̂������Ƃ��A�D���ɂȂ��Ă����ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N3��3���i���j |
| �Ί炪���ӂꂽ�Z�N���𑗂��I�B |
 |
 |
|
�@��������Ɉ��������A�Z�N���𑗂��̑�3�e�ł��B�����́A���w�N�̊���ł��B
�@�u1�N���Ƃ�������ɗV��Ŋy���������ł��B���肪�Ƃ��B4�������2�N���B�V�P�N���̂���{�ɂȂ��Ă��������B�v�@�c6�N���́A�e�w�N�Ƃ̎v���o�����ƂƂ��ɁA�G�[���𑗂�܂����B�����āA�a�s�r�́u�_�C�i�}�C�g�v�̃_���X���I������A�S�Z�Łu�_�C�i�}�C�g�v��x��܂����B
�@�V����5�N�������o�[�́u���݂̖����W���[�v�̊���̌�A5�N���́A6�N�����狳���Ă�������u�،��V���v��x��܂����B�����āA�u���x�͎������̔Ԃł��B�Ђ܂��w�N�̊F��������p�����ЊL���w�Z���A�����Ɩ��邭���C�Ȋw�Z�ɂ��Ă����܂��I�v�ƁA������������p�����ӂ�����Ă���܂����B
�@���ꂼ��̊w�N�̎q�ǂ������́A�u�U�N�����狳������،��V�����݂�Ȃ̑O�Ŕ�I���邱�Ƃ��ł��ėǂ������B�v�u�A���R�[�����炦�ăe���V�����}�b�N�X�ɂȂ����B�v�ƁA�U��Ԃ��Ă��܂����B���̑��ɂ��A���E�����_���X�Ɖ́E����ʁc�łЂ܂��w�N�Ɂu�͂Ȃނ��v��܂����B���Ɛ��̂Ђ܂��w�N�ɂƂ��Ă��A�y�����v���o�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N3��2���i�j |
| �Ί炪���ӂꂽ�Z�N���𑗂��I�A |
 |
 |
|
�@����Ɉ��������āA�Z�N���𑗂��̑�2�e�ł��B�����́A���w�N�̊���ł��B
�@�u�|���̎��A������邱�ƂJ�ɋ����Ă���A�݂�Ȃ̌��{�ɂȂ��Ă���܂����B�v�u���肪�Ƃ��A���肪�Ƃ��A�Z�Z�������肪�Ƃ��B�v�c3�N���́A�u���肪�Ƃ��R�[���v��S�����܂����B�Q�l�܂��͂R�l�g�ŁA6�N����l��l�́u���܂łɏ����Ă���������ƁE�����Ă���������Ɓv���Љ�܂����B6�N���́A�Ƃꂭ�������ɁA�ł����������ɕ����Ă��܂����B
�@4�N���́A�����ʁv�����S�����܂����B�~�j�R���g�̌�A�K���|����6�N���̑�\5���Ƒ��ƒS�C��I�т܂����B�����āA�J�E���g�_�E���̌�ɂW���̑�\���Ђ��������ƁA�u6�N���͂ڂ������̂Ђ܂�肾�v�u�����Ȃ��ɑ��ւ͂����v�̐��ꖋ�����ꂢ�ɊJ���܂����B�S�Z�̎q�ǂ��������A���ꂢ�ɏ���ꂽ���ꖋ�ƉԐ���ɑ��тł����B
�@3�E4�N���̎q�ǂ������́A�u���肵�Ă���Ă��ꂵ�������v�u�݂�Ȃŏ��������鎞���狦�͂ł��Ă��ꂵ�������v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�S�Z�̎q�ǂ��������������C�����ɂȂ�܂����B
|
|
|
| 2021�N3��1���i���j |
| �Ί炪���ӂꂽ�Z�N���𑗂��I�@ |
 |
 |
|
�@��T��2��26���i���j��5���ԖڂɁA�������Ấu�Z�N���𑗂��v���s���܂����B���ꂼ��̊w�N���A�Z�N���ւ̊��ӂ̋C������`���܂����B�����͂��̑�1�e�A��w�N�ł��B
�@2�N���́A�Z�N���̓��ޏ�Ƃ͂��߂̌��t��S�����܂����B�u���r���v�̋Ȃɍ��킹�āA�����������l�����_���X��̂����ς��ɕ\�����āA�Z�N�����}���܂����B������6�N�����ޏꂷ��Ƃ��́A�S�Z�̎q�ǂ��������A2�N���̃_���X��^�����Ă݂�Ȃŗx��A��ꂪ��ɂȂ�܂����B
�@1�N���́A�u�h��������v�̋Ȃł̃_���X�ƁA�v���[���g�n����S�����܂����B�_���X�ł́A���킢���ߑ��𒅂āA��������`�ϊ������Ȃ���y�����x��܂����B�����āA�莆�̃v���[���g���A�Z�N���͊��������ɂ��̏�œǂ�ł��܂����B
�@1�E2�N���̎q�ǂ������́A�u�݂�Ȃ����肵�Ă���Ċ����������B�v�u���܂����ǂ�Ă悩�����B�v�u6�N���ɂ��肪�Ƃ���`�����Ă悩�����B�v�@�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B��l��l�̎q�ǂ��������A���������Ɗ���ł��ėǂ������ł��B�@�@
|
|
|
| 2021�N2��25���i�j |
| �X�L�[���s�s��A���s���܂����I |
 |
 |
|
�@�����̒������̎��ԂɁA�u�V�������w�Z�X�L�[�����z�w���X�L�[���v�Ɍ����Ă̑s�s����s���܂����B����s��ꂽ�u�s�e�P�X�L�[���v�̌��ʁA����J�s�̑�\�Ƃ���2�����A2��28���i���j�ɂ�����ɏo�ꂵ�܂��B
�@�X�|�[�c�ψ���̃��[�h�Łu�t���[�t���[�Z�Z�Z�v�u�D���A�D���A�����v�c�ƁA�S�Z�œ�l�ɃG�[���𑗂�܂����B��\�I�肩��́u���~�Ɍ��܂��Ă����S�����s���邱�ƂɂȂ�܂����B�S�����ڎw����2�l�Ŋ撣���Ă��܂��B�v�Ƃ̗͋������Ӕ��\������܂����B
�@�Z������A�ЊL���̕�����̊�t�Ŕ��킹�Ă����������X�L�[�̏Љ�ƁA3��ނ̃��b�N�X��h���Ďx���Ă������郏�b�N�X�}���̕��X�̘b�����܂����B���̑��ł��A�u���ӖY�ꂸ�A1�b�����o���v��������Ă���邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2021�N2��24���i���j |
| �Z�����p�W�Ɍ����Ď��g��ł��܂� |
 |
 |
|
�@�e�w�N�ł́A���A3��1���i���j����n�܂�Z�����p�W�Ɍ����āA��T�����肩��}�H�̍�i���ɔM�������Ă��܂��B���̎����́A�ǂ̊w�N���ʼn�����Ă��܂����B
�@�u�Ŗ̂͂��܂ŁA�C���N����`���t���Ȃ��Ƃ���ˁB�v�u���̒����Ƀo�����������āA�l���ɐL���Ă���A�ۂ��C���Ă�����B�v�@�c���j����5�N�����A�}�H���Ŏ����̍�i��������Ă��܂����B����̎q�ǂ��������A�T�|�[�g���Ȃ���i�߂Ă��܂����B�ʼn掆��Ŗ���O���āA�����̍�i���ŏ��Ɍ���Ƃ����A��ԃh�L�h�L���ċْ�����̂ł��B
�@�P�E�Q�N���͎��ʼn�A3�N���̓X�`�����ʼn�A4�N���ȏ�͖ؔʼn�����Ă��܂��B�w�N�ɂ���āA������������F�����Ă�����A���낢��Ȕʼn悪����܂��B�i�E�́A6�N���̍�i�ł��B�j���ꂩ��e�w�N�̘L���Ɍf�����Ă����܂��B
|
|
|
| 2021�N2��19���i���j |
| ���w�N�A2��ڂ̔��R�X�L�[�����ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@3�E4�N���́A������2�E3�E4�����g���āA���R�^��������2��ڂ̃X�L�[�ɍs���Ă��܂����B�O��̐���Ƃ͑ł��ĕς���āA��̌��������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�u�`�O���[�v���s���Ă���R�[�X�A�����Ƌ}�Ȃ��Ǒ��v���ȁH�v�@�u���v�ł��B�s���܂��傤��I�v�Ǝq�ǂ������B�w�N�����ŁA�`�E�a�E�b��3�O���[�v�ɕ�����āA�X�L�[���y���݂܂����B2��ڂ̍���́A�ł��邾������������}�ȎΖʂ��C�����悭���邱�Ƃ��A�߂��Ăɂ��܂����B�ŏ��́A�����̋N���ł��]��ł����q�ǂ������B�����������A����~��Ă��������ɁA�ǂ�ǂ��肭�Ȃ�܂����B
�@�q�ǂ������́A2��̔��R�^�������ł̃X�L�[�������I���āu�����œ]����NJy�����������A����͊���������đ�ς������I�v�u�X�L�[�A���܂��Ȃ����C������I�v�Ƃ��������z�������܂����B�����ƁA���N�x�͂���ɂ��܂��Ȃ��āA�C�����悭����邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2021�N2��18���i�j |
| 4�N���A�A���t�@�x�b�g�̕��K�����Ă��܂� |
 |
 |
|
�@4�N���́A���1���̊O���ꊈ���ŁA�A���t�@�x�b�g�̏������̕��K�����낢��Ȋ����������Ă���Ă��܂����B���Ƃ̍ŏ��ɂ͖���A�c�u�c�̋��ނ��g���Ẵt�H�j�b�N�X�i�����̗��K�j�Ɏ��g��ł��܂��B�����悭���Ă���R��L�̉��ɂ��āAALT�̐搶�ƈꏏ�ɐ�̈ʒu���m�F���Ȃ���J��Ԃ����ɏo���Ċm�F���Ă��܂����B
�@���ɁA�A���t�@�x�b�g�t���̓_��a����z�܂ŏ��ԂɂȂ��ł������Ȃ��Ɏ��g�݂܂����B�����ABC�̉̂������Ȃ���Ȃ��ł����ƁA�u�����ƁA����̓s�U�̊G����B�v�ƃs�U��p�t�F�̊G�����������Ă��܂����B�u�s�U�́A�A���t�@�x�b�g�ŏ����ƁA�����Q���������B���������s�b�U���������ˁB�v�ƍ��܂Ŋw�K�������Ƃ��v���o���Ȃ���A�X�y���������ʂ�����A���{��Ƃ̉��̈Ⴂ�ɋC�Â����肷�邱�Ƃ��ł��܂����B�Ō�ɂ́A6�`�[���ɕ�����āu�A���t�@�x�b�g�����`���Q�[���v���s���܂����B�搶���o�肵���A���t�@�x�b�g���A���̐l�̔w���Ɏw�ŏ����A�`���Ă����܂��B�Ō�̎q�ǂ��̓����ɁA�吷��オ��ł����B
�@�q�ǂ������́A�u�A���t�@�x�b�g�̏��Ԃ�����o���Ă����B�v�ut�Ƃ��͌`�����Ă��āA�w���ɏ����ē`����̂���������B�v�Ɗw�K��U��Ԃ��Ă��܂����B���낢��Ȋ������y���݂Ȃ�����K���āA�p��ɂ��e����ł����ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N2��17���i���j |
| 3�E4�N���A�ǂ������Ă��������܂��� |
 |
 |
|
�@�����̒��w�K�̎��ԁA3�E4�N���́A�ǂ��{�����e�B�A�̕��X�ɁA��^�G�{�⎆�ŋ���ǂ�ł��������܂����B�Ⴊ�~�肵���钆�A���N�x�Ō�̓ǂ��ɗ��Ă��������܂����B
�@3�N���ł́A����̋��ȏ��ł��w�K�����u���`���`�̖v����L���ɓǂ�ł��������܂����B�܂��A4�N���ł́A�u�������̂����v�@�Ƃ������ŋ��ŁA�n����茻���̕����c�Ƃ������̐[�����b��ǂ�ł��������܂����B�傫�ȊG�{�œǂ�ł������3�N���́A���Ƃł̊w�K���N�ǂɂ���Ă���ɐ[�܂������Ƃł��傤�B
�@���N�x�̓ǂ��́A�ЂƂ܂������ŏI���ł��B�q�ǂ������ɂƂ��āA��ς悢�o���ɂȂ�܂����B���N�x�́A2�w���ȍ~�Ŋ��������肢���Ȃ���Ȃ�܂���ł������A���N�x�͗\��ʂ肨�肢�ł���Ƃ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
|
|
|
| 2021�N2��15���i���j |
| �V�P�N���𗬉�E�ی�҉���s���܂��� |
 |
 |
|
�@��T���j����12���ߌ�ɁA���N�x�̂P�N�����}���Ă̌𗬉�ƕی�҉���s���܂����B�𗬉�ł́A��1�N���ƌ�5�N�����N������ƌ𗬂��܂����B�ی�҉�ł́A�ƒ닳��u������w�Ɍ����Ă̏������̐���������܂����B
�@��1�N���́A�����ȂŊw�K���Ă��邨�͂����₯��ʁE����Ƃ�E���܉Ȃǂ̗̐̂V�т��A�N������ɗD���������Ȃ���ꏏ�ɗV�т܂����B�����čŌ�ɁA�ЊL���w�Z���Љ�邨�莆���A��l��l�ɓn���܂����B
�@1�N���̎q�ǂ������́A�u�ْ��������ǁA�y����ł��炦�Ă悩�����B�v�u�����͑�ς��������ǁA�N�����݂�Ȋ��ł��Ă悩�����B�v�ƁA������U��Ԃ��Ă��܂����B4���Ɍ����āA1�N����5�N���A�����ĔN��������A���҂��c��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ɂ��S�z�Ȃ��ƁE�s���Ȃ��ƁE���k���������Ɠ�������܂�����A�w�Z�܂ł��A�����������B
|
|
|
| 2021�N2��12���i���j |
| 3�N���A������w�K�����܂��� |
 |
 |
|
�@3�N���́A����2/10�i���j��3���ɁA�����I�Ȋw�K�̎��Ԉ�Ƃ��āA��������̊w�K�����܂����B��҂Ǝ�b�ʖ�҂̕����Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ��������A�u������w�K�v���s���܂����B
�@��b��p���[�|�C���g�̉f���Ȃǂ��g���Ȃ���A�u��҂̓��퐶���̒��ł̍H�v�v��u��҂ƃR�~���j�P�[�V��������鎞�ɋC��t���ė~�������Ɓv�Ȃǂ��A��̓I�ɋ����Ă��炢�܂����B�����āA��{�I�Ȏ�b����K������A���ۂ̏�ʂ�z�肵�ă`�������W���Ă݂܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�O����A�������A��l���b�����Ƃ��厖�Ȃ��Ƃ����������B�v�u��b���킩��Ȃ��Ă��W�F�X�`���[�œ`��鎞������ƕ��������B�v�u�����s���R�Ȑl�̂��߂ɍH�v���ꂽ�������Ə��߂Ēm��܂����B�v�ȂǁA�w�K��U��Ԃ��Ă��܂����B���ꂩ�炳��ɁA�q�ǂ��������A���낢��ȏ�Q�������X�ɑ��Ă��A����̗���⊴�����Ɋ�肻����悤�ɂȂ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
|
|
|
| 2021�N2��10���i���j |
| 5�E6�N���A���ۗ������[�N�V���b�v��̌����܂��� |
 |
 |
|
�@�����̌ߑO���A5�E6�N���́A�����I�Ȋw�K�̎��Ԃ̈�Ƃ��āA�V�����ۏ���w�̊w���̊F������Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ��}�����āA���ۗ������[�N�V���b�v���s���܂����B�u�����������ē�����O?�@�`�R���i�ɂ���Ă�舫���������E�̕s�����`�v�Ƃ����e�[�}�ŁA�e�w�N�Ŋw�K���܂����B
�@�q�ǂ������́A�O���[�v���������˂��A�C�X�u���[�N����n�܂�A�����̌����[�N�≷�x�v���[�N��̌����܂����B�����āA�V�^�R���i�ɂ�鐢�E�̎q�ǂ������̎�����A�����ʐ^�Ō����Ă��炢�܂����B���̌�A��w�����e�O���[�v�̃t�@�V���e�[�^�[�i�����o�����E�i��ҁj�ɂȂ�A���E�n�}�Ɏq�ǂ������̋C�t���⊴�z���ʒu�Â��Ă���܂����B
�@�q�ǂ������́A���[�N�V���b�v���I��������Ɓu�����n���ɏZ��ł���̂ɁA����ȂɊi�������邱�Ƃɋ������B�v�u���������͌b�܂�Ă���B��������Ȃ��l�̂��߂ɁA���������ɂł��邱�Ƃ͂Ȃ낤�c�v�Ɗ��z�������܂����B���ꂩ����n���Ƃ�������ŗl�X�Ȃ��Ƃ��l������q�ǂ������ɁA�Ȃ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
|
|
|
| 2021�N2��9���i�j |
| 3�N���A����T�����\����s���܂��� |
 |
 |
|
�@3�N���́A���2�^8�i���j��2���ɁA�����w�K�̈�Ƃ��āu����T�����\��v���s���܂����B���q�l�Ƃ��āA�u�t�Ƃ��Đ���T���ɎQ�������������u�Ό�������v�̉��4���̕��ƁA4�N�����o�Ȃ��܂����B
�@�u����́A���ɑ�ɉԂɃT���K�j�A���R����܂��B���̈Ӗ��́c�v�@3�N���͔ǂ��ƂɎ��������̃|�X�^�[�̓��e�⒲�ׂ����Ƃ⊴�z�S���Ĕ��\���܂����B4�N���̎q�ǂ������́A���̔��\���Ď��₵����A�悩�����_�\�����肵�܂����B�܂��A�Ό�������̕�����́A���O�ɂ��肢�����q�ǂ������̎���ɁA���������Ă��������܂����B
�@3�N���̎q�ǂ������́A���\��I����āu�����������Ă��邱�Ƃ�������܂����B�v�u���A���������Ă���l���q�ǂ��̂���ɂ����ŗV��ł����Ƃ͎v���܂���ł����B�v�u�傫�Ȑ��Ŏ����̍l�����݂�Ȃɓ`�����Ă悩�����ł��B�v�u���ꂩ������R���ɂ��Ă���l�����邱�Ƃ�Y��Ȃ��B�v�ƁA������U��Ԃ��Ă��܂����B�ЊL�̎��R�L���ȁu����v����낤�Ɗ��Ă�����X�����邱�Ƃ��A�����ł��Ă悩�����Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N2��5���i���j |
| �X�L�[���s�s����s���܂��� |
 |
 |
|
�@�����̒������̎��ԂɁA�������{����鏬��J�s�e�P�X�L�[���E�s���X�L�[���̑s�s����s���܂����B���Z����́A2�����Q�����܂��B
�@�Z������́A���܂Ŏ��g��ł����X�L�[���S���̘J���ƁA�o�ꂷ��2���ւ̌��オ����܂����B���̌�A�S�Z�̎q�ǂ������̃G�[���ƁA��\�I��̌��Ӕ��\������܂����B�����ƁA�����́u�S�͂��o�����āA1�b��������o���I�v�u���ӂ�Y��Ȃ��v��2�_���撣���Ă���邱�Ƃł��傤�B
�@�����́A�R���i��Ŗ��ϋq�ł̑����{�ɂȂ�܂��B�������A����J�s���U�w�K�ہE�X�|�[�c�̃z�[���y�[�W����A�s�����xouTube�`�����l���̃��C�u�z�M�̃����N�����邻���ł��B����A�������Ȃ��炲�����������B
|
|
|
| 2021�N2��4���i�j |
| ��������p�����s���܂��� |
 |
 |
|
�@�����̒������̎��ԂɁA��������p�����s���܂����B�X�e�[�W��ɂ́A�ψ�����̐V���̈ψ��������т܂����B
�@�u�ŏ��́A���܂��s���Ȃ����Ƃ�����܂������A�݂�Ȃňӌ����o�������C�����āA�㔼�͊������X���[�Y�ɂȂ�܂����B���N�x���A��肪�������Ƃ��Ă��C�����Ȃ���撣���Ă��������B�v�c���ψ�����l��l����A�����̐U��Ԃ��V�ψ���ւ̊��҂��b����܂����B���̌�A�ψ���t�@�C���Ǝ�������̈����p���ꂽ��A�V�ψ����̂�����������܂����B�����ł��A���ꂼ��̈ψ���ł���낤�Ƃ��邱�Ƃ⎩���̌��ӂ����X�ƌ���܂����B
�@���T����A4�E5�N����̂̈ψ�����ɐ�ւ���Ă��܂��B���ɁA���߂Ĉψ�����ɎQ�����Ă���4�N���́A������Ċ撣���Ă��܂��B����͌ۓJ���p���ł������A���ƂɌ����Ċ������A�������p����Ă����܂��ˁB
|
|
|
| 2021�N2��3���i���j |
| �Z���̂v���|�e���H�����i��ł��܂� |
 |
 |
|
�@��T����Ǝ҂��Z�ɓ��ŁA�v���|�e���̍H����i�߂Ă���Ă��܂��B�e�Z�ɂ̊e�K�ɃA�N�Z�X�|�C���g��ݒu���A�^�u���b�g�[������C���^�[�l�b�g�ɐڑ��ł���悤�ɂ��邽�߂̍H���ł��B
�@���̕��j�ɏ]���A����J�s�ł͗ߘa2�N�x���܂łɁA�q�ǂ���l���̃^�u���b�g�����܂��B����ɔ����A���e�w�Z��Wi-Fi�H���������Ă���̂ł��B���T�ɂ́A�^�u���b�g���[�d�E�i�[���邽�߂̍H���╨�i�̔[�����n�܂�܂��B
�@���ۂɎq�ǂ��������g����悤�ɂȂ�̂́A�V�N�x����ł��B�E������́u�ǂ�Ȃ��Ƃ��ł��邩�A���N���N���܂��B�v�Ƃ��������������Ă��܂����B���������E�����A����̔g�ɏ��x��Ȃ��悤�A���p�̕��@�����C���Ă��������Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N2��2���i�j |
| 1�N���A�����͉J�ŃX�L�[���Ƃ��c |
 |
 |
|
�@�����́A�c�O�Ȃ��璩����J���~���Ă��āA�\�肳��Ă���1�E2�N���̃X�L�[���Ƃ��ł��܂���ł����B
�@�����ŁA1�N���́A�̈�قŒZ�꒵�т��g���āA�삯���꒵�тŃ����[��������A���ɂ������������肵�܂����B12������A����Ŕ��̎����т����K���āA�������܂��Ȃ�܂����B
�@��T�́A�V�C�ɂ��b�܂�A�E�̎ʐ^�̂悤�ɃO���E���h�ŃX�L�[���ł��܂����B�X�g�b�N�Ȃ��ŁA������ɕ�������]��ł��X���[�Y�ɗ����オ������ł���悤�ɂȂ�܂����B�̈�قŃX�L�[�𗚂����K�������̂ŁA�������Еt����������ł����B
�@1�N���̎q�ǂ������́A�u�X�L�[�͓]�Ԃ��NJy�����ȁB�v�u���̓X�L�[���ł���Ƃ����ˁB�v�Ƙb���Ă��܂����B���K���Ƃɂ��܂��Ȃ�̂ŁA�V�C�Ɍb�܂��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N1��29���i���j |
| �ۓJ���p����w�K�Q�ς��s���܂��� |
 |
 |
|
�@����ŋC�����Ăщ����钆�A�����̌ߌ�ɌۓJ���p����w�K�Q�ρA�w�N���k��A�o�s�`��\�ψ���Ȃǂ����{���܂����B��������̕ی�҂̊F�l�ɂ����Z���������A��ς��肪�Ƃ��������܂����B
�@�ۓJ���p���ł́A�R���i�Ή��ŁA4�`6�N�̎q�ǂ������ƕی�҂̕��X�݂̂ōs���܂����B�V���w������u�F����p�����`����������������p���܂��B�v�Ƃ̌��Ӕ��\�ƁA�Ђ���E�ȂȂ���ۓJ���̗͋������t������܂����B�܂��A5���̎��ƎQ�ςł́A���ꂼ��̊w�N�ō���E�Z���𒆐S�Ɏq�ǂ������̊w�K�̗l�q�����Ă��������܂����B�w�N���k��ł́A�e���ƒ��w�Z�ʼnۑ�E���ɂȂ��Ă���I�����C���Q�[���Ȃǂɂ��āA���������Ă��������܂����B
�@���ꂼ��̏�ʂł��ꂼ�ꐬ�ʂ����܂�āA�ƂĂ��悩�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
|
|
|
| 2021�N1��28���i�j |
| ���R�^�������ŁA���w�N�X�L�[���s���܂��� |
 |
 |
|
�@5�E6�N���́A�����̌ߑO���ɏ���J�̔��R�^�������Ƀo�X�ōs���A�m���f�B�b�N�X�L�[�����Ă��܂����B���܂�̃X�L�[���a�̒��A�ЊL���w�Z�̃O���E���h�ł͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��A�����������~�����K�����܂����B
�@�܂��A���R�ȃO���E���h����������l�q����A�`�E�a�E�b�̂R�O���[�v�ɕ�����܂����B�`�R�[�X�͂Q�����R�[�X���A�a�R�[�X�͍�ƂP�����R�[�X���A�b�R�[�X�͍�𒆐S�Ɋ���܂����B������`�������W���邤���ɁA�q�ǂ�����������]���ɁA�X�s�[�h�ɂ�����Ċ����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�q�ǂ������́A�u�|���������ǁA���邱�Ƃ��ł��ėǂ������B�v�u���̂������J�����[����܂����B�y���������B�v�Ɨ��K��U��Ԃ��Ă��܂����B
�@2���ɓ����Ă���A������x���R�ɍs���܂��B����ɁA�����������o�����X�悭��������A�C�����悭���艺�肽��ł���悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B�@
|
|
|
| 2021�N1��27���i���j |
| �u�Z����v�̂��߂̑�\�ψ���J����܂��� |
 |
 |
|
�@�����̒��x�݂ɁA5�N���̑����ψ����Â̑�\�ψ���J����܂����B�����̃e�[�}�́A2��26���i���j�ɗ\�肳��Ă���u�Z�N���𑗂��v�̃X���[�K������e�A�������S�ɂ��Ăł����B
�@�Q���҂́A�P�`�T�N���̃N���X��\�ƁA�P�E�Q�N���̐搶�ł��B�e�N���X�ł̘b�����������ƂɁA�R�̃X���[�K���Ă���P��I�т܂����B�u�Ђ܂��̂悤�ɂƂ������t�������v�Ȃǂ̈ӌ����o�āA�ŏI�I�Ɂu��������̂Ђ܂��w�N�I�Ђ܂��̂悤�ɂ����₯�I�v�Ɍ��܂�܂����B
�@�����ψ����N���X��\�̎q�ǂ������́A�u���߂Ă̑�\�ψ���ŋْ������B�v�u�U�N���Ɋ��ł��炦��悤�ȘZ����ɂ������B�v�Ƙb���Ă��܂����B�������܂����������S�ɉ����āA�����Ɍ����Ċe�w�N�����K�⏀�������Ă����܂��B�����ƁA���ӂ̋C���������ӂ��f�G�ȉ�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2021�N1��26���i�j |
| �V�ψ��������J����܂��� |
 |
 |
|
�@������6���ɁA���݂̖؎�����́u�ߘa3�N�x�V�ψ����������v���A�����o���ōs���܂����B���N�x�̈ψ���̔��Ȃ܂��āA5�N�����A�V�N�x�̊e�ψ���̌v��𗧈Ă������̂��A4�N����6�N���ɐ������܂����B
�@�u���������ψ���̏펞�����́A�T�ł���B�����~���B�c�v�e�ψ���A�����̖ڕW���Ȋ����A�Q�N�x����̈����p���E���P�_�Ȃǂ����������A�u���K�N�C�Y�v���o���܂����B�q�ǂ������́A�O����⁛�~�N�C�Y�Ɋy���݂Ȃ瓚���Ă��܂����B�����āA4�N������e�ψ���ɂ�������̎��₪���ꂽ��A6�N���̋��ψ�������͉������������b�Z�[�W������ꂽ�肵�܂����B
�@5�N���̎q�ǂ������́A������I�������A�u�ψ�����͑�ς����NJ撣�肽���B�v�u�V�������g�݂��ł���悤�ɁA�v��𗧂ĂĂ��������B�v�ƁA���ӂ�V���ɂ��Ă��܂����B���T�ɂ́A4�N���̈ψ���������܂�A2��4���ɂ͈ψ�����p�����\�肳��Ă��܂��B
|
|
|
| 2021�N1��25���i���j |
| 2�N���A�����悤�����у����h�ɏ��ҁI |
 |
 |
|
�@2�N���́A��T22���i���j��4���ɁA1�N���Ƌ��E���������āA���������ł�������̂��X���^�c����u�����悤�����у����h�v���J���܂����B���܂Ŋw�K���Ă��������Ȃ́u��������Â���v�̂܂Ƃ߂̊����Ƃ��čs���܂����B
�@2�N���̗V�у����h�ɂ́A�u�u�[�������Ƃ���v�u�~�X�^�[�܂Ƃ��āv�u�W�����v�Ń|�������h�v�u�ӂ˂�v�c�ȂǁA�P�P�̂��X������܂����B���ꂼ�ꂨ�X�ł́A1�N���ɃQ�[�������������A�V�ѕ��̌��{����������A���_�𐔂�����ƁA2�N���������̖������S���A�y���݂Ȃ������Ă��܂����B1�N���⋳�E�����A���낢��Ȃ��X������ăQ�[�����y����ł��܂����B
�@�u�����悤�����у����h�v���I��������ƁA2�N���̎q�ǂ������́A�u�������q�����đ�ς������B�v�u��������̂�����������ǁA�y����ł��炦�Ă悩�����B�v�Ɗ�����U��Ԃ��Ă��܂����B��������������Ċy���ނ����łȂ��A���������Ōv�悵�Ȃ��瑼�̐l�ɂ��y����ł��炤�o�����ł��āA�悩�����Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2021�N1��21���i�j |
| �~�G�Ԃ̔��P�������{���܂��� |
 |
 |
|
�@������3���ɁA��3����P�������{���܂����B���N�́A�z��ʂ�ɂ�������̐ϐႪ���钆�ŁA�S�Z�Ŕ��ꏊ����o�H���m�F���܂����B
�@�q�ǂ������́A���x���Ɓu���J�n�I�v�̕����̌�A�h�Г��ЂƖh�����E���C�p�ŁA�_�ЂɌ��������H�ɔ����J�n���܂����B�ǂ̊w�N���q�ǂ������́A���̓r����ҋ@���Ă��鎞�E�Z�ɂɖ߂鎞���Â��Ɏw�����A���R�ƍs�����Ă��āA�ƂĂ����h�ł����B
�@�����ɖ߂�����̍Z�������ŁA����J�s��V�������A�u�ፑ�v�ł��邱�Ƃ����グ�܂����B�n�k��Ύ��ȂǂŔ��鎞�ɁA���̋G�߂Ƃ��낢��ȓ_�Ŏ���̏�����Ă��邱�Ƃ��m�F���܂����B��ЊQ�ɒ��ʂ��Ă��A�ł��邾����ÂɑΏ��ł���l�ɂȂ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
|
|
|
| 2021�N1��20���i���j |
| 4�E5�N���A�ۓJ���p���Ɍ����āI |
 |
 |
|
�@4.5�N���́A������6���ɁA�ۓJ�����p���Ɍ����Ă̗��K�����܂����B��N�ł��ƁA�ۓJ���p����11�����ɍs���Ă��܂������A���N�x�͎q�ǂ�������2�w���̖Z�������ɘa���邽�߂ɁA1��29���i���j�̎��ƎQ�ς̓��ɍs���܂��B
�@6�N�����A5�N���ɒ��x�݂��g���ċ�����p�́A11�����猩���܂����B12���ɂ́A5�N���̎w���҂�ۑ��̃I�[�f�B�V�������I���A�p�[�g�����܂�܂����B�����A���x�݂Ɏ�����K����p�����������܂��B�ŋ߂́A4�E5�N�����A1�^29�i���j�Ɍ����āA���Ǝ��Ԃ��g���Ĉꏏ�ɑ̈�قŗ��K���Ă��܂��B
�@�q�ǂ������́u�w���҂����邱�Ɓv�u�݂�ȂƓ��������킹�邱�Ɓv����Ɉӎ����ė��K���Ă��܂��B���N�x�̈��p���́A�R���i�Ή��ŁA4�E5�E6�N��6�N���̕ی�҂̕��X�݂̂ōs���\��ł��B��낵�����肢���܂��B
|
|
|
| 2021�N1��19���i�j |
| ���w�N�A�X�L�[���Ƃ��n�܂�܂��� |
 |
 |
|
�@5�E6�N���́A������1�E2���ɁA���ܐ��Ⴊ���������钆�A�̈�ŃN���X�J���g���[�X�L�[���s���܂����B�w�N�ł̃X�L�[���Ƃ́A�S�Z�ō��������߂Ăł��B
�@�X�L�[���̎q�ǂ������̌��{��������A�O���E���h�̕��n���g���āA���i������_�C�A�S�i������K���܂����B�u�Z�Z����A���������i�ނȁ`�B�v�@���̌�A����g���Ċ��艺�����K�����܂����B�N���J���̃X�L�[�́A�����Ƃ��Œ肳��Ă��Ȃ��̂ŁA�^���ɑ̏d�������Ă��Ȃ��Ɠ]��ł��܂��̂ł��B�q�ǂ������́A�u�����������ǁA�y���������B���͂����Ƒ������肽���B�v�u�������̂��y�����B�������R�֊���ɍs�������B�v�ƁA�v���Ԃ�̃X�L�[�̊��G�ɁA�y����ł��܂����B�@
�@���T�ɂ́A1��ڂ̔��R�^�������ł̃X�L�[���Ƃ�����܂��B���������A�y�����A�C�����悭�����ė����Ƃ����ł��B
|
|
|
| 2021�N1��18���i���j |
| �X�L�[���̗��K���n�܂�܂����B |
 |
 |
|
�@�X�L�[���́A�~�x�݂���ЊL�N���J������̋��͂āA���R�^�������ŗ��K���J�n���Ă��܂��B�Z���ł��A��T���琅�j�Ƌ��j�̕��ی���g���āA���K���n�߂܂����B
�@15���i���j�̗��K�ł́A�_�C�A�S�i���␄�i�����Ȃǂ𒆐S�ɗ��K���܂����B�u�O�̃X�L�[�ɑ̏d���悹�āA�Б��ɒ�������Ă����B�v�u�O�ɐL�яオ��悤�ɂ��āA�X�g�b�N��˂��ĉ�����v�c�@�����Ŋ��o���m���߂Ȃ���A��{��{���K���Ă����܂��B
�@�q�ǂ������́A�u�����Ȃ��Ċy�����v�u�����ɂ��Ȃ�v�ƁA���z��b���Ă��܂����B���ی�Ɏ�����K���Ԃ͑�ϒZ���ł����A�݂�ȂŏW�����Ď��g��ł������Ƃł��傤�B�����āA�����Ƌꂵ�������z���āA�����̗͂�L���Ă����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
|
|
|
| 2021�N1��15���i���j |
| 3�N���A�ǂ�����Ƌʂɓd�C���ʂ邩�H |
 |
 |
|
�@3�N���́A���ȁu����������悤�v�̊w�K�ŁA�����͓d�C��ʂ����Ƃ�������ʂ��Ċw��ł��܂��B������5���ł́A�q�ǂ������́u�A���~�ʂ̂܂�肪�A�d�C��ʂ��Ȃ��̂͂Ȃ����낤�H�v�Ƃ����^����A������ʂ��ĒT��܂����B
�@�q�ǂ������̗\�z�́A�u�����Ƀe�[�v���͂��Ă���̂ł́H�v�u�t�B�������͂��Ă����Ă���܂��Ă���̂ł́H�v�ł����B�����ŁA�ʂ̓d�C��ʂ��Ȃ��Ƃ�����A���₷���2�����͂����āA���d���̖����肪�t�����ׂ܂����B�q�ǂ�������2�`3�l�g�ɂȂ��āA���͂��ċʂ̕\�ʂ̓h�����͂����A���d�����t�������������܂����B
�@����ƁA������������u�t�����`�I�搶�A�t������`�I�v�Ƃ̐��B�q�ǂ������́u���₷��ł͂�������A����ς�����v�u�͂����ƐF���ς���ċ������łĂ����v�ƁA�������番���������Ƃ⊴�z��b���Ă��܂����B�d�C�̕s�v�c�ɁA�܂�����邱�Ƃ��ł��܂����B
|
|
|
| 2021�N1��14���i�j |
| �����́A�Z�������ߑ��̂Q���ڂł��� |
 |
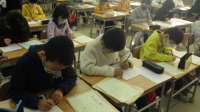 |
|
�@�����́A����Ɉ��������Z�������ߑ��s���Ă��܂����B�S�E�U�N���������o���łQ���Ԃ��A�P�E�Q�N�����������łP���Ԏ��g�݂܂����B
�@���܂ŖѕM�̎�g�̗l�q�����`�����Ă����̂ŁA�P�E�Q�N�̍d�M�̗l�q�����`�����܂��B�V�t�ɂ悭�����u�t�̊C�v�Ƃ����Ղ̋Ȃ��Ȃ���A���J�ɏ������߂������܂����B
�@�P�N���́u�^�̐����ӎ����Ȃ���A�����v���߂��ĂɎ��g�݂܂����B�~�x�݂ɉƂł����P���Ă��������W�����Ȃ��珑���i�߂Ă��܂����B
�@�Q�N���́u�Ƃ߁E�͂ˁE�͂炢�E����E�܂���ɋC��t���āA���������`�ŏ����v���߂��ĂɎ��g�݂܂����B�܂��A���M�̎�������p���ɂ��C��t���܂����B
�@���T�P�^20�i���j����A�e�w�N�̘L���ɍ�i���f������܂��B���ƎQ�ς̐܂ɁA�������������B
|
|
|
| 2021�N1��13���i���j |
| �Z�������ߑ��n�܂�܂��� |
 |
 |
|
�@�~�Ⴊ��i�����J�ɕς���������A�Z�������ߑ��n�܂�܂����B�R�N���ȏ�́A���̎����o���̊W�Ŏ��{������U���čs���Ă��܂��B
�@�����́A�R�N���E�T�N�����Q���Ԃ��g���āA�����߂Ɏ��g�݂܂����B�R�N���́u�n�M�Ɛ܂�ɋC��t���āA���J�ɏ������I�v�A�T�N���́u12���ɏK�������ƂƓ~�x�݂̐��ʂ��o�����I�v�ɁA���ɋC��t���ă`�������W���܂����B
�@�u���J�ɏ�����悤�ɂȂ����I�v�Ǝq�ǂ��������b���Ă��܂����B�~�x�݂̗��K�̐��ʂ�����A�Q�w���̍�i�Ɣ�ׂāA�u�����E�傫���v������悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�ׂ��M���g���Ė��O���o�����X�悭������悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@���̊w�N���A���ꂩ��u�S�W���v�Ŏ��g��ł����܂��B
|
|
|
| 2021�N1��12���i�j |
| 3�w���n�Ǝ��A���C�ɃX�^�[�g���܂��� |
 |
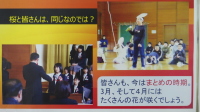 |
|
�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�N��������ɂ݂܂�ꂽ�V�����B��N������������̐�̒��ŁA3�w�����X�^�[�g���܂����B
�@�V�C�\��ő��x���߂���Ă��܂����̂ŁA�n�Ǝ���3���ɕύX���A�W�c���Z�ɐ�ւ��܂����B
�@����Ȓ��A�n�Ǝ��ł́A��l�̑�\��������u3�w���A�Z���Ɗ�������Ɋ撣�肽���B�v�u�ۓJ���̑��w���ɂȂ����̂ŁA������������p�������B�v�Ƃ̌��Ӕ��\������܂����B�Z������́A�u���̉ԉ�͊����Ŗڂ��o�܂��A�t��ڎw���Ă��ꂩ�炾��傫���Ȃ�B�F������A�܂Ƃ߁E�����̎O�w���Ɏ����̉ԉ��傫�����Ă��������B�v�Ƃ����b�����܂����B
�@��l��l�̎q�ǂ������ɂƂ��āA���S�E���S�Ŏ��葽��3�w���ɂȂ�悤�Ɏx�����Ă��������Ǝv���܂��B�������E�����͂����肢���܂��B
|
|
|
| 2020�N12��25���i���j |
| 2�w�����A�����ɏI�����܂��� |
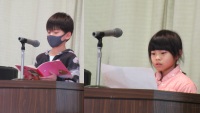 |
 |
|
�@���12��24��(�j�ɁA85���Ԃ�2�w���������I�����܂����B�傫�Ȏ����E���́A�����Ċ����ǂ̗��s�����Ȃ��A�ǂ������Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�u���݂̃L�b�Y�w�у����h�ł́A�݂�ȂƉ��ƐS�����킹�āA�傫���������邱�Ƃ��ł��܂����B�c�v�u���ɁA�Z�����撣�邱�Ƃ��ł��܂����B�c�v4���̏I�Ǝ��ł́A2�l�̑�\�������A2�w���Ɋ撣�������ƁE�S�Ɏc�������Ƃ\���܂����B�����āA�Z���̍u�b�ł́A�q�ǂ������́u�Ί�Ɛ^���Ȋ፷���v���ʂ��Ă���ʐ^���g���āA2�w����U��Ԃ�܂����B
�@�e�����ł��A�ʒm�\��z������A����b�J�[�Ȃǂ̕Еt���������肵�āA2�w������߂�����܂����B�~�x�݂��A�q�ǂ��������A�y�������C�Ɍ��N�ʼn߂����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
�@�F����A�悢���N�����}�����������B
|
|
|
| 2020�N12��23���i���j |
| 4�N���A�N���X�}�X�E�H�[�N�����[�����܂����I |
 |
 |
|
�@4�N���́A������1���̊O���ꊈ���Łu�w�f�������@walk rally�v�����܂����B2�w���Ɋw�K�����p��\���̂܂Ƃ߂Ƃ��āA�O���[�v���ƂɂV�̃`�F�b�N�|�C���g�����܂����B
�@�h�v�������@do you want for X'mas?" �`�F�b�N�|�C���g�ł́A�T���^�N���[�X��g�i�J�C�E�_�[�X�x�[�_�[��"Merry christmas!"�ƌ�������A�����̗~�������̓����p��œ`���܂��B���̌�A����Ɏ����������T�C������������肵�܂����B�܂��A���ɂ��w�������N�C�Y�ɓ�������A�U����Ă����A���t�@�x�b�g����ł��錾�t���������肵�܂����B
�@�q�ǂ������́A�u���낢��Ȑ搶�̗~�������������Ă悩�����B�v�u�C�^���A�ł́A�������v���[���g�������Ă��邱�Ƃ�m���Ăт����肵���B�u���܂Ŋw�K�������Ƃ�U��Ԃ�Ȃ���A�y�����O����̕����ł����B�v�Ɗ��z��b���Ă��܂����B�ƂĂ��y�����A�O���ꊈ���̂܂Ƃߊw�K�ɂȂ�܂����B
|
|
|
| 2020�N12��22���i�j |
| �X�L�[���A�x�[�X���b�N�X�������܂����I |
 |
 |
|
�@��T����A�X�L�[���́A�����̎g���X�L�[�Ƀ��b�N�X���������Ă��܂��B�N���X�J���g���[�X�L�[�́A���x�����b�N�X�������Ă͂͂����A�����Ă͂͂������Ȃ��犊���ʂ�����悤�ɂ��Ă����܂��B
�@���T���A�X�L�[���̎q�ǂ������́A�S���̐E���ƒ��x�݂Ƀ��b�N�X��Ƃ����Ă��܂��B�A�C������u���V�E�X�N���C�p�[�c�ȂǁA���낢��ȓ�����g���̂ł��B�����āA�u���V���A�L���ׂ̍����ʼn��i�K�������Ă����܂��B���Ԃ���Ԃ��A�ƂĂ��������Ƃł��B
�@�X�L�[���̎q�ǂ������́A�u������NJy�����I�v�u�������肽���I�v�Ƙb���Ȃ���A��Ƃ����Ă��܂����B����J�̔��R�^���������A�N���J���R�[�X���I�[�v�����܂����B�~�x�݂���́A���悢����ł̗��K���n�܂邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N12��18���i���j |
| �������߂Ɏ��g��ł��܂�! |
 |
 |
|
�@��T���炢����A3�N���ȏ�̊w�N�ł́A�ѕM�ɂ�鏑�����߂Ɏ��g��ł��܂��B���N�́A���Ɏ����o���Ńu���[�V�[�g��~���āA�����G�Ń`�������W���Ă��܂��B
�@�u������̕G�����̒��S���ɂ���悤�ɁA������2���������č���܂��B�v�u�Z����E�ׂ���E�������������邩��A������E������E�傫�������ڗ����܂��B�v�c�@���ꂼ��̊w�N�̃`�������W���Ă��鎚�́A3�N�u���̏o�v4�N�u�������v5�N�u�ጎ�ԁv6�N�u���t�̕��v�ł��B���N�́A���Ɂu���E��E���v�ȂǁA��������������悤�ł��B
�@2�w���ɂ��������w�Z�ŗ��K������A�~�x�݂̉ۑ�Ƃ��Ă��`�������W���܂��B�u�]������邱�Ƃ⋭������邱�Ɓv�ɋC��t���ė��K�ł���ƁA����ɏ�B����ł��傤�B�x�ݖ����ɂ́A�Z���������ߑ�������܂��B��l��l�������̂�����i���ł���Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N12��17���i�j |
| 1�E2�N���A�R�[�f�B�l�[�V�����g���[�j���O�Ƀ`�������W�I |
 |
 |
|
�@1�E2�N���́A��X�T�ƍ��T�ɁA2��˃R�[�`����u�R�[�f�B�l�[�V�����g���[�j���O�v�����Ă��������܂����B�����̗̑̂l�X�ȓ������ł���͂���މ^���ł��B
�@1��ڂł́A1�N���́A�t���t�[�v���g���āA�f�����W�����v�����肭�������肷�铮����̌����܂����B2�N���́A�~�j�n�[�h�����g���āA����Ȃ���W�����v�����ł̗l�X�ȓ����Ƀ`�������W���܂����B2��ڂł�2�w�N�Ƃ��A����̏���������W�����v���Č�����ς����肷�铮���Ƀ`�������W���܂����B�q�ǂ������́A�y�����̌���ʂ��āA���Y�����厖�Ȃ��Ƃ�g�̂������̎v���悤�ɑ��邱�Ƃ̓�����w�т܂����B�����āA��˃R�[�`����u�ǂ���̊w�N���A���s�����ꂸ�A�Ō�܂Ń`�������W���悤�Ƃ���p���������Ă����ł��ˁB�v�Ƃ��������t�����������܂����B
�@1�N���́u�����ȓ������ł��Ċy���������I�܂���˃R�[�`�ɗ��Ăق����ȁB�v�A2�N���́u�y�����������Ǔ�������B�����Ɨ��K����B�v�Ƙb���Ă��܂����B���ꂩ�犦���Ȃ��Ă���������̂����Ȃ���A�l�X�ȓ����E�^���Ƀ`�������W���Ă����ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N12��16���i���j |
| 5�N���A���сE���X�`���Ƀ`�������W�I |
 |
 |
|
�@5�N���́A��T10���i�j�ɉƒ�ȁu�H�ׂČ��C�I���тƂ݂��`�I�v�̊w�K�ŁA�����ǂɋC��t���Ȃ��璲�����K�Ƀ`�������W���܂����B����������́A����g���Đ��������тƁA�o�`����Ƃ������X�`�ł��B
�@�u�ϊ����̓����Ƃ��āA���ɐZ���Ă�����B�v�u���������A�卪�ׂ���������������Ȃ��H�v�c�@�O���[�v���ƂɁA���k���Ȃ��狦�͂������āA�ޗ�������Ă�u�����肵�Ă����܂����B�����āA�ǂ̃O���[�v�����������������o���オ��A�݂�ȂŎc�����H�ׂ܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�ϊ�������o�`���Ƃ邱�Ƃ��ł��ėǂ������B�Ƃł�����Ă݂����B�v�u�菇�ʂ�ɂł����B���������������ł����B�v�ƒ������K�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B���̌o�����������āA�Ƃł��H��������`�������Ă����Ăق����Ȃ��Ǝv���܂��B�@
|
|
|
| 2020�N12��15���i�j |
| ��������~�i�F�ɂȂ������x�� |
 |
 |
|
�@�������~��n�߂���ŁA�w�Z�̎������������~�i�F�ɂȂ�܂����B���̂Ƃ���A�O���E���h�̐ϐ��30�������x�ł��B
�@����Ȓ��A��������������x�݂̎��ԂɌ��C�ɊO�ɔ�яo���Ă����q�ǂ����������������ł��B�����āA�F�B�Ɛፇ���������A��ʂ�]�����đ傫��������ƁA����������Ƃ������ɗV��ł��܂����B����ς�A�ፑ�̎q�ǂ������ł��ˁB
�@�q�ǂ������́A���ׂ��Ђ��Ȃ��悤�ɕ����𐮂�����A�傫�ȉ�����̉��ŗV�Ȃ��悤�ɋC��t���ėV��ł��܂��B�i����ł��A�����r�V���r�V���ɂȂ��Ă��܂����c;�D�M)�j�ƂɋA���Ă�����A���H�◬��a�̎���ȂǁA���S�ɋC��t���ĉ߂����ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N12��14���i���j |
| 2�N���A�����ȂŃu�[�������Â���I |
 |
 |
|
�@2�N���́A��T���琶���ȁu����Ă����ڂ��v�̊w�K�Ńu�[�������Â���ȂǂɎ��g��ł��܂��B�g�̉��ɂ���i�{�[���Ȃǂ̍ޗ����Ƃ��玝���Ă��āA���p���Ă��܂��B
�@�u�搶�A�����̂͂���܂�߂��Ă��Ȃ���B�ǂ���������H�v�u�啪�߂��Ă�����ǁB�v�c�����́A�k�^����Ŏ���̃u�[�����������ۂɔ���Ȃ���A���������H�v������A�`�����ǂ����肵�܂����B����Ă͎����E����Ă͎����Ƃ����������J��Ԃ��āA�u���͂������Ă݂悤�v�Ƃ����ӗ~�����߂Ă����܂��B
�@�q�ǂ������́A�u���������͌������������ȁB�v�u������͂����������ǂ��������B�v�ƋC�t���n�߂܂����B�q�ǂ������̍��̔Y�݂́u�ǂ�������A�����̂Ƃ���Ƀu�[�����������ǂ��Ă��邩�v�ł��B�݂Ȃ���A������܂����H���ЁA�q�ǂ������ɃA�h�o�C�X���I�F�B�Ə�������������A�������蒼���Ď��s���낵���肵�Ȃ���A�������[���ł���悤�Ɏ��g��ł������Ƃł��傤�B�S�[���̊����Ƃ��ĂP�N�������҂���u�����у����h�v��\�肵�Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N12��10���i�j |
| 3�N���A���ٍH��Ɍ��w�ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@3�N���́A����8���i�j�̌ߑO���ɁA�Љ�ȁu�H��œ����l�Ǝd���v�̈�Ƃ��āA�z�㐻�ٕЊL�H��Ɍ��w�ɍs���܂����B�J�̒��ł������A���C�ɕ����čs���Ă��܂����B
�@�H��ł́A�ŏ��ɁA��Ђ̊T���₨����ׂ��Ȃǂ̍����A�ЊL�H��œ��ɋC��t���Ă���_�Ȃǂ�������Ă��������܂����B�����āA��\�̎q�ǂ��Ɏ��ۂ̐�����ʂŎg���Ă��镞���𒅂����Ă��������A���َq������Ă���l�q�������Ă��������܂����B�O�ꂵ���q���Ǘ��̒��ŁA�傫�ȋ@�B���g���Ă�������̂��َq������Ă���l�q�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�H��ɓ���O�ɃG�A�V�����[�ŕ��̂��݂𗎂Ƃ��Ă���B�������B�v�u�@�B����ǂ�ǂ���ׂ����o�Ă���B������������ł���B�v�Ɗ��z��b������A���w��U��Ԃ����肵�Ă��܂����B�F���H�ɂ��I�ꂽ�Z�p���g���āA�H�v���Ȃ��炨�q����Ɋ��ł��炦�邨�َq�������Ă���l�q���A�w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B
|
|
|
| 2020�N12��9���i���j |
| 1�N���A�����_�Ԓd�ɋ����A�� |
 |
 |
|
�@1�N���́A���8���i�j��1���ɁA�O�V�������_�ɂ���Ԓd�ɋ�����A���Ă��܂����B�J�̒��ł������A�ЊL�̉Ԃ̉�̎菕���̂������Ŗ����A���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�u�����ɂ͏�Ɖ��A�O�ƌ�낪����܂��B�A����Ƃ��́A�Ƃ��Ă��������ɂ��܂��傤�v�ƁA�ŏ��ɉԂ̉�̕�����A�����̐���������܂����B�����āA1�l4���A�`���[���b�v�̋�����A���܂����B
�@�w�Z�ɖ߂��Ă������ƁA�q�ǂ������́A�u���ꂢ�ȃ`���[���b�v���炭�̂��y���݂��ȁv�u�����ʂ�ꏊ������A�w�Z�̍s���A��Ɍ����I�v�Ƙb���Ă��܂����B�����������A�����`���[���b�v�̉Ԃ��A���N�̏t�ɂ͂����ƍ炫�ւ邱�Ƃł��傤�B�����āA���������b�ɂȂ��Ă���ЊL���ɁA�����ł����ɗ��Ă�Ƃ����ł��B
|
|
|
| 2020�N12��8���i�j |
| 6�N���A�ނ����\�h���������Ă��������܂��� |
 |
 |
|
�@6�N���́A���7����5���ɁA�w�Z���Ȉ�l����ނ����\�h���������Ă��������܂����B���w���w��O�ɁA���ȉq���ɂ��Ă̂��ڂ����m���ƁA�����̎�����낤�Ƃ���ӗ~�������ė~�����Ƃ����肢������{���܂����B
�@�u�t�b�f�������Ă��鎕�݂������̏ꍇ�́A�����䂷���̂�3����x�ł����ł��B�v�u������������Ɉ�������Ǝ������ɂȂ��āA�����������ł͎���Ȃ��Ȃ�̂ŁA���u���V�̎��ւ̓��ĕ��ɋC��t���Ė����Ă��������B�v�c�@�f����A���̖͌^�Ȃǂ��g���āA������₷�������Ă��������܂����B
�@�q�ǂ������́A����⊴�ӂ̌��t�ȂǂŁA�u�ނ����ɂȂ�v���������������Ǝv��������ǁA�X�g���X���v���ɂȂ邱�Ƃ����߂Ēm�����B�Ɖu�͂��ቺ���邩��Ƃ������R���m�邱�Ƃ��ł��Ă悩�����B�v�u�ނ����⎕���a�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���������Ă�������������Ŏ��������������B�v�Ƙb���Ă��܂����B�w�Z���Ȉ�l�́A�e�q2��ɂ킽���Ăނ����\�h���������Ă��������Ă��܂��B�ł��܂�����A��������肢�������Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N12��7���i���j |
| 6�N���A���p�h�~��������u���܂��� |
 |
 |
|
�@6�N���́A��T12/4�i���j�ɁA����J���C�I���Y�N���u�̕��X���u�t�ɂ��������āA���p�h�~��������u���܂����B���Ő��̂�����̂ɂ́A�^�o�R����E�喃���̖ȂǁA�l�X�Ȃ��̂����邱�Ƃ��w�т܂����B
�@�u�́A���g�����тɔ]��j��B�v�u����߂Ă��A�]�͌��ɂ͖߂�Ȃ��B�v�c�ȂǁA���Ɉ�@�̊댯���J�ɋ����Ă��������܂����B�܂��A�����ɂƂ��Đg�߂Ȑl����U��ꂽ���́A�h���b�Z�[�W���g�����f����������Ă��������܂����B
�@���ƌ�ɂ́A�������Ă������������̕W�{���A�q�ǂ������́A�^���Ɍ��Ă��܂����B�u���������������Ăт����肵���B�v�u�����A�������Ă���ɒf�肽���B�v�Ɗ��z�������܂����B�u�B�_���I�[�b�^�C�I�v���A���U�Y��Ȃ��ł��ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N12��4���i���j |
| ����A�S�Z��������܂��� |
 |
 |
|
�@����̒������̎��ԂɁA�Վ��̑S�Z������s���܂����B�������̕\����A�����̐��ʂ̔��\�A�����ߓ��ɂ������Z���u�b��R���i�E�C���X�W�Ɛ����W�̎w�����A��������̓`���������e������������ł��B
�@�Z���u�b�ł́A���嗬�s���Ă���u�S�ł̐n�v���ނɁA�u���ꂼ��̐l�ɂ́A���̐l�̌����E�l�����E�������E���j������B�v�u����̐S�Ɋ�肻�����Ƃ��邱�Ƃ͓�����ǁA��ɂ��Ă������B�v�Ƃ����b�����܂����B
�@�܂��A�{�싳�@����́A���̓��{�̃R���i�E�C���X��������u������x�A�\�h���O�ꂵ�Ă������B�v�Ƃ����w��������܂����B�u�������Ԃ̊ԂɃE�C���X�������Ȃ��āA�l�ɂ����\�������邩��A��������}�X�N���������肵�悤�B�v�Ɗm�F�������܂���
�@�q�ǂ������ɂƂ��Ĉ��S�E���S�Ȋw�Z�ɂȂ�悤�A���ꂩ������g��ł��������Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N12��3���i�j |
| ���ȃN���u�A�t�̒��f���g���Ď����I |
 |
 |
|
�@���12��2���̃N���u�̎��ԁA�Ȋw�E�����N���u�ł́A�s���ȃZ���^�[�����及���̕������������āA�t�̒��f���g�������낢��Ȏ����Ɏ��g�݂܂����B�t�̒��f�̉��x�́A��[200���ł��B
�@���ȃN���u�̎q�ǂ������́A�t�̒��f�̒��ɓ��ꂽ�o�i�i���u���Â��v�̂悤�Ɍł��Ȃ�����A�Ԃт炪���X�ɂȂ����肷��l�q�������Ă��炢�܂����B���̌�A���������ŕ��D���t�̒��f�̒��ɓ����Ƃǂ��Ȃ邩����������A�}�V���}�����t�̒��f�̒��ɓ��ꂽ��ǂ�ȐH���ɂȂ邩�H�ׂĂ݂�������܂����B
�@�q�ǂ������́A�����̌�u�����Ȏ������ł��Ċy���������B�v�u�Ȃ�ł����Ȃ��?!�ƕs�v�c�Ȃ��Ƃ��肾�����B�v�ƁA���z��b���Ă��܂����B�s�v�c�ȉȊw�̐��E�ɐG��A�����������Ƃ��ł��āA�ǂ������Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N12��2���i���j |
| ���݂̃L�b�Y�w�у����h�B�A���w�N�̕� |
 |
 |
|
�@�O���Ɉ��������A�����́A�w�у����h�Ō�̍��w�N���̗l�q�����m�点���܂��B
�@�T�N���́A�`���̉��ڂł���S�u��[�،��v�E���t�u�������E�����̂ڂ�v�������܂����B���B���x���g���ҋȂ����V���M���̋Ȃ��A�a�y��Ɨm�y��ʼn��t���܂����B�܂��A�u��[�،��v�́A�`���|�\�ۑ���̕��X�ɂ��w�����Ă��炢�A�u�Ƃ��Ă����܂��Ȃ��Ă���B�v�Ƃ��n�t����������Ă̔��\�ł����B�����ƁA�ЊL�܂�̕��i���ڂɕ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�U�N���́A���u�ЊL�O�ڋʕ���`����24�N�ЊL�l�̒���`�v�\���܂����B�ЊL���ŏ��߂ĎO�ڋʂ�ł��グ�����́A�ЊL�̎�҂����̎p�������܂����B���������Ȃ�������͂��āA�O�ڋʂ̑ł��グ�ɐ���������l�����̔M���v����`���܂����B
�@�T�N���́u�R�U�l�̉����ЂƂɂ��邱�Ƃ��ł����B�ЊL�܂�̗l�q���v�������ׂĂ��炦���Ǝv���B�v�A6�N���́u�O�ڋʂ𐬌������悤�Ɠw�͂��Ă��������̐l�����̋C�����ɂȂ��ĉ����邱�Ƃ��ł����B�w�N�݂�Ȃ̗͂Ō������肠���邱�Ƃ��ł��Ċy���������B�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�w�у����h�����{���A�ی�҂̊F�l�Ɍ��Ă��炦�āA�{���ɗǂ������Ǝv���Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N12��1���i�j |
| ���݂̃L�b�Y�w�у����h�A�A���w�N�̕� |
 |
 |
|
�@�O�Ɉ��������A�����́A�w�у����h�̒��w�N���̗l�q�����m�点���܂��B
�@�R�N���́A�u�����₫�̂v�`�������v�\���܂����B���߂Ď��g���R�[�_�[�Łu�u���b�N�z�[���v�����t���܂����B�݂�ȂŁA�����e���|�̋Ȃɍ��킹�ď��ɉ��t���邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�����u�v�`�ɂȂ��ėx�낤�v�ł́A��b��t���Ȃ��炫�ꂢ�Ȑ��ʼn̂��܂����B
�@�S�N���́A���u�Q���̂P���l���p�[�g�Q�v�\���܂����B�P�O�N��̕ЊL�܂�Q���ڂɁA�ȂȂ���w�N�̖ʁX���A�e�����Łu���l��v�����z���Ă����ł��낤�l�q���݂�Ȃʼn����܂����B�Ō�ɂ́A�傫�ȉԉ�ł��グ�A�_���X�u�쒆�\�[�����v���݂�Ȃ̐S����ɂ��ėx��܂����B
�@�R�N���́u���y���D���ɂȂ����v�u���K��ςݏd�˂�A������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƕ��������v�A�S�N���́u�݂�ȂŐS���ЂƂɋ��͂ł��Ă悩�����v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�݂�ȂŏW�����Ď��g�݁A�N���X�̑傫�Ȑ����������܂����B
|
|
|
| 2020�N11��28���i�y�j |
| ���݂̃L�b�Y�w�у����h�@�A��w�N�̕� |
 |
 |
|
�@�{���ߑO���ɁA�w�K���\��ł���u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v�����{���܂����B���N�x�́A�e���ƒ�2���܂ł̎Q�ς����肢���A��w�N���E���w�N���E���w�N���ɕ����Ď��{���܂����B��w�N���̗l�q���A�����͂��m�点���܂��B
�@1�N���́A�u�Ђт��I�����y���v�\���܂����B�q�ǂ������́A���w���Ă���̎v���o���A���ŕ\���Ȃ��牉�t�E�����ɂȂ��܂����B���Ճn�[���j�J�Łu�x��ۂ�ۂ����v�����t������A��b�����Ȃ���u���E���̎q�ǂ��������v���̂����肵�܂����B��l��l���A�ƂĂ��傫�Ȑ��Ŕ��\�ł���悤�ɂȂ�܂����B
�@�܂��A2�N���́A�����ȂŒ��ׂĂ������Ƃ��A���u�ЊL�͐E�l�̒��v�ɂ܂Ƃ߂Ĕ��\���܂����B�����e�n�̐E�l����̂Ƃ���ɎU������u�v���A�����悤���������q���g�����ƂɒT���ɏo�����A�Ō�ɂ́u�E�l�̒��A�ЊL�v�̕��낤�Ƃ����y�������ł����B
�@���\���I�������A1�N���́u�ْ��������ǁA�ԈႦ���ɂł��܂����B���N���撣�肽���ł��B�v�A2�N���́u�傫�����o�����ƂƓ�����傫�����邱�Ƃ�B���ł��܂����B�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�݂�Ȃŋ��͂��A�B�����𖡂키���Ƃ��ł��܂����B
|
|
|
| 2020�N11��27���i���j |
| 3�N���A�����̊w�K��i�߂Ă��܂� |
 |
 |
|
�@3�N���́A���A�Z���Łu�����v�̊w�K��i�߂Ă��܂��B1�ɖ����Ȃ��͂����̐����A�����ŕ\���w�K�ł��B�����́A�����𐔒����̏�ɕ\������A�召�W�ׂ��肵�܂����B
�@�u�P��0.1��10�ŁA����0.8��0.1��8������10�{8�ŁA1.8��0.1��18������ˁc�B�v�q�ǂ������́A���O���[�v�̒��ŁA�����̍l�������������A�����������肵�܂����B���낢��ȋ��ȂŃO���[�v�̘b�����������Ă���̂ŁA�q�ǂ��������b�����������ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
�@�q�ǂ������́A�����̊w�K��ʂ��āA�u���������g���ƁA�����̑傫����������₷���B�O�D�P�����������邩��������₷���B�v�ƁA���������̌��t�ł܂Ƃ߂����܂����B�����̎d�g�݂̗������A�啪�i��ł����悤�ł��B
|
|
|
| 2020�N11��26���i�j |
| �u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v�̃��n�[�T�����s���܂��� |
 |
 |
|
�@������2�`4���ɁA�u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v�̃��n�[�T�����A�S�Z�ōs���܂����B���N�x�́A�{�ԓ����ɑ��̊w�N�̔��\�͌������邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA�����������Ӗ��ł́u�{�ԁv�ł�����܂��B
�@��������̐l�̑O�Ńh�L�h�L���钆�ŁA�u�ЊL�E����J�E�����Ď��������̂悳���`���v�������Ă݂邱�ƁB���̊w�N�⑼�̐l�̉��Z��ԓx�E�p����A�u�悳�v�����������Ċw�Ԃ��ƁB���̓���߂��ĂɁA���n�[�T���Ɏ��g�݂܂����B�l�^�o���ɂȂ�̂ŁA�����̂Ƃ���͏ڂ��������܂���c�B�ł��A�ǂ̊w�N���Ƃ��Ă��f���炵�������ł��B
�@�y�j���̖{�Ԃł́A���̊w�N�̂悳��������A����ɉ��Z���ɖ����������Ĕ��\���Ă���邱�Ƃł��傤�B�����͊����Ȃ�V�C�\����o�Ă��܂��B�펞���C�����܂��̂ŁA�\�������������ł��z�����������B
|
|
|
| 2020�N11��25���i���j |
| 2�N���A�E�l�T���̂܂Ƃ߂�n��L���ɂ͂�܂��� |
 |
 |
|
�@2�N���́A�����Ȃ̊w�K�Łu�ЊL���̐E�l�ɉ�ɍs�����v�̊w�K�ŗl�X�ȂƂ���Ɍ��w�ɍs���A���b�����Ă��炢�܂����B�����āA����́A���̂���̎莆�����ꂼ��̐E�l����ɓ͂��ɍs���Ă��܂����B
�@�q�ǂ������́A�����Ă���������ƁE�����������w���Ƃ��m���ɂ܂Ƃ߁A�̈�ق̓n��L���ɂ͂�܂����B��m������́A�C���^�r���[���Ă����������Ώ㌚��E���D���E�����E�����E�r�c���́u�Z�Z����v�̐�������v�����A�`����Ă��܂��B�����āA�w�у����h�ł��A���̕��X�Ƃ̃C���^�r���[��ӂꂠ���̗l�q�����Ŕ��\���܂��B
�@�܂��A��^����̓����̕ǂɂ́A�s�����̈�قɂ��W�����Ă����������A������i�u�킽�������̒��ЊL�̉ԉv���f������Ă��܂��B�u�w�у����h�v�̎��ɁA���킹�Ă������������B
|
|
|
| 2020�N11��24���i�j |
| 6�N���A1�N���̎Z���ɂ������ɂ����Ă��܂��� |
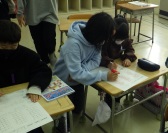 |
 |
|
�@������4���ɁA6�N���̏��q�́A1�N���̋����ɎZ���̈����Z�������ɍs���Ă��܂����B�Ƃ����̂��A���悢��u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v���߂Â��Ă�������ł��B
�@���́A��T�̋��j���ɁA6�N���́u���g�v����ʑ���Ɏg���������Ă��܂����B���̒��Ŏg���哹��Ƃ��Ăł��B1�N���̒S�C�́A�ʑ���̉���̑g���ɂ����ʂ��Ă���̂ŁA6�N���̒j�q�Ƒg�������Ă������Ɂi����ɁH�j�A���q��1�N���̎Z���̐搶���Ƃ��ċ����ɍs���Ă����̂ł��B
�@6�N���̎q�ǂ������́A�u���܂�ď��߂Ė{���̉����g�ݗ��ĂĊ����I�v�A1�N���̎q�ǂ������́A�u�܂��U�N���ƈꏏ�ɕ��������B�v�Ƙb���Ă��܂����B��N�ƈꖡ������u�w�у����h�v�ɂȂ肻���ŁA�y���݂ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N11��20���i���j |
| �{�����e�B�A�̕��X�ɂ��ǂݕ�������}������ |
 |
 |
|
�@�����̒��w�K�̎��ԁA�{�����e�B�A�̕�����A3�E4�N���͓ǂݕ������i�N�ǁj�����Ă��������܂����B11�����犈�����ĊJ����A����2��ڂł��B
�@�����́A�u��܂�̂ɂ����v�Ȃǂ̖{��ǂ�ł��������܂����B���ꂼ��̎q�ǂ������́A�S�̂��������N�ǂŕ���ɓ��荞��ł��܂����B4�N���ł́u�X�̒��ɉB��Ă��铮�����������āA�y���������I�v�Ƙb���Ă��܂����B�Ǐ��{�Ԃ̒��ŁA��ς����@��������Ƃ��ł��܂����B
�@�܂��A��T�̖ؗj���ɂ́A�}���{�����e�B�A�̕��X�����Z����A�u�{�̕a�@�v���ĊJ���Ă��������܂����B�R���i�Ђ̒��ł����A�\�������Ǒ�����Ȃ���A��ȕ��X�Ƃ́u�������v��ݒ肵�Ă��������Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N11��19���i�j |
| �ӏH�̏H����̒��x�݁I |
 |
 |
|
�@�����̒��x�݁A���N�Ōォ������Ȃ����V�̂��ƁA��������̎q�ǂ��������O�ɏo�Ă��܂����B�������������̒��ŁA�O���E���h��u�Ȃ��悵�̍�v�E����ȂǁA���ꂼ��̏ꏊ�Ō��C�悭�V��ł��܂����B
�@�O���E���h�ł́A�j�����悭�T�b�J�[���y���ގq�A�������ɂȂ��ċS������������q�A�u�����R�Ȃǂ̗V��ŗV�Ԏq�c�ȂǁA�w�N���Ƃɒj���ꏏ�ɂȂ��ėV�Ԏp�����������܂����B�����Ȃ��Ĕ����ɂȂ��Ă���q�ǂ��������`���z���B
�@���~�W��C�`���E�̖��A��������ɐF�t���Ă��܂����B�w�Z�̒�����́A���݂̃L�b�Y�w�у����h�Ɍ����Ċy�����K���鉹�F���������Ă��܂����B�q�ǂ������̏Ί炪����������Ă����A�f�G�Ȓ��x�݂ł����B�@
|
|
|
| 2020�N11��18���i���j |
| �Ǐ��{�ԁA�}���ψ��̓ǂݕ������I |
 |
 |
|
�@���Z�ł́A11��9���i���j����20���i���j�܂ŁA�Ǐ��{�ԂɎ��g��ł��܂��B�}���ψ�����S�ƂȂ�A�u�{��ǂ�ł���������炨���I�v��u�ǂݕ������I�v�u�搶������̂������ߖ{�̏Љ�v�Ȃǂ̊������Ȃ���A�{�ɐe���݂�������Ǐ�������q�ǂ������𑝂₻���Ƃ��Ă��܂��B
�@�����̒������̎��Ԃɂ́A2��ڂ́u�}���ψ��ɂ��ǂݕ������v�@���s���܂����B5�E6�N�̐}���ψ����A���w�K�̎��Ԃ�1�`3�N���̋����ŁA�G�{��ǂ݂܂����B�@�w���ɂނ����x�@�w�ւ�}�W�b�N�x�ȂǁA���������̂��C�ɓ���̖{���A�C���������߂ēǂ݂܂����B
�@���w�N�̎q�ǂ������́A�u�����œǂ��Ƃ��邯�ǁA�ǂ�ł��炤�Ƃ��ꂵ���B�v�Ɠǂ�ł���������z��b���Ă��܂����B�ی�҂̊F�l�ɂ����肢���Ă���u�Ɠǁi�����ǂ��j�v�̎�g������܂��̂ŁA�H�̖钷�Ɏq�ǂ������ƈꏏ�ɓǂ�ł���������Ƃ��肪�����ł��B��낵�����肢�������܂��B
|
|
|
| 2020�N11��17���i�j |
| 5�N���A�ߑ���p�ق̏o�O���ƂɎQ�����܂��� |
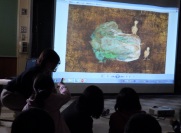 |
 |
|
�@������2���ɁA5�N���́A�����ߑ���p�ق̊w�|���̕�����o�O���Ƃ����Ă��������܂����B��N�ł��ƁA���p�ق�K�₵�Ċӏ܋��������Ă��������܂����A���N�x�͗��Ă��������Ă��܂��B
�@�u�����Ă���Ђ悱���A2�H����B�v�u��e�̒�����ʂ̊O�ɂ����Ȃ����ȁB�v�c��l��l���A���e���ꂽ�G�悩�猩�������̂\���āA�ӌ����𗬂�����K�����܂����B���̌�A�O���[�v���Ƃɂ��ꂼ��̊G�悩�犴�������Ƃ��𗬂�����A���̃O���[�v�ɓ`�����肵�܂����B
�@�q�ǂ������́A���Ƃ�ʂ��āu�F�����ƍ�i������ƁA�����ɂ͂Ȃ����������ɋC�t�����Ƃ��ł����B�v�u��̍�i���炢���Ȃ��Ƃ��l���邱�Ƃ��ł����B�v�Ƃ��������z�������܂����B��l��l���A���ꂼ��̌����E�����������邱�Ƃ��A�G���ʂ��Ċ����邱�Ƃ��ł��܂����B���U�A���p�E�|�p���ɂ����������Ă�Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N11��16���i���j |
| 4�N���A���y�̌������Ƃ�����܂��� |
 |
 |
|
�@��T��13���i���j��5���ɁA4�N���̃N���X�ʼn��y�̌������Ƃ�����܂����B�u�̂��悤�ɐ������v�Ƃ����w�K�ŁA������́u�F�����Ȃv�����R�[�_�[�łǂ̂悤�ɉ��t���邩���l���Ȃ�����K���Ă��܂��B���̋Ȃ́A�ۓJ���ł����t���܂��B
�@�u�w��������A��������x�̌�ɁA���ꂼ��u���X������Ǝv���܂��B�x���̋L�����Ȃ��Ȃ�Ȃ��悤�ɁB�v�u�w��������A��������x�́A�����łЂƂ����܂�Ȃ̂ő��p�����Ȃ����������Ǝv���܂��B�v�c�q�ǂ������́A���p������ꏊ���A���ۂɉ��x�����t������A�̎����l�����肵�Ĕ��\���Ă��܂����B
�@�q�ǂ������́A���ƌ�u�O�����ɐ�����悤�ɂȂ����B�v�u���ۂɐ����Ċm���߂Ȃ���l�����B�v�Ɗ�������A�U��Ԃ����肵�Ă��܂����B������������ƁA1���̈��p���Ɍ����āA6�N�����A4�N����5�N���ɌۓJ���������ʂ��o�Ă��܂��B���̊w�K�́A�ЊL���̓`���������p���厖�Ȋ����ɂ��Ȃ����Ă����܂��B
|
|
|
| 2020�N11��12���i�j |
| �����ߌ������[���X�N�[���W����s���܂��� |
 |
 |
|
�@�����̒������̂��݂̖ؒ���ŁA�����ψ���̎�Âł����ߌ������[���X�N�[���W����s���܂����B
�@������́u�Ƃ������Ȃv���̂�����A�c����O���[�v��3��̃N�C�Y���l���܂����B�u�ǂ��������������߂��Ƃ����邩�H�v�̖��ł́A���ꂼ��̃O���[�v�ł��낢��ȓ������o����܂����B���肪�����������A�\�́E����Ȃ��Ƃ����ꂽ���A�݂�Ȃň�l���U�����Ă��鎞�A�����Ƃ����肩�������肵�����A�c�B���݂̖����W���[���A�e�O���[�v���[�_�[�ɕ����ĉ��܂����B�����́A���肪�����߂��Ǝv�����炢���߂Ȃ̂ŁA�������������S���������ł��B
�@�Ō�l�ɁA�Z�����璆�z�n���ł��������L�����Ă��Ă���R���i�����ǂ̘b������܂����B�u���ꂪ������Ƃ��Ă��A����������������肷��̂ł͂Ȃ��A�����������������āA�݂�ȂŊ�@�����z���Ă����܂��傤�B�v�Ƙb���܂����B�l�X�Ȃ����߂��������Ȃ��悤�A���ꂩ������g��ł����܂��B
|
|
|
| 2020�N11��11���i���j |
| 3�N���A����̌������Ƃ�����܂��� |
 |
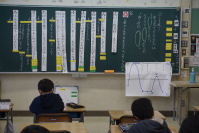 |
|
�@���11��10���i�j��5���ɁA3�N���́A���J���Ƃ��s���܂����B�u���`���`�̖v�Ƃ�������̎�l���u�����v�̋C�������A�ǂݎ��w�K���s���܂����B�O���[�v��S�̂Ō������āA�����̍l����[�߂܂����B
�@�u�����猌���o�Ă����̂ɁA�Ȃ��Ȃ���������ʂ��A��ԓ������E�C���o�����Ƃ��낾�Ǝv���B�ɂ����A�������A�|���̂ɁA�E�C���o���đ���������B�v�u���́A�\�˂�̂łԂ�����āA����o�����̂Ƃ���ł��B���R�́A5�Ȃ̂ɁA���l�ŁA�ӂ��Ƃ̈�җl���Ăтɍs������ł��B�v�c�q�ǂ������́A�����܂̊�@�ɁA�E�C��U��i���āA��̐�̎R�����삯����Ă����p���A�ǂݎ��܂����B
�@�q�ǂ������́A�w�K�̌�u�b�������ł́A�F�B�Ɠ����Ƃ����I����ǁA���R������āA�����������R������ȂƎv���܂����B�v�@�u�l�̈ӌ����ƁA�w����͂Ȃ��ȁx�Ǝv���Ă��Ă��݂�ȗ��R���w�m���ɁI�x�Ǝv���āA�l�̈ӌ����̂͂��������ȂƎv���܂����B�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B
�@�����̏��q�ɉ����āA�o��l���̋C�����̕ω�����ɋC�t�����Ƃ��ł��܂����B
|
|
|
| 2020�N11��10���i�j |
| 5�E6�N���A�w�Z�ی��ψ���̍u���Ŋw�K���܂��� |
 |
 |
|
�@���9���i���j�ɁA5�E6�N���́A�ЊL��1�N���ƈꏏ�ɁA�ЊL���E�ЊL���w�Z�ی��ψ���u����ɎQ�����܂����B���̍u����́A���E���w�Z��PTA�����Ƃ��A�g���Ď��{����܂����B�u�t�́A��z�����w�̓��C�y�����ł��������铇�ÍO���l�ł��B
�@�u�Q�[���ˑ��́A�]�̖J���V�X�e�������āA�Q�[���̂��Ƃ��C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ���Ԃł��B�v�u������́A����̗�V��}�i�[�̉����ɂ���̂ł��B�v�c�@�d�q���f�B�A�̊댯����Q�[���ˑ��̂��킳�Ȃǂɂ��āA�q�ǂ������ɕ�����₷�������Ă��������܂����B
�@�u����A�q�ǂ������́A��������̎�������āA���Ð搶�ɒ��J�ɓ����Ă��������܂����B�I����A���Ð搶���q�ǂ������̐ϋɐ��ɂт����肵�Ă�������Ⴂ�܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�Q�[���ˑ��ǂɂȂ肽���Ȃ��v�u�Ύ��ɂȂ��č����Ă���X�|�[�c�I�肪���邱�Ƃ����߂Ēm�����v�Ƃ�������̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�Q�������ی�҂̊F�l�ɂƂ��Ă��A�L�Ӌ`�ȍu��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N11��6���i���j |
| 5�N���A�Љ�Ȃ̌������Ƃ�����܂��� |
 |
 |
|
�@���5����5���ɁA5�N���̎Љ�ȁu�䂪���̍H�Ɛ��Y�@�`�����Ԑ��Y�Ǝ������̕�炵�v�̎��ƌ��J������܂����B������w�ɍs���Ă���NS�A�h�o���e�b�N�ōs���Ă���l�X�ȍH�v�ɂ��čl���܂����B
�@�u��ƍH���̂قƂ�ǂ̏�ʂŁA�@�B��{�b�g����������g���Ă���̂ɁA�ǂ����đg���ł͐l����Ƃ��Ă���̂��낤�B�v�Ƃ����^����A�q�ǂ������͂����܂����B�����ŁA�e���̗\�z���𗬂�����A��ƈ��̕����g����Ƃ����Ă�����ۂ̉f�������܂����B
�@���ۂɍs���Ă���s�ׂ���A�q�ǂ������́A�����̗\�z���ēx�������܂����B�����āA���ꂼ��̍l������������o�������āA�u�l�́A�@�B�ɂ͂ł��Ȃ��g���ƌ������ɍs���Ă��邩��ł͂Ȃ����B�v�ƁA�l����[�߂܂����B
�@���ꂩ��NS�A�h�o���e�b�N����Ɏ莆���o���āA���������̗\�z���m���߂�\��ł��B
|
|
|
| 2020�N11��5���i�j |
| 6�N���A�����̕ЊL�܂�ւ̒��܂Ƃ߂Ă��܂� |
 |
 |
|
�@6�N���́A����u���̍K���_�v�̊w�K�ŁA�����̕ЊL�����ǂ������ė~�������A�܂���ێ����Ă������߂ɂǂ�Ȃ��Ƃ��K�v���A���l���Ă��܂��B����̎��ƎQ�ςł��A�ی�҂̊F�l���炱�̎��Ƃ����Ă�����������A�Q�����Ă�������肵�܂����B
�@�����̈ӌ��Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ȃ���A�q�ǂ������́A�ʑ���E�������E���g�E���l�c�ȂǁA6�̃O���[�v�ɕ�����A���ꂼ��̗ǂ����������̎p��͍����Ă��܂��B�����āA�܂Ƃ߂����������̍l�����v���[��������K���n�߂܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�l�̂Ȃ���������Ă����Ղ�̂悳�𑽂��̐l�ɒm���Ă��炢�����B�v�u���N���~�ɂȂ������炱���ЊL�Ղ����肽���C�����ɂȂ����B�v�Ƃ������v���ŁA�w�K�����Ă��܂��B�q�ǂ������̃v���[�����F����ɓ`������@���A�l�����ł��B
|
|
|
| 2020�N11��4���i���j |
| 3�N���A�S���̓����ׂĂ��܂� |
 |
 |
|
�@3�N���́A10�����{���痝�ȁu����S���̂͂��炫�v�̊w�K�����Ă��܂��B��l��l���A�S���œ��������Ԃ��g���Ď��������Ă��܂��B
�@�̈�قŁA���ꂪ�����܂Ŏ����Ԃ����炷���Ƃ��ł��邩������������A�R���̐L�т�ς��đ��鋗���𑪒肵���肵�܂����B�u�S���L�т�傫�����Ď�𗣂��ƁA�����Ԃ������܂ōs���݂����B�v�u�ł��A���������Ƃ͌���Ȃ���v�c
�@�����̓S���̐L�т�ς��āA�Ԃ����߂�ꂽ�����܂ő��点��ɂ͂ǂ����邩���l���܂����B�O�̎��Ԃ̃f�[�^���Q�l�ɃS���̐L�т�ς��ČJ��Ԃ��J��Ԃ��Ԃ𑖂点�܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�����܂ōs���߂�������L�т̒�����Z����������v�u�����L�т̒����Ȃ̂ɂ��傤�Ǔ��������ɂȂ�Ȃ��v�ƁA�����������Ƃ��܂Ƃ߂���A�U��Ԃ����肵�Ă��܂����B�����āA�S���̐L�т�ς���A�Ԃ̑��鋗�����R���g���[���ł��邱�ƕ�����܂����B
�@���̓S���̐L�т�ς���ȊO�̕��@���l���āA�����Ŋm���߂Ă����܂��B
|
|
|
| 2020�N11��2���i���j |
| ���J�ȍ�ƁA�X�N�[���E�T�|�[�g�E�X�^�b�t |
 |
 |
|
�@9�����瓖�Z�ŁA�����Ă��������Ă���u�X�N�[���E�T�|�[�g�E�X�^�b�t�v�̑q��������Љ�܂��B
�@��Ȏd���́A�Z�ɓ��̏��ŁE�q����Ƃł��B�ċx�݂܂ŕ��ی�E������������Ă������ō�Ƃ��A��l�ł܂����Ă��������Ă��܂��B���ʋ�����g�C�������łȂ��A�e�����ɂ����x�݂Ȃǂɏo�����āA�h�A��CD�v���[���[�E�Z���d�b�c�Ȃǂ����f���ł��Ă�����Ă��܂��B�u�q�ǂ��������G�邾�낤�ꏊ��t�z�����Ȃ���A���łɓw�߂Ă��܂��B�v�ƁA�b���Ă��������܂����B
�@���ɂ��A�v�����g�ނ̈���E�e�K�i����̐��|�E���Z�҂̌����Ȃǂ����Ă��炢�A��Ϗ������Ă��܂��B���ꂩ�����낵�����肢�������܂��B
|
|
|
| 2020�N10��30���i���j |
| 5�E6�N���A���犴�ӍՂɎQ�����܂��� |
 |
 |
|
�@���T���j����28���ɁA5�E6�N���́A�ЊL���̋��犴�ӍՂɎQ�����Ă��܂����B���̊��ӍՂ́A�ЊL���w�Z�̑O�g�ł��钩�z�فE�w�Ǔ��̐搶���̈⓿���Âԉ�ł��B
�@�q�ǂ������́A�ЊL���̖��m�̕��X�ƈꏏ�ɁA���g�R�ɂ���V�R��ł��܂����������A�ЊL���w�Z�̑̈�قɈړ����܂����B�̈�قł́A�ЊL���{�����e�B�A�K�C�h�̏��їl����A8�l�̐搶���̕ЊL�Ƃ̌W���E��������тȂǂɂ��Ă��b�����������邱�Ƃ��ł��܂����B�o�g�n�ɕ����A�q���̕��X�Ƃ�������Ă���l�q���A�������Ă��炢�܂����B
�@5�E6�N���́A���b���āu�ЊL���w�Z�̏���Z���搶���k�Ǔ��̐搶����Ȃ����Ă��Ăт����肵���B�v�u����Q��ɋ߂��܂ŗ��邯��ǁA�V�R��ɂ͏��߂ē����Ă݂��B�Ƃ̐l�ɂ����������B�v�Ƃ��������z�������܂����B�]�ˎ���V�̂ł������ЊL�̒��̗l�q��A���̂���̐l�����̍l�����̈�[��m�邱�Ƃ��ł��A�ǂ������ł��B
|
|
|
| 2020�N10��29���i�j |
| 1�`3�N���A�|�p�ӏ܋����ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@���10��28���̌ߌ�A�P�`3�N���́A������J���w�Z�ōs��ꂽ�|�p�ӏ܋����ɍs���Ă��܂����B�s���̏��w����2���ɕ�����čs���Ă��܂��B
�@����́A�k�C���̌��c�u���̎q�v���A�u�}�[�����ƉJ�P�v�Ƃ����������A�̈�قŌ����Ă���܂����B���Ƃ葱���̑��ŁA�̋ʂ��₶�ɂ���ĕ����߂�ꂽ�J�P���A�}�[�������m�b���i��Ȃ���F�B�Ƌ��͂��ď�����A�Ƃ����X�g�[���[�ł��B6�l�̌��c�����A�\��L���ɓo��l���̐S���\�����Ă���܂����B
�@�q�ǂ������́A�u��������̊y����g���Ă��Ă����������v�u�ƂĂ����傤���ł������납�����v�Ƃ������z�������܂����B�v���̔o�D�̐l�����̉��Z���A�g�߂Ɍ��邱�Ƃ��ł��A�q�ǂ������ɂƂ��Ċy�����o���ɂȂ�܂����B�@�@�@�@
|
|
|
| 2020�N10��28���i���j |
| �T�N���A�N�k�ԑ̌������܂����B |
 |
 |
|
�@���5���ɁA5�N���́A�h�Ћ���ƎЉ�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA����J�s���h���̕�����A�n�k�ւ̑Ώ��̎d���������Ă��������܂����B�V���������L���Ă���N�k�Ԃ��A�����ė��Ă��炢�܂����B
�@�u�k�x�S���炢�܂łȂ�A�e�[�u���̉��ɂ�����邯��ǁA�k�x6���炢�ɂȂ�Ƃ������Ċ�Ȃ��Ȃ邩������܂���B�v�c�@�N�k�Ԃɏ��O�ɁA�n�k�ւ̐S�\����Ώ��̎d���������Ă��炢�܂����B������4�l���A���ۂɋN�k�Ԃŗh���̌������Ă��炢�܂����B�@
�@�q�ǂ������́A�̌��̌�u�h���ƕ������Ă�������v���������ǁA���ۂɗ����炷�����|���B�v�u�傫�ȗh�ꂪ������A���̉��ɉB���悤�ɂ������B�v�Ɗ��z��b���Ă��܂����B��T�̎��ƎQ�ςł́A���z��k�Ђɂ��Ď��ۂ�DVD�̉f���������Ȃ���w�K���܂����B����ɁA�傫�ȗh���̌��ł��āA�ǂ������ł��B
�@�����́A4�N�����̌������Ă��炤�\��ł��B
|
|
|
| 2020�N10��27���i�j |
| 5�N���ASN�A�h�o���e�b�N�ɎЉ�Ȍ��w�ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@5�N���́A���10��26���ɁA�Љ�ȁu�����Ԑ��Y�Ƃ킽�������̕�炵�v�̊w�K�̈�Ƃ��āA�R�J�V�ۂɂ���NS�A�h�o���e�b�N�Ɍ��w�ɍs���Ă��܂����B���̉�Ђ́A�Ő�[�̋Z�p�����āA���{�̃��[�J�[�͂������̂��ƁA���E�̎����Ԃ̃��[�^�[���i�����H��ł��B
�@�܂��A�q�ǂ������́A��Ђ̊T�v�����Ă��鐻�i�̐��������Ă���������ƁA���ۂɍH��̒������w�����Ă��������܂����B�u���݃[���^���v�����{���Ă���H��̒��́A�S�~���������܂Ȃ��E���݂��o���Ȃ����߂̍H�v�����Ȃ���A���i���̐��i����肾���l�X�ȍH�v������Ă��܂����B
�@���w���I�����q�ǂ������́A�u�@�B�����������ċ������B���̑����͂������B�v�v�u�����Ă���l�́A���S�E���S�Ȏ����ԃ��[�^�[����邱�Ƃ�S�����Ă��邱�Ƃ����������B�v�Ƃ��������z�������܂����B����J�s�̍H�ꂪ�킽�������̐����ɂ͌������Ȃ������Ԃ̃��[�^�[�Â�������Ă��邱�ƂɊ������Ă��܂����B����́A����ɓ��{�̍H�ƁE����J�s�̍H�Ƃɂ��āA�[�����ׂĂ����܂��B
|
|
|
| 2020�N10��23���i���j |
| ���N�x�ŏ��̎��ƎQ�ς����{���܂��� |
 |
 |
|
�@�{���ߌ�ɁA���N�x�ŏ��̎��ƎQ�ς����{���邱�Ƃ��ł��܂����B���ŁE�����̓O�����J���Ԃ̕��U�ȂǂɎ��g�݂Ȃ���A���{���܂����B
�@�u�ڂ������̈�Ԑ��������Ǝv���Ƃ���́A�݂�Ȃŋ��͂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������Ƃł��B�v�u���́A�R�~�X�ŁA�����͂Q�V�ɂȂ�܂��B�v�c1�^2���l����Z���E����E�����ȂǂŁA�q�ǂ��������A�����ƗF�B�̍l�����ׂ���A�ʐ^���炽������̏���ǂݎ������A�����̐�����U��Ԃ�����A�ЊL���̖������l�����肷��p������܂����B
�@���ꂼ��̊w�N�ŁA��������̐����̎p�����Ă����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������̕ی�҂̊F���炲���Z���������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B����Ƃ��A��낵�����肢�������܂��B
|
|
|
| 2020�N10��22���i�j |
| 2�N���A2��ڂ̐E�l�C���^�r���[�I |
 |
 |
|
�@2�N���́A�����̌ߑO����2��ڂ̐E�l�C���^�r���[�ɏo�����܂����B����́A�u�r�c���v�Ɓu���D���v�̃O���[�v���A���ז����܂����B
�@�r�c���O���[�v�̎q�ǂ������́A���X�ō���Ă��邢�낢��Ȃ��َq�̎�ނ������Ă��炢�܂����B��������̂��َq�̏܂��Ƃ������Ƃ�A���q����̈ӌ���������Ȃ���V���i���J�����Ă��邱�Ƃ������Ă��炢�܂����B
�@�܂��A���D���O���[�v�̎q�ǂ������́A�u���̂��Ƃ�z���Ȃ���A���������ƌ����Ă��炦����̂���낤�Ƃ��Ă���B�Z�����Ȃ��̂���ςȂ��Ƃ��B�v�ƁA�U�߂��狳���Ă��炢�܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�q�ǂ������́A�w�Z�ɋA���Ă��āu�ʂ˂�����Ă��ڂ����݂Ȃ��Ȃ�ĕs�v�c���ˁB�v�@�u�Z�����������X�ɂƂ��Ă͂������ƂȂˁB�v�Ƃ��������z�������܂����B���q����ɍ��킹�Ă����ƍH�v�𑱂��Ă��邱�ƂɁA�������q�ǂ������ł����B��ς��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N10��21���i���j |
| �����搶�A���C���܂��� |
 |
 |
|
�@�{���A�p�ꋳ�琄�i�ψ��̐����搶���A���Z�ɒ��C���܂����B���A�Վ��S�Z����Œ��C�����s������A�e�w�N�̎��Ƃɂ������Ă��炢�܂����B
�@���C���ł́A�Z���̏Љ�₲�{�l�̎��ȏЉ�̌�A2�l�̑�\�������A�p��Ɩ|��Ŋ��}�̌��t���q�ׂ܂����B����搶����ϊ��ł��������܂����B5�N���̊O����̎��Ƃł́A����搶�p��r���S�N�C�Y�ō��܂ł̊w�K�̕��K�����Ȃ���A�y��������オ��܂����B
�@����搶�́A����J�s�̏o�g�ł����A���w�����2��̒Z�����w�����A�A�����J�̑�w�𑲋Ƃ���Ă��܂��B���́A����J�s�ŗ��w���x����|���ƂȂǂɂ����g��ł��������邻���ł��B�q�ǂ������ɂ��A���낢��Ȃ��Ƃ������Ă������邱�Ƃł��傤�B�y���݂ł��B
|
|
|
| 2020�N10��20���i�j |
| 2�N���A�E�l�C���^�r���[�ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@2�N���́A�{���ߑO�ɁA�����̒��ׂ�E�l�̃O���[�v�ŃC���^�r���[�ɏo�����܂����B�����́A2�O���[�v���u�����v�Ɓu���z���v�ɍs���܂����B
�@��������ł́A�u���q���������Ăق����Ƃ������Ƃ��悭�����Ĕ��̖т���Ă��܂��B���q����Ƙb���Ă����C�����ɂȂ��ċA���Ăق����B�v�Ƃ����b������A���ۂɑ�\�҂��h���C���[�������Ă�������肵�܂����B�܂��A�����ł́A�u�������҂����߂ɁA�Ⴂ��������C�s���Ă����B�v�Ƃ����b�����Ă��������A���ۂɔ�����Ƃ������Ă�������肵�܂����B
�@�q�ǂ������́A���ꂼ��A���ė�����u��������b�������Ă悩�����B�v�u���̖т��Ƃ����Ă�����Ă��ꂢ�ɂȂ����B��肾�ˁB�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�ЊL�ɂ��A���낢��ȋZ�����������l�E�E�l���A�������������邱�Ƃ�������A�ǂ������ł��B���ꂩ�瑼�̐E�l�̕���T������A�w�у����h�Ɍ����Ă܂Ƃ߂��肵�Ă����܂��B
|
|
|
| 2020�N10��16���i���j |
| 1�E2�N���A�o�X�����ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@�{���A1�E2�N���́A���ٓ��������ď���J�s���R�^�������Ƀo�X�����ɏo�����܂����B�H����̂��ƁA1�E2�N��������10�O���[�v������A�l�X�Ȋ����Ƀ`�������W���܂����B
�@�܂��́A�������̃g���b�L���O�R�[�X������܂����B�r���ɂ���W�]��ŏ���J�̌i�F�߂܂����B�ߌォ��́A�H�T���r���S�Q�[�������܂����B�ǂ��g�t�����t�Ȃǂ�T���A�H�ɐe���݂܂����B���ɂ��A���ٓ��₨����O���[�v���ƂɐH�ׂ���A��������̗V��ŗV�肵�܂����B
�@�q�ǂ������́A�A���ė���o�X�̒��ⓞ�����ŁA�u�ǂ�������������Ċy���������I�v�u��������V�ׂĊ����������v�Ƙb���Ă��܂����B����J�s�̍L�����ꂢ�Ȏ{�݂ŁA1���y�����L�Ӌ`�ɉ߂����Ă悩�����ł��B�@�@�@�@�@�@
|
|
|
| 2020�N10��14���i���j |
| 4�N���A�ޏ����̌��I |
 |
 |
|
�@4�N���́A���T���j����12���ɑ����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA�ޏ���ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B���N�x�́A�R���i�Ђ̂��߂ɁA�ޏ���q�ǂ��N���u�̊������c�O�Ȃ��璆�~���Ă��܂��B
�@����Ȓ��A�u���������悭�Ȃ��Ă����̂ŁA�`�����q�������v�Ƃ����M���v���ŁA�ЊL���`���|�\�ۑ����3���̕����A�Q�X�g�e�B�[�`���[�Ƃ��ė��Ă��������܂����B�ޏ���̗��j�������Ă��������A�ȑO�̐�y�����̉��Z��DVD�Ō����Ă�������肵�܂����B�����āA���l���̎q�ǂ������́A���ۂɛޏ����G�点�Ă��炢�܂����B
�@�w�K�̌�A�q�ǂ������́A�u�ޏ��Ɩ�̊W���������Ă悩�����v�u�ǂ�ȕ���������Ă���̂��m�肽���v�Ɗ��z��b������A�U��Ԃ����肵�܂����B������x���Ă��������āA�̂�x��ɍ��߂�ꂽ�Ӗ��ɂ��ċ����Ă��炤�\��ł��B
|
|
|
| 2020�N10��12���i���j |
| 6�N���A�����ЊL���u����ɎQ�� |
 |
 |
|
�@��T���j��10��9���ɁA�ЊL���w�Z�̈�قŁA�����ЊL���Â̋���u����J�Â���܂����B���N�̓R���i�ЂƂ������ƂŁA�����ЊL���̖{�c�l���Z���܂����̓����l�́A���z���ɂȂ�܂���ł������A6�N���͋���u����ɎQ�����Ă��܂����B
�@�u����ł́A��39�Ƃ��ĐS��̋��l���A�u�^���̉Ȋw�v�Ƃ�������ōu�����Ă��������܂����B���w�Ö@�m�Ń��n�r���W�̂��d�������Ă��������鋽�l����A�ȒP�Ȏ��Z�������Ȃ���u�^�����A������w�K��F�m�ǂ̗\�h�ȂǁA�l�X�ȖʂƊW���Ă���v���Ƃ������Ă��������܂����B
�@�q�ǂ������́A�u���ꂩ��͏��������Ă�������悤�B�v�u�����̓X�|�[�c�ɂƂ��Ă�����Ƃ킩�����B�������Q���悤�Ǝv�����B�v�Ƃ��������z�������܂����B�^���ɂ��Ă����ƈႤ����ł��b���������āA�ƂĂ��L�Ӌ`�ł����B���N�x�́A�u������N�ʂ�ɍs���������̂ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N10��9���i���j |
| �������������Ƒ����ė~�����ł��I |
 |
 |
|
�@���T�̌��j������n�܂����������L�����y�[�����A�����ŏI���ł��B
�@���w���̎q�ǂ��������A���k��̈ψ���Ƃɓ��ւ��ŁA�Z��O�Ȃǂɗ����Ĉ��A���Ă���܂����B�܂��A������肽������̒n��̕����A�q�ǂ������̓o�Z�̗l�q��������Ă��������܂����B�u�����Ƒ傫�Ȑ��ŁA���C�悭�������ł���Ƃ����ł��ˁB�v�ƁA�����Ă������闧���w���̕��X���A��������Ⴂ�܂����B
�@�u�������v�́A�l�Ɛl�Ƃ��Ȃ��R�~���j�P�[�V�����̑厖�Ȋ�Ղł��B�L�����y�[���̊��Ԃ͍����ŏI���܂����A���ꂩ������C�ɑ�������悤�Ɏw�����Ă��������Ǝv���܂��B����Ƃ��A�q�ǂ������̌���蓙�A��낵�����肢�������܂��B
|
|
|
| 2020�N10��8���i�j |
| 5�N���A�A�w�����N�f�f�̂���`�������܂��� |
 |
 |
|
�@���10��7���̌ߌ�A���N�x��1�N���i�N������j�̂��߂̏A�w�����N�f�f���A���Z�ł���܂����B5�N���ȊO�̊w�N�́A���H�㉺�Z���܂������A5�N���͎c���Č��f�̂���`�������܂����B
�@�T�N���́A�N�����ی�҂̕��Ɨ���Ă��s���ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA��t����N������Ǝ���Ȃ��ňē�������A���ꂼ��̌������ɘA��čs���ĕ�������A���Ԃɖ{��ǂ�ŕ��������肵�Ă���܂����B�ƂĂ��A�D�����ڂ��Ă���܂����B�܂��A�ی�҂Ɋw�Z�Љ�������q�ǂ����������܂��B���������ōl�����O���N�C�Y���o���Ȃ���A���������̎�g���Љ�܂����B
�@�q�ǂ������́A�������I������u�ْ��������ǁA�V�P�N���ɊG�{�̓ǂݕ����������邱�Ƃ��ł����B�v�u�V�P�N�����������������B���N���y���݁B�v�Ƙb���Ă��܂����B���N�x�̂U�N���Ƃ��āA���h�Ɋ��Ă���܂����B����̐������y���݂ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N10��7���i���j |
| 3�N���A�����2��ڂ̒T���ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@�����̌ߑO���ɁA3�N���́A�����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA2��ڂ̐���T���ɍs���Ă��܂����B�O���6���ł������A����͏H�̗l�q�����ɍs���܂����B
�@�q�ǂ������́A5�O���[�v�ɕ�����ăQ�X�g�e�B�[�`���[�̕��X�ƈꏏ�ɁA���A������������T���܂����B�A���ł́A�I��A�P�r�Ȃǂ̎��E���̂���݂傤���E�A�U�~��q�K���o�i�̉ԂȂǁA���������܂����B�܂��A�����ł́A�J�i�w�r��N���A�Q�n�E�T���K�j��S�Ȃǂ������邱�Ƃ��ł��܂����B�����ĕ߂܂������������������Ă��܂����B
�@�w�Z�ɋA���Ă���A�q�ǂ������́u�y���������I�v�u���ׂ����́A�����ς��������I�v�ƒT����U��Ԃ��Ă��܂����B�ĂƏH�̗l�q�̈Ⴂ�ɂ��C�Â����Ƃ��ł��āA�ǂ������ł��B��������̃Q�X�g�e�B�[�`���[�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N10��6���i�j |
| 1�N���A�N������Ƃ̌𗬉�����܂��� |
 |
 |
|
�@�����10��5���i���j�ɁA1�N���́A�ЊL�ۈ牀�̔N������Ƃ̌𗬉���s���܂����B���T�̐��j���ɐV1�N���̏A�w�����N�f�f������܂��̂ŁA�N������ɂƂ��ẮA���O���K�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B
�@�u���傤���������́A���ƂȂƂ��ǂ��A���킹�ĂȂ�ɂ�ł��傤�H�c�v1�N���́A�N�����������o�}��������A�}�����Łu�ЊL���w�Z�N�C�Y�v���o������A�����̃y�A�̔N������ɖ{�̓ǂݕ������������肵�܂����B���̌�ɁA�̈�ق�1�N���������A����Ȃ��ŗD�����ē����܂����B
�@1�N���̎q�ǂ������́A�N���������A������A�u�P�N���ɂȂ�����ꏏ�ɗV�т����v�u�N�C�Y�����܂��ł��Ă��ꂵ�������v�Ƙb���Ă��܂����B�𗬉�̏�������ۂ̌𗬂�ʂ��āA2�N���Ɍ������đ傫���������Ă��邱�Ƃ������܂��B
|
|
|
| 2020�N10��5���i���j |
| �������L�����y�[���@���n�܂�܂����I |
 |
 |
|
�@��������A�ۏ����A�g���Ƃ̈�ł���u�������L�����y�[���v���n�܂�܂����B�R���i�ЂŁA1�w���ɗ\�肵�Ă������Ƃ𒆎~���A����1��ڂƂȂ�܂����B������n��̕��X�⒆�w���̊F���A�����e����Z��O�ɗ����Ă��������������Ă��������Ă��܂��B
�@�u�c�����������鎞�ɂ́A����̖ڂ����Ă���������Ƃ����ł��B�c�v�����͏����Ƃ������ƂŁA�ЊL���w�Z�̑����ψ���̐l�������A�ЊL���w�Z�̑S�Z����ɗ��ăC���^�r���[���������Ă���܂����B�q�ǂ������ɂ������̈Ӌ`�₠�����̃|�C���g�Ȃǂ��m�F���Ă���܂����B
�@�������^���̐������F���đł��グ���A��ӂ̉ԉu�ЊL����̉v���A���ꂢ�ɊJ���܂����B���C�Ȃ��������A�����ɂ����Ƌ����n��悤�ɂ��Ă��������ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N10��2���i���j |
| 5�N���A���R�����ɖ����s���Ă��܂����I |
 |
 |
|
�@5�N���́A����̎��R����2���ڂ̌ߑO���ɁA�����̌����s���܂����B���͉J���~���Ă��܂������A3�l�̊w�|���̕��X�ƃO���[�v���Ƃɑ������Ă����܂����B
�@�r���A�T���K�j��S�A�g�r�Q�����A�A�~�Ȃǂ��g���ĕ߂܂��܂����B�Ȃ�ƁA�C���i��߂܂����q�ǂ������܂����B�r������J���オ��A���͂��Ȃ���X�̊Ԃ���蔲�����������z�����肵�āA������ڎw���܂����B�����ł��Ȃ��l�X�Ȏ��R�̌����A�݂�ȂŊy���ނ��Ƃ��ł��܂����B
�@�q�ǂ������́A2���Ԃ̎��R�������I���āu�ЊL�Ƃ͈Ⴄ���R�̗ǂ����Ŋ����邱�Ƃ��ł����B�Q���Ԋy���������B�v�u�J���[���ł�����������ꂢ�ɂ�����A���������ꂢ�ɂ����肷�邱�Ƃ��ł����B�v�����̃o�g�������ɂȂ��邱�Ƃ��ł����B�v�Ƃ��������z�������܂����B�����������A�傫���Ȃ��ċA���ė���5�N���̎q�ǂ������ł��B�����Ƃ����̌o�����A���ꂩ��̊w�Z�����̂��낢��ȏ�ʂŐ����Ă��邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N10��1���i�j |
| 5�N���A���R�����Ŋ撣���Ă��܂� |
 |
 |
|
�@5�N���́A���9��30��(���j����A�����s�ɂ��鍑���������N���R�̉ƂɎ��R�����ōs���Ă��܂��B
�@����́A�ߑO���ɁA�V�������j���[�ł���u�X�g���[�g�n�C�N�v�Ƀ`�������W���܂����B�e�O���[�v�ŃR���p�X�𗊂�ɁA��Ԃ����������Ă܂������S�[����ڎw���܂����B�̎}��N���̑��ɕ������A�݂�Ȗ����ɐ��҂��܂���!
�@�ߌォ��́A��O���тŃJ���[���C�X�����܂����B���������ł��܂ǂɉ��������A�撣���č��܂����B���N�x�̓R���i�ЂŁA�����߂Ă̒������K�ł������A�ǂ̃O���[�v�����������ł��܂����B��́A�L�����v�t�@�C���[���y���݁A�݂�Ȃ������薰��܂����B
�@�����́A�J�̒��A�����T���Ƀ`�������W���Ă��܂��B�y����ł��邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N9��30���i���j |
| �T���搶�A���悤�Ȃ�I�i���C���j |
 |
 |
|
�@�����̒������̎��ԁA�Վ��S�Z������s���܂����B2�N�Ԃ̔C�����I�����A����10���ɃA�����J�̃��V���g���B�ɋA������ALT�̃T���搶�̗��C���ł��B
�@�u�cQuizgame with points was so fun.�@Also interview game
in�@Halloween�@was g��eat.�c�v �Z������̃T���搶�̏Љ��������A2�l�̑�\���������S���āA�p��ł́u���ӂ̌��t�v�Ƃ��̖|����A�T���搶�Ǝq�ǂ������ɓ`���܂����B�����āA�ԑ��ƑS�Z�����̃��b�Z�[�W���������J�[�h���A�T���搶�Ƀv���[���g���܂����B
�@���̌�A�S�Z�̎q�ǂ������ŁA�T���搶�o�[�W�����̃G�[����܂����B�u�c��D����D���T�`���A��D����D���T�`���c�v
�@�h�A�����J�̍��Z���ɓ��{���������搶�ɂȂ�h�Ƃ��������A���Ȃ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B���܂ŁA���邭���C�Ɏq�ǂ������ɉp��������Ă�������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N9��29���i�j |
| �V�����X�|�t�F�X�A�����ɏI���I |
 |
 |
|
�@9��26���i�y�j�ɁA�O������̉J�ƃO���E���h��Ԃ��S�z����钆�A�X�|�t�F�X�����{���邱�Ƃ��ł��܂����B����������APTA�̖����̊F�l�𒆐S�ɃO���E���h�̐�����Ƃ����Ă����������������ł��B
�@�q�ǂ������́A�X���[�K���u�V�����X�|�t�F�X�A�S�͂ŏ������������I�v�̂��ƁA�k�����E�����[�Ȃǂɐ���t�̗͂��o�����Ƃ��ł��܂����B���ɁA�e��s�������~�ɂȂ�A���N�x�ŏ��ōŌ�ɂȂ�ۓJ���̃h�������t�����Ă����������Ƃ��ł��A��ς��ꂵ���v���܂����B�܂��A��������ł��A��l��l���u�S�͂Łv���g��ł���l�q���`������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�ŏI���ʂ́A���Z�D�����ԑg�A�����D�������g�ł����B���̏��s�ȏ�ɁA�q�ǂ������̂�������̐��������p�����Ă����������Ƃ��ł����Ǝv���Ă��܂��B���܂ł̂������E�����͓��A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N9��25���i���j |
| 3�N���A����̊w�K���撣���Ă��܂� |
 |
 |
|
�@3�N���́A����̊w�K�Łu�T�[�J�X�̃��C�I���v�Ƃ������ꕶ�̓ǂݎ����s���Ă��܂��B���C�I���̂��́A�j�̎q�Ƃ̌𗬂ɂ���āA���̗D�����ɐG��Ēj�̎q����������ƃT�[�J�X�̍ŏI���Ɍ����Ă��C���o�܂��B�������A�O���̖�A�j�̎q�̉Ƃ��Ύ��ɂȂ�A���͖������Œj�̎q�������o���Ƃ�������ł��B
�@�u�킽���́A���͂��E���ŗD�������C�I�����Ǝv������B���R�́c�v�����̊w�K�ł́A�q�ǂ������́A�{���ɗ����Ԃ�Ȃ���A����ł��܂������ɁA�莆�œ`���������e���l���܂����B�����̍l�����O���[�v�Ō𗬂��A�c��܂��Ă���莆�������܂����B
�@�q�ǂ������́A���܂ł̊w�K�����ƂɁA�����̖����]���ɂ��Ă܂Œj�̎q�����������ւ̎莆���A�W�����ď������Ƃ��ł��܂����B���t�ɂ�������ēǂ����Ƃ���p�����A����ɐg�ɂ��Ă��āA�w�K�̐[�܂�������܂��B
|
|
|
| 2020�N9��24���i�j |
| 5�N���A���Ƀ`�������W�I |
 |
 |
|
�@�T�N���́A������1�E2���ɑ����I�Ȋw�K�̎��ԁu���l�Ɋw�ԁv�̈�Ƃ��āA����̌������Ă��������܂����B��N�x�܂ł������b�ɂȂ��Ă��钬���̈��B���A���N�����ɂ��ċ����Ă��������Ă��܂��B
�@�u��̉�����20�p���炢�̂Ƃ��������ł������莝���āA��C�ɗ͂����Đ�܂��B�c�v��̊���������B����ɋ����Ă�����Ă���A���ۂɃ`�������W���܂����B����������Ђ��ł���A���������ŕ����ĉ^�т܂����B���̌�A�R���o�C����ŐV���̕đ܂��ړ�������@�B�������Ă��炢�܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�̂̐l�͂���Ȃɑ�ςȂ��Ƃ����Ă����̂��v�u��J���Ĉ�ĂĂ������A���Ă��c�����H�ׂ����v�Ƃ��������z�������܂����B���Ɛ̂̈Ⴂ��A�_�Ƌ@�B�̗l�X�ȍH�v�A�_�Ƃ̐l�X�̋�J�∤��ɋC�t���ėǂ������ł��B����A����Ɂu���l�̋Z�v�ɂ��Ċw��ł����܂��B
|
|
|
| 2020�N9��18���i���j |
| �������K��X�|�t�F�X���s�ψ���i��ł��܂��� |
 |
 |
|
�@�X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�����A���悢��1�T�Ԍ�ɋ߂Â��Ă��܂����B�u�c���g�́A�k�^����ŗ��K�����܂��I�c�������āA�W�܂��Ă��������I�v�u�n�C�I�I�v�����c���̕����̐��ɉ����āA�S�Z����傫�Ȃ̎q�ǂ������̐����������Ă��܂��B�q�ǂ��������A�������̉������K�Ȃǂ�ʂ��āA�X�|�t�F�X�ւ̋C���������܂��Ă��܂����B
�@���N�x�́A�R���i�Ђ̂��Ƃ�����A�ی�҂̊F����̊ϐ�ꏊ���A��N�����肳���Ă��������܂��B�����ŁA�����ł��F����ɂ������茩�Ă����������߂ɁA��������̑��`�̌�����ی�Ґȑ��ɕς��ė��K���Ă��܂��B
�@�����A�S�`�U�N���́A�Ō�̃X�|�t�F�X���s�ψ���ŊJ��̗��K�����܂����B���T�́A�S�Z���K�ōŏI�m�F�����Ă����܂��B�V��Ɍb�܂��Ƃ����ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N9��17���i�j |
| 6�N���A�e�P������Ŋ撣���Ă��܂����I |
 |
 |
|
�@6�N���́A���9��16���ɁA���R�^�������ŊJ�Â��ꂽ����J�s�e�P������ɎQ�����Ă��܂����B�R���i�Ђő��𒆎~����s�������������A�s����6�N�����ꓰ�ɏW�܂��Ă̑��J�Âł������Ƃ́A�{���ɂ��肪�������Ƃł��B
�@6�N���́A�u�������������Ă���́v�����ׂďo���邱�Ƃ�ڎw���āA�����̃G���g���[��ڂɎQ�����܂����B�x�X�g�L�^��啝�ɍX�V�����q�ǂ���������ϑ����A���ܐ����\�z�ȏ�ɑ��������������ł��B
�@�u���Z���y������������ǁA�����ł�����オ�����v�u���ȃx�X�g�X�V�ł��āA���K�����b�オ�������v�ƁA�q�ǂ������͐U��Ԃ��Ă��܂����B�������ł̗��K��ˑR�̉J�ł̒��~�ȂǁA�v���悤�ɗ��K�ł��܂����A�q�ǂ������ɂƂ��Ă͑傫�Ȏ��M�ɂȂ�܂����B���܂ł̂����͂�T�|�[�g�A��ς��肪�Ƃ��������܂����B���̌o�����A�X�|�t�F�X�▾������̐����ɐ������Ă������Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N9��15���i�j |
| 3�N���A���h�����w�ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@3�N���́A�����̌ߑO���ɎЉ�ȁu�n��̈��S�����v�̊w�K�̈�Ƃ��āA����J���h���Ɍ��w�ɍs���Ă��܂����B
�@�u119�Ԓʕ���ƁA�n�}��ɏꏊ��������܂��B�c�v�q�ǂ������́A�܂��ŏ��ɕ����Ȃǂ̑����������Ă�������蒅���Ă�������肵����A119�Ԓʕ���ʐM�w�ߎ��������Ă��炢�܂����B�����āA�e����h�����Ԃ�~�}�ԁE�͂����ԓ��������Ă��炢�܂����B���ɁA�~�}�Ԃɂ͈�l��l���悹�Ă��炢�A���������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�q�ǂ������́A�w�Z�ɋA������A�u�Ύ��̎��͖�Q�Okg�̑�����g�ɒ�����B�g���[�j���O���K�v�Ȃ킯���I�v�u�����̏Z��ł��钬����肽������A�l�̖��ɗ�������������h�m�ɂȂ����Ȃ�Ă��炢�I�����������I�v�ƁA�U��Ԃ�������Ă��܂����B�s���̖��ƍ��Y��24���Ԏ���Ă�����h���̊F����́A�H�v��w�͂�m�邱�Ƃ��ł��A�L�Ӌ`�Ȍ��w�ƂȂ�܂����B
|
|
|
| 2020�N9��14���i���j |
| �ЊL�܂�@���̌� |
 |
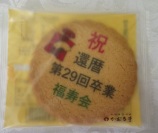 |
|
�@����́A�ЊL�܂�ɂ��Ă̂��ڂ�b�ł��B
�@1�ڂ́A���̎ʐ^�̊G�ł��B2�N����1�w��������g��ŕ`���Ă����u�ЊL���̉ԉ̊G�v���A���A����J�s�����̈�ق̂P�K�z�[���ɏ����Ă���܂��B�����������q�ǂ������́u�ԉ����ꂢ�ɑł����������ˁv�u�J���t���ȉԉ��`���Ă悩�����ˁv�Ƙb���Ă��܂����B��m���P�O�����قǂ̑傫�ȊG���A�s���̕��X�Ɍ��Ă��������Ă��܂��B���Ԃ���������A���Ђ������������B�i���������P�����܂����c�j
�@�Q�ڂ́A�E�̎ʐ^�̃N�b�L�[�ł��B�җ�̕�����̊F�l����A���z�̂���t�ƂƂ��ɁA�����������ł��������܂����B�H�c���ɕ�炷����̕����A�Ǝ҂̕��ɍ���Ă�����ĕ�����ɂ킴�킴�����Ă��������������ł��B��������Ă��Ă��̋���z���u��y�v�̐S�ӋC�ɐG��邱�Ƃ��ł��܂����B����t�ƂƂ��ɁA��ς��肪�Ƃ��������܂����B
�@���N�́A����A�u�����̕ЊL�܂�v�����{�ł��邱�Ƃ�����Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N9��11���i���j |
| �Q�����V���M�����i�H�j�̕��X�����Ă���܂����I |
 |
 |
|
�@���9��10���ɁA�L�u�̕��X�̏W�܂�́u�Q�����V���M�����i�H�j�v���A�ЊL���w�Z�ɋ}�ɗ��Ă��������܂����B10�l�قǂ̒����̊F���A�q�ǂ������ɃV���M�����������E�܂�C���𖡂�킹�����Ƃ����v���ŁA���x�݂̎��ԑтɁu�ʑ���v�̉���t���ŗ��Ă��������܂����B
�@�V���M���̉������āA�q�ǂ��������A�������֑O�ɒ�w�N�𒆐S�ɂ�������W�܂�܂����B�����ŁA�O���E���h���g���ĉ�����������Ă��炦�邱�ƂɂȂ�܂����B�q�ǂ������́A�V���M���ɍ��킹�ċʑ��肪�ł��āA��ϊ��ł��܂����B�ߏ��̕��X�����l�����Ă�������A�q�ǂ������̗l�q��ڂ��ׂ߂āA������Ă��������܂����B
�@�u���܂肪�Ȃ��Ă��Ȃ����ȂƎv���Ă�����A���䂪�w�Z�ɂ��Ă���܂����B�P�N�Ԃ�ɂЂ��ς邱�Ƃ��ł��Ă��ꂵ�������ł��B�v�u�������Ƃӂ��̉��y�����ꂢ�ł����B�v���Ԃ�ɉ̂��������̂ł��ꂵ�������ł��B�v�ƁA�q�ǂ������́A���z��b���Ă��܂����B�Q�����V���M�����i�H�j�̊F����A�q�ǂ������ɕЊL�܂�̋C���𖡂�킹�Ă��������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N9��10���i�j |
| 1�E2�E�N���A�ԉ|�X�^�[�\��ɍs���Ă��܂����I |
 |
 |
|
�@�����9��9���i���j�ɁA1�E2�N���́A3�O���[�v�ɕ�����āA�����Ȃō�����ԉ|�X�^�[�̌f�������肢���ɍs���Ă��܂����B����A�V���Ȃǂł��Љ�ꂽ�h���[���B�e�̎ʐ^���g�����ЊL�������|�X�^�[�ł��B
�@�u�|�X�^�[��\��ɗ��܂����I�v���ꂼ��̕��S�̏ꏊ�ŁA����̕��X�ɒS�������߂Ă��肢���܂����B�q�ǂ��������f�������肢�����̂́A�ԉΉ������X�ǁE��s�E���w�Z�E�ۈ牀�E���X������ȂǁA11�����ł��B
�@�q�ǂ������́A�A���ė�����u��ꂽ���ǕЊL���݂̂�Ȃ����ł��ꂽ�̂ł��ꂵ�������ł��v�u�|�X�^�[��z�����璬�̐l���Ί�ɂȂ��Ă��܂����B�Ί�̗͂��Ă������Ȃ��Ďv���܂����B�v�Ɗ��z��b������A�U��Ԃ���������肵�܂����B�����́A�ЊL�܂�2���ڂł��B���N�̍���E�����́A�����Ɛ���ɉԉ��オ���Ă��邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N9��9���i���j |
| 4�N���A�Z���^�[�Ɍ��w�ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@4�N���́A���9��8���i�j�ɁA�Љ�ȁu���̂䂭���v�̊w�K�̈�Ƃ��āA�����s������ɂ��钷���Z���^�[�Ɍ��w�ɍs���Ă��܂����B���̏Z���^�[�́A�ЊL���̉������ŏI�I�ɏ��������ꏊ�ł��B
�@�u�����r���́A�������̗͂���Ă��ꂢ�ɂ��āA�M�Z��ɖ߂��Ă��܂��B�c�v�q�ǂ������́A�܂������̕�����Z���^�[�̖�����A���ꂽ�������ꂢ�Ȑ��ɂȂ��Ă����d�g�݂��A�����Ă��������܂����B�����Ă��̌�A����J�s�Ⓑ���s�����̍L���͈͂̐����p�������ꂢ�ɂ��Ă���A�ƂĂ��傫�Ȏ{�݂����ۂɌ����Ă��炢�܂����B
�@�q�ǂ������́A�������ꂢ�ɂȂ��Ă����l�q�����w���āA�u�������͂ɂ����������Ă����v�u���������Ȃ��悤�ɂ������v�Ƃ��������z����������A�܂Ƃ߂ɏ������肵�܂����B�q�ǂ��������A������Ȏ����ł��ꂢ�ɂ���K�v�����邱�Ƃ�A�₦�������z���A���̐����ɂ��e�����邱�Ƃ��킩���Ă悩�����ł��B
|
|
|
| 2020�N9��7���i���j |
| �����c�̗��K���A�n�܂�܂��� |
 |
 |
|
�@�X�|�[�c�t�F�X�e�B�o���Ɍ����āA��T��3���i�j�ɉ����c���c�����s���A���T������K���{�i�I�Ɏn�܂�܂����B��N�x�܂ł́A���c������^����ɑS�Z�ŏW�܂��Ă���Ă��܂������A��^�E�k�^�ɕ�����čs���܂����B
�@�u�܂��͂��߂ɁA�����c������Č����܂��̂ŁA���Ċo���Ă��������I�v�u�n�C�I�v�c��1�����̂�G�[���ȂǁA����ނ��̃��j���[������܂��B���ꂼ��A�̎���U��t�����o���āA�݂�Ȃō��킹��̂��Ȃ��Ȃ���ςł��B�ł��A���̑�ς������z����ƁA���[�_�[�Ƃ��Ă���l��l�c���Ƃ��Ă��������A��C�Ƀ`�[�����܂Ƃ܂�܂��B
�@�c���́A�ԑg�u���Ɨ͂��P�ɂ��āA�D�����߂����܂��傤�B�v���g�u���K�͏��Ȃ��ł����A�����D�����߂����Ă����܂��傤�B�v�Ƙb���Ă��܂����B�������K�́A���ꂩ��X�|�t�F�X�Ɍ����āA�������̎��Ԃ��g���čs���Ă����܂��B�����Ɠ����́A�f���炵���������킪�����邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N9��4���i���j |
| �Z���Ȋw�������\�����܂��� |
 |
 |
|
�@���9��3���i�j�ɁA�Z���Ȋw�������\���k�^����ōs���܂����B���w�N�̕���2���A���w�N�̕���3���ɁA������čs���܂����B
�@���w�N�̕��ł�7�l�̑�\�����\���܂����B���d�b��A���Ɋւ��錤���A�M���ǂ�c�o������ȂǁA�����ʂɓn���Ă��܂����B�܂����w�N�ł́A��̂c�m�`��H�i�⒲�����̓��x�A�u�����v�ɂ��Ē��ׂ��q�ǂ�����3�l���A���\���܂����B���ꂼ�������������Ĕ�r������������A�����Ԃɓn��ώ@��������A�����ŏڂ������ׂ��肵�Ă܂Ƃ߂܂����B
�@���̔��\�̌�ɁA�u�\��ʐ^�ȂǁA�܂Ƃߕ����H�v���Ă��Ă������B�v�u�^�₩��X�^�[�g���āA����ނ����������Ē��ׂĂ���v�c�ȂǁA�q�ǂ������́A�F�B�̔��\���������蕷���A��������̎���⊴�z�����Ă��܂����B�[���������ԂɂȂ��Ă悩�����ł��B���ꂩ��A�s�������\��ɐi�ތ������I��A���������Ă����\��ł��B
|
|
|
| 2020�N9��3���i�j |
| 1�E2�N���A�h���[�����g���ă|�X�^�[������Ă��܂� |
 |
 |
|
�@1�E2�N���́A�����ȂŁA�R���i�Ђʼnԉ��グ���Ȃ��Ȃ����ЊL���̐l�������܂����߂ɁA�|�X�^�[������Ē����ɓ\�낤�Ƃ��Ă��܂��B���̃|�X�^�[�ɂ́A1�E2�N���݂�ȂŃO���E���h�Ɍ`�Â������ԉ̎ʐ^���ڂ���\��ł��B
�@�����ŁA�����9��2���i���j��3���ɁA�����̃h���[���B�e�̐��Ƃ̐l�ɗ��Ă��������A���q�ǂ������̎ʐ^���B���Ă��������܂����B�������ł������A�݂�ȂŊ撣���ĉԉ�\�����܂����B���̌�ɁA���ۂɎg�����h���[����B�e�����ʐ^�������Ă��������܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�ԉ̌`�Ɍ����Ă��ꂵ�������v�u�h���[���ɎB���Ă�����Ċy���������v�Ɗ��z��b���Ă��܂����B���ꂩ��A�O���[�v���ƂɍH�v���ă|�X�^�[������܂��B�����āA�����Z���^�[�₨�X�ɂ��肢���āA�\��ɍs���\��ł��B
|
|
|
| 2020�N9��2���i���j |
| 6�N���A�C�w���s�ɍs���Ă��܂����I |
 |
 |
|
�@8��31���i���j9��1��(�j�ƁA6�N���́A�ꔑ����ō��n�ɏC�w���s�ɍs���Ă��܂����B�o�����̎��́A�܂��J���c���Ă��܂������A���]�Í`���獲�n�ɓn��ƁA�L����\��ʂ�̊������ł��܂����B
�@1���ڂ́A���炢�D�̌��⑾�ی𗬊قł̊����A�S�[���h�p�[�N�ł̍������ȂǁA�q�ǂ������͂��ꂼ��̑̌��i���܂����B�܂��A�R�قǂ̂����������o����ɂ́A���͂̂���u�S���ہv�̎�����g�߂Ɋӏ܂��邱�Ƃ��ł��܂����B
�@2���ڂ��A���n���R�ł̍B���̌��w��Y�H���̃W�I���}��ށA�����ċ��̉��ז_�`�������W�ƁA���Ԃ������đ̌����܂����B�܂��A�g�L�̐X�����ł��A�g�߂ɕ����~�肽�g�L�̗l�q���ώ@���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�q�ǂ������́A�u���ۂ��������Ƒ傫�ȑ��ۂ̊v�܂ŐU�����Ă��Ăт����肵���B�v�u���V�̊��˂�^���Ō����甗�͂������Ă����������B�v�Ɗ��z��b������A�������߂��肵�܂����B
�@�R���i�Ђ̒��A6�N���S���ŁA�y�����E���܂�悭�E���C�ɏC�w���s�ɍs���ė��邱�Ƃ��ł��A�{���ɗǂ������ł��B�ی�҂̊F�l�A���܂ł̑̒��Ǘ��₲�������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N8��28���i���j |
| 5�E6�N���A�V���M�����t�̈��p�����n�܂�܂��� |
 |
 |
|
�@���27���i�j��1���ɁA6�N������5�N���ɃV���M�����t�̈��p�����K���n�܂�܂����B��N5�N�����A�u���݂̃L�b�Y�w�у����h�v�ʼn��t����V���M���̉��t���A6�N������y�ɋ�����̂ł��B
�@�p�[�g���Ƃɉ��y���◝�Ȏ��A���듙�ɕ�����āA5�N����6�N�����ق�1��1�̃y�A��g�݂܂��B�����āA5�N�������t����l�q���āA6�N�����A�h�o�C�X�����Ă��܂����B�u�����̃��Y�����A�����Ƒ����ˁB�v�u5�N���A�J�̉����݂�ȏo���āA�������ˁB�v�c�Ƃ��������������Ă��܂����B
�@6�N������5�N���ւ̈��p���̑�1�e�ł��B�ЊL���̓`���������p�����ƁA�^���Ɏ��g��ł��鍂�w�N�̎p�́A�ƂĂ����������ł��B
|
|
|
| 2020�N8��27���i�j |
| 6�N���A�Q�X�g�e�B�[�`���[�ƃ����[���K�I |
 |
 |
|
�@������8��25����5���ɁA6�N���́A�O���u�t�����������āA�����[���K���s���܂����B6�N���́A�X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�������łȂ��A9��15���i�j�ɗ\�肳��Ă���s�e�P������ɂ��Q������\��ł��B
�@����́A�R�[�`����A�S�����o�ꂷ��X�|�t�F�X�̃o�g���p�X�𒆐S�Ɏw�����܂����B�u�o�g����n���l���A�ӔC�������āw�S�[�I�x�w�͂��I�x�̐��������邱�Ɓv�u��{��{�̗��K�̌�ɁA��������R�~���j�P�[�V�������Ƃ��đł����킹�邱�Ɓv�c���A���K���Ȃ��瑽���̂��Ƃ������Ă��������܂����B
�@�����5�E6�N�̗�����K�ł́A�M���ǂɂȂ�Ȃ��悤�ɐ܂��ݎ��e���g���o���ē��A���������A���܂߂ɐ����⋋��������A�����^�u���b�g��z�����肵�܂����B�������t�F�[�����ۂő�Ϗ����Ȃ肻���Ȃ̂ŁA���Ȃ́u�M���w���v�Q�l�ɁA���K�̉ۂ����߂Ă����܂��B�������̂قǁA��낵�����肢���܂��B
|
|
|
| 2020�N8��25���i�j |
| �S��������āA2�w�����X�^�[�g�I |
 |
 |
|
�@���8��24������A2�w���������ɃX�^�[�g���܂����B�ċx�݂ɂ͑傫�ȃP�K��a�C�E�����E���̓��̘A���͂Ȃ��A�S�������Ă�2�w�����}�����đ�ς��ꂵ���ł��B
�@����ԂɁA2�w���̎n�Ǝ����^����ōs���܂����B�u4�̂߂��Ă������āA2�w���撣���Ă��������ł��B�v��6�N���̑�\���猈�Ӕ��\������܂����B�����āA�Z������q�ǂ������ɁA�u�s������ʂ��āA�Z�̂�搂��Ă���M�Z��┪�C�R�̂悤�Ȑl���߂����Ă����܂��傤�B�v�ƁA�N�C�Y��ʂ����b������܂����B�����w����C����́A��4���̐������̂߂��Ă�A�R���i�E�C���X�ɊW���邢���ߖh�~�ɂ��Ă̘b������܂����B
�@9��26���ɗ\�肳��Ă���X�|�[�c�t�F�X�e�B�o���Ɍ����āA��l��l�̗͂��`�[���̗́E�S�Z�̗͂ɍ��߂Ă��������Ǝv���܂��B2�w�����A��낵�����肢�������܂��B
|
|
|
| 2020�N8��3���i���j |
| 1�w���I�Ǝ����I���܂��� |
 |
 |
|
�@��T�̋��j��7��31���ɁA1�w���I�Ǝ����s���܂����B�V�^�R���i�E�C���X�̊W�ŁA�ċx�݂��N���Z�k���āA8��1���`23���܂ł�23���ԂŎ��{���܂��B
�@�u1�w���́A�F�B�̘b�Ȃǂ��������蕷���A�w�K���W�����Ċ撣��܂����B�c�v�u���Ȃ��Ƃ��A�撣��ł���悤�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B�c�v�I�Ǝ��ł́A2���̑�\������1�w���̐U��Ԃ�Ȃǂ̔��\������܂����B�Z������́A1�w���̎q�ǂ������̗l�q���ʐ^�ŐU��Ԃ�A�S�Ɏc���Ă���4�̂��Ƃ�b���܂����B
�@�~�J���A���悢�斾�����悤�ł��B�����w����C���炠�����u�ċx�݂ɋC��t���Ăق������Ɓv�����Ȃ���A���S�Ŋy�����ċx�݂��߂����ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N7��29���i���j |
| �U�N���A�k�Ѓ~���[�W�A���u���Ȃ��فv�Ŋw�K���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@����V���Q�W���i�j�̌ߌ�ɁA�U�N���́A����J�s��m�R�ɂ���k�Ѓ~���[�W�A���u���Ȃ��فv�ɍs���Ă��܂����B���̊w�N�ł����g��ł���h�Њw�K�̈�Ƃ��āA�w�K���Ă��܂����B
�@�q�ǂ������͍ŏ��ɑS���Ō��w�̗���ɂ��Đ������܂����B���̌�O��������邽�߂ɂQ�̃O���[�v�ɕ�����āA�̌��k�̉f�����ς���A�R�c���K�l�������Ē��z��k�Ђ̑̌��������肵�܂����B���̌�A�V�����X���b�p��r�j�[���܉J���H�Ȃǂ����܂����B�܂����R���w�Ŕ��̗l�q��t�̎������u�ȂǂɐG��A�n�k�ɂ��Đg�̂Ŋ�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�u����܂Œn�k���Â��݂Ă�������ǁA����͖{���ɕ|���Ɗ������B�v�u�����Ƃ������̔��������Ă��������B�v�q�ǂ������́A���Ȃ��قɍs���āA�n�k�̕|��������̑���Ȃǂ�������̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł����悤�ł��B���̌o�������āA�������̎��́A�����̖�����邱�Ƃ͂������A����̐l�̂��߂ɉ����ł��邩�l���čs���ł���悤�ɂȂ��ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N7��27���i���j |
| ���w�N�A�Q�X�g�e�B�[�`���[�ɂ�闤��g���[�j���O |
 |
 |
|
�@��T�V��21���i�j��22���i���j�ɁA6�N����5�N���́A�Q�X�g�e�B�[�`���[�����������āA������K�̊�b�g���[�j���O���s���܂����B
�@�u�O�ƌ��̑��̊J���̊p�x���A�ł��邾���傫���I�v�u���̉��ɂ���̂̒��S����A���������グ��C���[�W�ŁI�v�u���̍����Ђ˂�Ȃ���A1�����L���悤�v�c�l�X�ȑ���Ƃ��̃|�C���g���A�C���[�W���₷�����t�ŋ����Ă��������Ȃ���A���낢��ȓ������o�����܂����B���ɁA6�N���͍����тɂȂ��铮���A5�N���͑��蕝���тɂȂ��铮������K���܂����B
�@�q�ǂ������́A���K���I�������A�u�|�C���g���ӎ����Ȃ��瑖�肽���v�u�����Ă���������Ƃ𑱂���ƁA���������Ȃ�C������v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B���ꂩ��A��������߂����āA����������������������Ȃ���A�^���\�͂����߂Ă����܂��B
|
|
|
| 2020�N7��22���i���j |
| �T�E�U�N���A���j�������s���܂��� |
 |
 |
|
�@����V���Q�P���̂P�E�Q���ɁA�T�E�U�N���́A�O���u�t�̕������������Ă̐��j���Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂����B�J�̂��߂ɂQ�����A���{���P��ɂȂ��Ă��܂��܂������A�q�ǂ������͂���������K���܂����B
�@�u���p�������鎞�ɁA���ւ����ꏏ�ɌX���܂��v�c�O���́A�N���[���̑��p���𒆐S�ɗ��K���܂����B���E�̎�Ƃ����K���J��Ԃ������ɁA�ǂ�ǂ��B���܂����B�܂��A�㔼�́u���������̗��ŁA���������܂Ŕ���܂��v�c�ȂǁA���j���̑����̓����𒆐S�ɗ��K���܂����B
�@�q�ǂ������́A���K��ʂ��āu���ւ����X���đ��p���������璾�܂Ȃ��ő����z���₷�������B�v�u����������ƕ��j���ɂ��ċ����Ă��炢�����Ȃ��B�v�ȂǂƊ����Ă��܂����B�q�ǂ������ɂƂ��āA�����̐����������ł����Q���Ԃł����B�R�[�`�A��ς��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N7��21���i�j |
| ���E��w�N�A�h�Ћ����Ɏ��g�݂܂��� |
 |
 |
|
�@�����̂Q���ɂR�E�S�N�����A�R���ɂP�E�Q�N�����A�h�Њw�K�o�O�u���Ɏ��g�݂܂����B������k�Ѓ~���[�W�A���u���Ȃ��فv����A�Q���̕����A�u�t�Ƃ��ė��Ă��������܂����B
�@�q�ǂ������́A���z��k�Ђ̎��̓����ʐ^�������Ȃ���A��Q����ɂ������O��h�ЃN�C�Y�ɓ����܂����B�܂��A�㔼�ɂ́A�R�E�S�N���͐V�����X���b�p�Â���A�P�E�Q�N���̓L�b�`���y�[�p�[���g���Ẵ}�X�N�Â�������܂����B���ŏ����ł��𗧂��̂Ƀ`�������W���܂����B
�@�Q�N���̎q�ǂ������́A�u�n�k�ɂ��Ēm��Ȃ����Ƃ������������v�@�Ƃ��������z�������܂����B�����̑�ς���m��A�ЊQ���N���������ɉ����ł��邩�l���邱�Ƃ��ł��܂����B
|
|
|
| 2020�N7��20���i���j |
| 5�N���A�~�}�@�u�K����s���܂��� |
 |
 |
|
�@������5�E6���ɁA5�N���́A�h�Ћ����̈�Ƃ��āA�~�}�@�u�K�����u���܂����B����J���h����2���̕�����A�u�t�Ƃ��ė��Ă��������܂����B
�@�ŏ��ɁA�q�ǂ������́A���ۂɂ������ЊQ�⎖�̂̎ʐ^����A����������Ɛg�߂Ȑl���|�ꂽ���ɁA�ǂ��m�F���s�����邩���w�т܂����B�����Ď��ۂɁA���h���ɓd�b���Ȃ���119�Ԓʕ�̎d������K���܂����B�㔼�ɂ́A�S�x�h���@�̂�����`�d�c�̑�����A��l���̌����Ȃ���w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�S�x�h���̂��������������B�v��������ꂽ�v�u�l���|��Ă�����ǂ��s�������炢���̂����������v�u�l�̖�������悤�Ɋ撣�肽���v�Ƃ������C�t���⊴�z�������܂����B���ۂɐg�̉��̐l���|�ꂽ���A����̊w�K���v���o���āA�����ł����������čs���ł���Ƃ����ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N7��17���i���j |
| 5�N���A���Y�Ƃ̌��w�ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@5�N���́A�Љ�ȁu���Y�Ƃ̂�����Ȓn��v�̊w�K�̈�Ƃ��āA���16���̌ߑO�����g���āA����`�܂Ō��w�ɍs���Ă��܂����B�����āA���Ƌ����g������x���̕��X�ɁA����s�̐��Y�Ƃ̊T�v�������Ă�����������A���ۂɋ��D�Ȃǂ������Ă����������肵�܂����B
�@�܂��A�q�ǂ������́A�b�����Ă�����������A��������̎���ɓ����Ă��������܂����B���̌�A�`�ɔ��܂��Ă��邢�낢��Ȏ�ނ̋��D����������Ă��������܂����B�܂��A�߂�������①����{�݂̒��ɂ�����Ă��������܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�����ȋ��@�ŋ����l���Ă��邱�Ƃ����������v�u�l�鋙�Ƃ�������Ȃ��A�����Ă鋙�Ƃ����Ă��邱�Ƃ�m�����v�u�q�Q�\���_�C�̗{�B���������Ăق����v�Ȃǂ̊��z�������܂����B�V�N�ŗǎ��Ȃ��̂���������o�ׂ��邽�߂ɁA��������̍H�v��w�͂��s���Ă��邱�ƂɋC�t�����Ƃ��ł��A�L�Ӌ`�Ȍ��w�ɂȂ�܂����B
|
|
|
| 2020�N7��16���i�j |
| �X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�����s�ψ���������n�߂܂����B |
 |
 |
|
�@������14���i�j��6���ɁA��P��X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�����s�ψ���s���܂����B4�E5�E6�N���́A���łɎ����̏����̈ψ�����A���ꂼ��̊w�N�őI�l���ʂ��Č��߂Ă��܂����B
�@�Z������A��N�x�̃X�|�t�F�X�����̎ʐ^�����ƂɁA�q�ǂ������Ɋ��҂���p��A�V�^�R���i��ō��܂łƈႤ�X�|�t�F�X�̎��������̘b������܂����B���̌�A���ۂɊe���s�ψ���Ƃɑg�D�Ґ������߁A�����̌��ʂ����m�F���܂����B�����āA��������ƁA���x�݂��g���Ď��ۂɐ��슈�����ɓ����Ă�����s�ψ��������܂��B
�@�����c��O�b�Y�S���̎q�ǂ������́A�u����l���y���߂�O�b�Y����肽���v�u�S�Z������オ�鉞���ɂ������v�Ƃ����v���������Ċ��������Ă��܂��B�ċx�ݑO�ɁA������x�S�̂Ŋ���������s�ψ������܂��B9��26���i�y�j�̖{�ԂɌ����āA������������i�߂Ă����܂��B
|
|
|
| 2020�N7��15���i���j |
| 2�N���A�U���K�j�o�������s���܂��� |
 |
 |
|
�@2�T�Ԗ����U���K�j�̐��b�𑱂���2�N���́A���14���i�j��1���ԖڂɁA�u�U���K�j�o�����v���s���܂����B�̈�قł��ʂ�̉��������A�k�^����Ɩk�Z�ɂ̊Ԃɂ���r�I�g�[�v�ɕ����ɍs���܂����B
�@�̈�قł́A�U���K�j�����̂��߂Ɂu������̍����v�����t������Ō�̂������E�ԃv���[���g�Ȃǂ������肵�܂����B�����āA�q�ǂ������́A���������̃O���[�v�Ő��b���Ă����U���K�j�Ɂu���C�łˁc�v�Ɛ��������Ȃ���A�J�̒��U���K�j������܂����B
�@�o�������I�������A�q�ǂ������́A�u�ŏ��͕|���������ǁA���킢���Ȃ����v�u�Z�݂������̂��āA��ςȂȂƎv���܂����v�c�ƁA���܂ł̊�����U��Ԃ��Ă��܂����B����������ĂĂ����ƈ�������Ƃ������Ƃ�F�B�Ƌ��͂���y�������w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�q�ǂ����������ׂď������������|�X�^�[���A�����̘L���ɓ\���Ă���܂��B���Z�����܂ɁA�������������B
|
|
|
| 2020�N7��13���i���j |
| 2�w�N�R�����[���@������܂��� |
 |
 |
|
�@�����̒��x�݂ɁA�X�|�[�c�ψ����Ấu2�w�N�R�����[���v��1�E6�N���̕����s���܂����B��T�A�J�������ĉ������Ă��܂������A�����͓܂��̉����{���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���ꂼ��̊w�N���A�u�{�C�`�[���F�ԐF�v�u���C�`�[���F���F�v�u�Ȃ��`�[���F���F�v�̎O�`�[���ɕ�����A1�N���͂T�O���E6�N����150���𑖂�܂��B1�N��6�N���݂ɑ����āA�o�g�����Ȃ��܂����B�u�Z�Z����A�����`�v�ƁA�e�`�[�����A���������̒��Ԃ��ꐶ�����������Đ���オ��܂����B
�@�����[���I�������A�u������x���肽���I�v�Ƃ�������̎q�ǂ������̐����������܂����B���Ԃ��Ȃ��Ăł��܂���ł������A���ꂩ����ꏏ�Ɋ������������āA���悭�Ȃ��ė~�����Ǝv���Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N7��10���i���j |
| ��w�N���v�[���ɓ���܂��� |
 |
 |
|
�@���7��9����3�E4���ɁA��w�N�́A���N�x���߂Ă̐��j���Ƃ��s���܂����B�J���オ������ł�����Ɣ����������ł����A�q�ǂ������͌��C�ɒ��ւ��ē���܂����B
�@�u����Ă悩�����I�v�u����Ɠ����ˁv�c2�N���́A��N�x�̉j�����v���o���Ȃ���A�O���[�v�����̌���Ƀ`�������W���܂����B�܂��A1�N���́A���̒����������A�t���t�[�v������������A�r�[�g���g���ĕ������肵�āA�ۈ牀��肸���Ɛ[���v�[���ɏ���������܂����B
�@���j���Ƃ��I��������ƁA�u���̃v�[�����y���݂��ȁB�v��2�N���͘b���Ă��܂����B�܂��A1�N�����u����Ɠ��ꂽ�v�[���y���������ł��B�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�j�����тɁA��B���Ă������Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N7��8���i���j |
| ��w�N�A��ʈ��S�������s���܂��� |
 |
 |
|
�@����Ɉ��������A2�E3�E4�����g���āA4�E5�E6�N����ʈ��S�������s���܂����B�������A�S���I�ɋ����J���~�葱���Ă��邽�߁A��^����ōs���܂����B
�@��ʎw�����̕�����́A�o�Z�ǒ��Ƃ��Ă̖����⓮����A���]�Ԃɏ�鎞�̈��S�m�F�̂����Ȃǂ������Ă��������܂����B�����āA�q�ǂ������́A�̈�ٓ��̃R�[�X����l2�A���S�m�F�J�ɂ��Ȃ��玩�]�Ԃʼn�邱�Ƃ��ł��܂����B
�@4�N���́u���f�����O�ł�������Ǝ~�܂肽���v�@5�N���́u���E�̊m�F���������肵�āA���S�Ɏ��̂Ȃ����]�Ԃ���肽���v�Ɗ��z��b���Ă��܂����B�����̎����̌�ʃ}�i�[��U��Ԃ�A�����@��ɂȂ�܂����B
�@�ی�҂̊F�l����́A���]�Ԃ̏�����w�Z�ւ̔����E���o�Ȃǂł������͂��������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N7��7���i�j |
| ���w�N�A��ʈ��S���������{���܂��� |
 |
 |
|
�@�����̌ߑO���ɁA1�E2�E3�N���́A��ʈ��S�������^����ōs���܂����B�V�^�R���i�E�C���X�̉e����4���\��̋����𒆎~���܂������A�q�ǂ������̓����̗l�q����}篂��肢���A���{���Ă��������邱�ƂƂȂ�܂����B
�@��ʎw�����̕��X��ЊL���݂���A�s�E���̕�6���̊F���A�Q�X�g�e�B�[�`���[�Ƃ��ċ삯���Ă��������܂����B2�E3�N���͎��]�Ԃ̏����𒆐S�ɁA1�N���͎��ۂ̕��s�̗��K�Ǝ��ŋ��ŁA��ʈ��S�ɂ��Ċw�т܂����B
�@2�N���́A�u���]�Ԃɏ��O�E�������A���]�Ԃ��牺��鎞�ɁA�E�����������Ƃ�������܂����v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B�܂��A1�N���́u���S�ɕ������@��������������A�C��t���ĕ��������v�Ɗ��z��b���Ă��܂����B�����̏�w�N�̌�ʈ��S�����́A�V�C�����A���ۂ̓��H���g���Ăł���Ƃ����ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N7��6���i���j |
| 3�N���A���݂���Ɏ��₵�܂��� |
 |
 |
|
�@3�N���́A��T7��3���i���j�ɁA�Љ�ȁu�n��̈��S�����v�̊w�K�ŁA�ЊL���ݏ��̕��Ɋw�Z�ɗ��Ă��������܂����B�����āA�x�@�̎d���ɂ��ċ����Ă�����������A�u7����v�������Ă�������肵�܂����B
�@�u�ЊL�ł�1�N�ɉ������炢���̂��N���܂����v�u���d���ōH�v���Ă��邱�Ƃ͂���܂����v�c�q�ǂ������́A�����肳��Ɏ�������������肵�܂����B�����肳����A�u�����ɑΉ��ł���悤�ɒn��̐l�⓹�Ȃǂ���������o����悤�ɂ��Ă��܂��v�ȂǁA�d���̋�J���肪���Ȃǂ�b���Ă��������܂����B
�@�q�ǂ������́A�����肳��̎d���ɂ��āA�u������������Ă���Ă���v�u�����������B�������l�����d�����������v�Ƃ��������z�������܂����B���ꂩ�炳��ɁA�x�@�̕��ȊO�Ɉ��S�E���S�Ȓ��Â���Ɋւ���Ă��������Ă���l�����ׂĂ����܂��B
|
|
|
| 2020�N7��3���i���j |
| ���w�N�A���j���Ƃ��n�߂܂��� |
 |
 |
|
�@���7��2���i�j�ɁA�{�N�x���߂Ă̐��j���Ƃ𒆊w�N��5�E6���ɍs���܂����B�ߑO���ɗ\�肵�Ă���1�E2�N���́A�C�������܂�オ��Ȃ��������߂ɁA�v�[���ɓ��邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
�@�u���\�A�������I�v3�E4�N���̎q�ǂ������́A�������������V�����[�𗁂т���A���ꂢ�ɂȂ����v�[���ɓ���܂����B�����āA��N�x�܂łɐ��j�ŗ��K���Ă������Ƃ��A1��1�m���߂܂����B���̓f�����E�_���}�����E�ӂ������E�o�^���c�ȂǁA�q�ǂ������̑̂́A�ł���悤�ɂȂ������Ƃ���������o���Ă��܂����B
�@�q�ǂ������́A���Ƃ��I�������u�������ǃv�[���̒��͋C�����悩�����I�v�u�r�[�g���g���ď��ɉj������I�v�Ɗ��ł��܂����B���ꂩ��C�����オ��A���ꂼ��̊w�N���C�����悭���j���Ƃ��ł���Ƃ����ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N7��2���i�j |
| ���Ċ���O���[�v�獇�킹������܂��� |
 |
 |
|
�@�����̎�������ł́A���N�x�̂��Ċ���O���[�v�̊獇�킹����s���܂����B�V�^�R���i�E�C���X�̊W�Œx��܂������A����͗l�X�Ȋ����ł��Ċ���O���[�v�œ����܂��B
�@�u�ЊL���w�Z�̎q�ǂ������̐l���́A���l�ł��傤�H�v�u�ЊL���w�Z�́A�n�����N�ł��傤�H�v�c�����́A�O���[�v���ł̎��ȏЉ�̑��ɁA�u�ЊL���w�Z�O���N�C�Y�v���O���[�v���ő��k���܂����B6�N�������S�ƂȂ��čl�����܂Ƃ߁A�R��̃N�C�Y���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�Ō�ɁA3�l�́u���݂̖����W���[�v���o�ꂵ�A���N�̃X���[�K���u���C�ɖ{�C�łȂ��悤�I���݂̖؎�����v���݂�ȂŊm�F���܂����B���Ċ���O���[�v�������オ��A��������{�i�I�ɃX�^�[�g�ł��Ă悩�����ł��B
|
|
|
| 2020�N6��30���i�j |
| ���݂̖؎�����A���j�Z�t����Ɏ��g��ł��܂� |
 |
 |
|
�@��T6��26���i���j����A������m�点�����uSDG���v�ƌ��ѕt�������j�Z�t������A��������ψ�����S�ƂȂ��Ă��Ă��܂��B���̓o�Z���ԂɁA�e�ψ����5�E6�N�����A�����̒S�����ɕ�����Ăъ|���Ă��܂��B
�@���N�̖ڕW�́A���z�ł͂Ȃ��u190�l�̐l�����������Ă��炤�v�������ł��B��l�ɂ��ꖇ�̃V�[�����A��m���̕\�ɓ\���Ă��܂��B3���ڂ��߂��A������116�l�܂ŗ��܂����B�q�ǂ������́u�V�[����������Ƃ��ꂵ���v�Ƙb���Ă��܂����B
�@�ŏI����7��3���i���j�܂ŁA�c��2���ԁB�ڕW���B�̂��߂Ɂu�݂�ȂŐ�����������낤�B�v�Ǝq�ǂ������͘b���Ă��܂����B�݂�Ȃ̗͂ŒB���ł���Ƃ����ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N6��29���i���j |
| 2�N���A�U���K�j�̐��b��ώ@�𑱂��Ă��܂� |
 |
 |
|
�@2�N���́A�����Ȃ̊w�K�ŕ߂܂����U���K�j��S�̐��b���A�������Ă��܂��B�ǂ��ƂɁA���������̐��b����U���K�j�Ȃǂ̐��ւ��₦���������Ă��܂��B
�@�����āA�����́A���������̐��b���Ă��鐶�������悭���āA�G�ɕ`���Ă��܂����B�u�傫�Ȃ͂��݂̑��ɂ��A�����ȑ��������ς������B�v�u�����ۂ̂Ƃ���́A�ׂ����Ȃ���悤�ɂȂ��Ă���ˁv�c�ȂǁA��������̔���������܂����B
�@�q�ǂ������́A���b�𑱂��Ă��āA�u�Z�݂������ɍ���悤�ɂȂ��Ă����v�u���̗ʂ͂����������ꂭ�炢���ȁv�ƌ����āA�U���K�j�ɂƂ��ĉ߂����₷����������悤�ɂȂ��Ă��܂����B���ꂩ��A����ɐ������������ώ@���A�������܂Ƃ߁A�������|�X�^�[���d�グ��\��ł��B
|
|
|
| 2020�N6��26���i���j |
| 6�N���A���j�Z�t����̃|�X�^�[�Z�b�V���������܂��� |
 |
 |
|
�@6�N���́A�����6��25���i�j�ɁA����Ƒ����I�Ȋw�K�̈�Ƃ��āA��������n�܂������j�Z�t����ɂ��ă|�X�^�[�Z�b�V���������܂����B���j�Z�t����̈Ӌ`���A���܂Ŋw��ł���SDG���i�����\�ȊJ���ڕW�̎Љ�j�ƌ��ѕt���āA�������܂����B
�@�u���E�ɂ́A�����������č����w�Z�ɍs���Ȃ��q�ǂ��������A�Z���l���c�v�u�D���ȂǁA���ꂢ�Ȑ������߂Ȃ��q�ǂ����A���E�ɂ́����l�c�v���ꂼ��̊w�N�̋����⋳�����ɂ́A�S����3�`4�l�̃O���[�v���A����̃|�X�^�[�������Đ������܂����B�������p�ӂ�����A���S�����߂��肵�āA1�`5�N����������₷���悤�ɍH�v���Ă��܂����B
�@�I�������A6�N���̎q�ǂ������́A�u�����Ă���q�ǂ����������������B�Ƒ��ɂ����͂��Ă��炨���Ǝv���B�v�u�P�N���ɓ`���邽�߂ɁA������₷�����t�ɂ���̂���������B�P�N������������ƕ����Ă���Ă��ꂵ�������B�v�ƁA���z�▾������̕���ɂ��Ęb���Ă��܂����B�w�K���Ă������Ƃ�������̊����ɂ��Ȃ���A�q�ǂ������ɂƂ��ėL�Ӌ`�Ȋ����ɂȂ����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N6��25���i�j |
| 4�N���A�������|�H������w���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@4�N���́A���ƂƂ���6��23���i�j�ɁA�Љ�ȁu���݂͂ǂ��ցH�v�̊w�K�ŁA�������|�H��ɍs���Ă��܂����B
�@�ŏ��ɁA�q�ǂ������́A�����̕��̐���������A���O�ɍl��������Ȃǂ������肵�Đ��|�H��̊T�v�ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł��܂����B���̌�A���ۂɍH������ē����Ă��������܂����B�u��������̔R���邲�݂̑܂��A�傫�ȃs�b�g�ɎR�ɂȂ��Ă���I�v�u�R���s���[�^���g���āA24���ԔR�₵�����Ă���̂��v�c�Ƃ��̋K�͂̑傫���ɋ����܂����B
�@�A���Ă��Ă���A�q�ǂ������́A�u�������|�H��݂͂�Ȃ��K���ɂ���ꏊ�v�u���R�ɂ₳�����ꏊ�v�u�����Ȃ��C���[�W�����������ǁA�ƂĂ����ꂢ�ȏꏊ���Ǝv�����v�Ɛ��|�H��ɑ���C���[�W��ς��܂����B���ꂩ��A����Ƀ��T�C�N���ɂ��Ē��ׂĂ����܂��B
|
|
|
| 2020�N6��24���i���j |
| 3�N���A�Ό�������ɐ��������� |
 |
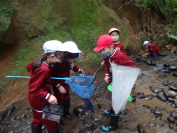 |
|
�@���6��24���i�j�ɁA3�N���́A�����I�Ȋw�K�̎��Ԃ̈�Ƃ��āA�ܔV���̏�ɂ��鐅��ɂǂ�ȓ��A�������邩���ׂɍs���܂����B��N�ł��ƁA�H��PTA�w�N�s���Ƃ��Ă��e�q�Ő���ɍs���̂ł����A���N�x�͐V�^�R���i�̊W�ŁA�����͂Q��Ƃ������I�Ȋw�K�̎��Ԃōs���܂��B
�@�u����ɂ͂������g���{�Ȃǂ�������̐������������B�v�q�ǂ������́A�S���̐��i���c��̕��X����A���ǂ�ȏꏊ�łǂ�ȓ��A�������邩����������A���������ŒT���n�߂܂����B�u�����A�I�K�G���̗�����������v�u�T���K�j���̉��ɂ�����B���O�̕�����Ȃ��c���݂����Ȑ���������������B�v�u�o���C�`�S��h�N�_�~����������B�h�N�_�~�͗t�������������B�v�c�ȂǁA��������̔���������܂����B
�@�q�ǂ������́A�w�Z�ɋA��ƁA�u����͎��R�L�����Y��ȂƂ��낾�����v�u�m��Ȃ�����m�ꂽ�菉�߂ăT���K�j��߂܂���ꂽ�肵�Ă悩�����v�u���D���ɂȂ����v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B���ꂩ�炳��ɁA���������߂����A���ׂāA�w�K��[�߂Ă����܂��B
|
|
|
| 2020�N6��22���i���j |
| 4�N���A�{��ɐ��������i�T���j |
 |
 |
|
�@��T5��19���i���j�ɁA4�N���͑����w�K�̊w�K�̈�Ƃ��āA������Ɛ{��̍����n�_�ɍs���Ă��܂����B
�@�u�㗬�ł́A�T���K�j�E���S�ȂǁA���ꂢ�Ȑ�ɏZ�ސ�������������B�v�u�ł��A�����Ȃ���ɂ��ސ�������������v�u������͂��ꂢ�ʼn�����I�v�c���܂Ŏ������2��T���ɍs���A���ꂢ���ɂ���ďZ�ސ��������Ⴄ���ƂɋC�t�����q�ǂ������B������̉����ɂ͂ǂ�Ȑ����������邩���ׂɍs���܂����B�{��Ƃ̍����n�_���ӂ̌��\�[�����̒��ŁA�U���K�j��I�C�J���Ȃǂ����͂��ĕ߂܂��܂����B����ɁA�{��ɂ́A�i�}�Y�����������āA�q�ǂ������͕K���ɑ傫�ȋ��e��ǂ������Ă��܂����B
�@�q�ǂ������́A�w�Z�ɋA���Ă��Ă���u�������������Ă����v�u������Ə�����������Ă��Ȃ��̂ɁA�Z�ސ��������������ĕs�v�c�������v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B���ꂩ��q�ǂ������́A����ɉ����̐M�Z��ׂĂ����\��ł��B�@�@�@�@
|
|
|
| 2020�N6��18���i�j |
| 1�N���Ƃ��������悤�I���悭���悤�I�L�����y�[�� |
 |
 |
|
�@���6�^17�i���j����A���������ψ����Ấu1�N���Ƃ��������悤�I���悭���悤�I�L�����[���v���n�܂�܂����B��������20���x�݂̎��Ԃ��g���āA1�N���Ƒ��̊w�N��1���𗬂����Ă��܂��B
�@�@���݂��Ɂu���͂悤�������܂��i����ɂ��́j�B�v�Ƃ���������B�A�u�킽���̖��O�́Z�Z�ł��B���O�������Ă��������B�v�Ƌ��������B�B���������āA�������l����u�킽���̍D���Ȃ��Ƃ́����ł��B��������̂����Ȃ��Ƃ͉��ł����B�v�ƏЉ�����B�C�݂��Ɂu��낵���ˁB�v�̂��ƁA���̊w�N�̎q�́A1�N���̑䎆�ɃV�[����\���Ă�����B�i���̌�A�����o�[�`�F���W�I�j�Ƃ�������ōs���܂����B���w�N�̎q�ǂ������́A�G�����đΉ����Ă���Ă��܂����B�������p�ł��B
�@1�N���̎q�ǂ������́A�u��������̐l�Ƙb���āA�V�[�������炦���B�v�Ƙb���Ă��܂��B��Â��Ă��邠�������ψ���̎q�ǂ��������u1�N���ƂQ�`6�N�����Ί�ł��������āA�𗬂��邱�Ƃ��ł��Ă悩�����B�v�ƌ����Ă��܂����B�����������𑝂₵�āA�S�Z�̎q�ǂ�����������ɐe�����Ȃ��Ă������Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N6��17���i���j |
| 2�N���A�U���K�j��߂܂��ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@���6�^16�i�j�ɁA�Q�N���́A�����ȁu���̐������́v�̊w�K�ŁA�������H�̋߂��ɃU���K�j��߂�ɍs���Ă��܂����B�O�̎��ԂɁA�߂܂���̂ɂ͂ǂ�ȕ��@�����邩�l���A�����ŕ߂܂��铹����������Ă����܂����B
�@�q�ǂ������́A����ɒ����ƁA�����̃y�b�g�{�g���ō�����d�|����ԂȂǂ��g���āA�U���K�j��T���܂����B�u�U���K�j�́A����Â��Ƃ���ɂ���B�v�u�v����������B
�v�ƁA�F�B�Ƒ��k���Ȃ���`�������W���܂����B�w�Z�ɋA�鍠�ɂ́A100�C���U���K�j���߂܂����̂ŁA�����ȏ�����Ė߂�܂����B
�@�w�Z�ɒ�������A�̈�ّO�̘L���Ɏ���Ă����U���K�j�𐅑��ɓ���ĕ��ׂ���A���̒��̗l�q���m���ɏ����ē\�����肵�܂����B�q�ǂ������́u�U���K�j�͗͋��������B�v�u���������͂悭���Ȃ��Ǝ����Ă����ꂿ�Ⴄ�B�v�@�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B���ꂩ��A���������ώ@���Ȃ���Z�݂�������Ă����܂��B
|
|
|
| 2020�N6��16���i�j |
| 3�N���A���є��^�������Ă��܂� |
 |
 |
|
�@3�N���́A�̈�̊w�K�Ő�T���璵�є��^�����n�߂Ă��܂��B�������Еt�����A�ǂ��Ƃɋ��͂��Ď�ۂ悭�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@����́A�J�r���т����ł͂Ȃ��A�u���яオ�蒵�щ���v�̋Z�ɂ����g�ݎn�߂܂����B�����āA������˂��Ƃ������������E�p���⒅�n�������������サ�Ȃ���A�A�h�o�C�X�����݂��ɂ�����ė��K���܂����B
�@�q���������́u��������ɒ��������肭���ׂ��v�u���͂����Ɛ��������Ē��т����v�ƁA�b���Ă��܂����B���ꂩ����A��l��l���A���܂łł��Ȃ������Z�ɂǂ�ǂ�`�������W���Ă����ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N6��15���i���j |
| 1�N���A�p��ł̂��������w�K���܂��� |
 |
 |
|
�@1�N���́A��T�O���ꊈ���̊w�K�ŁA�o��������̂������̎d������K���܂����B
�@�܂��A�����̋C������̗̂l�q��\���A���낢��ȉp��̌��t���w�т܂����B�u���C��fine�B.���Ȃ��ւ����͂�ungry�B������hot�c�v�����̋C������̗̂l�q��\�����낢��Ȍ��t���K���܂����B�����āA�uHello.�v�uHello.�v�uHow are you?�v�uI'm �Z�Z.And
you?�v�c�ƁA�o��������̉�b�̗������K���܂����B�����āA�Ō�́A���낢��Ȑl�ƃy�A�����A��b�̗��K���y���݂Ȃ��炵�܂����B
�@�q�ǂ������́A�u�T���搶�ɉ�Ċ����������B�v�u�O������Ċy�����ˁB�v�Ƙb���Ă��܂����B���ꂩ����������K���āA���������p��łł���悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N6��11���i�j |
| 2�N���A�G�u���������̒��v��`���n�߂܂��� |
 |
 |
|
�@2�N���́A���}�H�u�Ђ݂̂��܂��v�̊w�K�ŁA�G��`���Ă��܂��B��������Ē����牽����яo�����A��l��l���z���������̂��|���L�[�ƊG��ŕ`���܂����B
�@���̊k�͉�p����蔲���č��A�͗l��`�����݂܂����B���̗����炽������̓����⋛�A���̉ƁX�A�F���̐��X�ȂǁA�����̃C���[�W�������̂���яo���Ă��܂��B�����āA�������������q�ǂ������́A�E�̎ʐ^�̂悤�ɁA������m���ɒc�̍�i�u���������̒��v��`���n�߂܂����B��l��l���A�����̉Ƃ�`���Ă��܂��B
�@�q�ǂ������́A�u�����̐F�͂���ŁA�ǂ͂���Ȋ������ȁv�u�Z�Z����̂��Ƃł����ˁv�Ɗy�������ɘb���Ă��܂����B���~�ɂȂ����ЊL�܂�͑�ώc�O�ł����A�G�̒��ő傫�ȉԉ�ł��グ�悤�Ƙb���Ă��܂��B�H�Ɍ�������2�N���͏�����i�߂Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N6��10���i���j |
| 4�N���A������̐��������ׂ����Ă��܂� |
 |
 |
|
�@4�N���́A��T6��4���i�j��2��ڂ̎�����̒T���ɍs���Ă��܂����B����́A�ƂĂ��V�C�Ɍb�܂ꂽ���A�O���������ɏ㗬�̏ꏊ�ƁA�ЊL���w�Z�̃O���E���h�̘e�̏ꏊ��2�����ŁA��������T���܂����B
�@�u�㗬�ɍs���قǐ������ꂢ�B�v�u�O���E���h�̘e�͂قƂ�ǃR���N���[�g�ł������Ă��邯�ǁA�㗬�͂قƂ�ǃR���N���[�g���Ȃ��B�v�q�ǂ������́A��������T���Ȃ����̗l�q�̈Ⴂ�ɂ��C�Â��܂����B
�@�����āA�A���Ă��Ă���U��Ԃ������ƁA�u�㗬�ɃT���K�j��������������A���ꂢ�Ȑ삾�v�u�O���E���h�O�́A�߂��ɉƂ�Ԃ��ʂ邩�炫���Ȃ��v�ȂǁA�㗬�ƃO���E���h�̐������̈Ⴂ�ɂ��C�Â��n�߂܂����B���T�͂���ɁA���̂��ꂢ��������̊W�ɂ��ڂ������Ă����܂��B�@�@�@�@�@�@�@
|
|
|
| 2020�N6��8���i���j |
| 5�N���A�j���A�[�g������Ă��܂��B |
 |
 |
|
�@5�N���́A��T����}�H�́u�����オ�ꃏ�C���[�A�[�g�v�̊w�K�ŁA�j����[�����g���Đ��슈�����s���Ă��܂��B����ނ��̐F�Ƃ�ǂ�̐j�����A�y���`�ŋȂ���������肵�č��܂��B
�@�q�ǂ������́A�u�v���������̂⓮����\�����v�Ƃ����e�[�}����C���[�W�������̂��A�F�̂����j�����g���ė��̓I�ɍ���Ă��܂��B�܂��A�ǂ�ȍ�i����낤���\�z���@���ɁA���ۂɐj�����Ȃ�����A�g�ݍ��킹���肵�Ȃ���A������F���l�A�[�C�����c�ȂǁA�����̔��z�������̂�3�����ŕ\���Ă����܂��B
�@�u���M�ɐj���������ƁA�j�������邭��ɂȂ��Ėʔ����v�u�ǂ������痧���オ��낤�v�ȂǁA���s������J��Ԃ��Ȃ���A�q�ǂ������͂��낢��Ȋ��z�������܂����B���T���A���R�Ɍ`��ς�����f�ނ����Ȃ���A�����̍�i�����������Ă������Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N6��5���i���j |
| 6�N���A�������j�����قɌ��w�ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@6�N���́A���4���i�j�ɁA�����s���ɂ��錧�����j�����قɍs���Ă��܂����B�Љ�Ȃ̓ꕶ����ƏC�w���s�ɍs�����n�ɂ��āA���Ɋw��ŗ��܂����B
�@�q�ǂ������́A���N�x������{�����@�Ȃǂ̐����E���ی𗬂̊w�K�����Ă���A���j�w�K�ɓ����Ă��܂��B�����ŁA����͒��z�n���ɂ�������o�y����{���̉Ή��^�y��������Ă�����������A�ꕶ�l�̐����ɂ��ăW�I���}�����Ȃ�����������Ă�������肵�܂����B�܂��A�C�w���s�ŖK��鍲�n���́A���R�╶��l�`�Ȃǂ̗��j�ɂ��Ă������Ă��������܂����B
�@�q�ǂ������̊��z�ɂ́A�u�ꕶ�l�̒m�b���������v�u���n���R�ɑ��������Ă݂����v�Ƃ��������̂�����܂����B���Ƃ̕��X�̂��b��A�����ɐG��邱�Ƃ��ł��Ă悩�����ł��B
|
|
|
| 2020�N6��4���i�j |
| ���N�x�A���߂Ă̑̈�قł̑S�Z��������{�I |
 |
 |
|
�@�����A���N�x���߂đS�Z������������킹�Ă̑S�Z������A��^����ōs���܂����B�S���ً̋}���Ԑ錾�̉������āA���܂ł̐�����`��ς��A�Ԋu���J���Ċ��C���悭���čs���܂����B
�@�����̑S�Z����́A��2���u�����̗͂�L�����@�`�����̂悳�����āA�݂�Ȃ̂��߂ɖ������͂������`�v���āA�Z���u�b����w����C�̑S�Z�w���A���T����n�܂錒�N�X�e�b�v�A�b�v�T�Ԃ̎w���ł����B
�@�u�����̂����Ă���͂��A����t�o���Ă����Ȃ��ƂɎ��g��ł����܂��傤�B�����āA�݂�Ȃ̂��߂ɐ������Ă����܂��傤�B�v�u�����Q��E�����N����E���f�B�A�R���g���[���Ɏ��g��ŁA�w�Z�ł����ɁE�����Ɋ撣��͂�{���Ă����܂��傤�B�v�@�c�Ƃ̘b������܂����B�u�f���ȐS�E�v�����̐S�E�܂�Ȃ��S�v�ŁA�����̂悳��͂�����ɐL���A���̐l�̖��ɗ��Ă�悤�ɂȂ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N6��3���i���j |
| 3�N���A3��ނ̎���܂��܂��� |
 |
 |
|
�@�����6��2���i�j�ɁA3�N���́A���ȁu�A������Ă悤�v�̊w�K�ŁA3��ނ̐A���̎�܂������܂����B�q�ǂ������́A�ȑO�A���ዾ�Ŏ�̊ώ@�����āA��ނ��Ƃɑ傫����`�E�F���Ⴄ���ƂɋC�t���܂����B
�@�u�ŏ��ɁA�q�}�����̎���A�v�[���e�ɐA���܂��B�z�E�Z���J�ƃA�T�K�I�́A��ł܂��Ⴄ�ꏊ�ɐA�����B�v����́A�����ŏ��ԂɎ��I��ŁA�v�[���e�ƑO��̉Ԓd�ɐA���Ă����܂����B�A�����߂��ɁA�����̖��O����������ڈ�ɒu���܂����B�����āA�A������ɂ͂����Ղ萅���グ�܂����B
�@�A���I�������A�q�ǂ������́A�u�������ȃq�}�����ɂȂ�Ƃ����ȁv�u�����Ɖ肪�o�邩�ȁv�Ƙb���Ă��܂����B���ꂩ��肪�o�����Ƃ́A���ꂼ��̗t��ԁE�s�̓����Ȃǂ����ׂĂ����\��ł��B
|
|
|
| 2020�N6��2���i�j |
| 1�N���A�T�C������n�܂�܂����I |
 |
 |
|
�@���6��1���i���j����A1�N���́A�����Ȃ̈�Ƃ��āu�T�C������v���n�߂܂����B�Z���̋��E���ɁA��������b�������āA���ȏЉ��������A�����̊撣���Ă��邱�ƂȂǂ��Љ�������肵�܂��B�����āA�J�[�h�ɃT�C�������炢�܂��B
�@��N�ł��ƈ��������̂ł����A�����͂�����Ɓc�B����������Ȃǂւ̓�����Ȃǂ����K���Ă���A���x�݂Ȃǂ̋x�ݎ��Ԃ��g���Ċ������Ă��܂��B1���ŁA6�E7�l�̋��E���̃T�C�����W�߂��h����́h�����܂���B
�@�q�ǂ������́A�����ɖ߂��Ă���Ɓu��������̐搶�Ƃ��b���ł����B�v�u�ْ��������ǁA���������B�v�c�ȂǂƁA�b���Ă��܂��B�ǂ�ǂ�����b�������A��������̐l�ƒm�荇���ɂȂ��ƁA�����ł��ˁB
|
|
|
| 2020�N6��1���i���j |
| 6�N���A�Ƃł̒������K�Ɏ��g��ł��܂� |
 |
 |
|
�@���A6�N���́A�ƒ�ȁu���H���猒�N��1���̐������v�̊w�K�ŁA�h�{���l�����������������ō���悤�ɂȂ�w�K�����Ă��܂��B�����A�V�^�R���i�E�C���X�̊W�ŁA�w�Z�ł͂������炭�������K���ł��܂���B�����ŁA�Ƒ��ɗ���������ĐH�ׂĂ��炤���Ƃ��A�h��Ƃ��ďo�Ă��܂��B
�@�h��̊��Ԃ�1�T�ԂقǂŁA�q�ǂ������́A�J�[�h�ɗ����̎ʐ^�⊴�z�Ȃǂ����āA��o���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B��̎ʐ^�́A�������̓y�j�E���j�ɁA�h��Ɏ��g�q�ǂ������̃J�[�h�ł��B�����������ɂł��Ă��܂��ˁB
�@�ق��̎q�ǂ��́u���Ƃ̕��̈ꌾ�v�ɂ��A�u�������N���āA��l�Ŋ撣���č���Ă���܂����B�i�����j���͂��傤�ǂ悢�������ł����B�ƂĂ��������������ł��B�����A���肪�Ƃ��I���ꂳ��A���ꂵ��������B�v�ƁA�����Ă���܂����B���Ƒ��̂����́A��ς��肪�Ƃ��������܂��B�������낵�����肢���܂��B
|
|
|
| 2020�N5��29���i���j |
| 1�N���A�A�T�K�I�̐��b��ώ@���撣���Ă��܂� |
 |
 |
|
�@1�N���́A�T���P�W���i���j�ɃA�T�K�I�̎��A���܂����B�u�����肪�o�āA�傫���Ȃ��ĂˁB�v�ƁA�����A�����h�Z���������ɒu������A����ɏo�ăA�T�K�I�ɐ��������Ă��܂��B
�@�����āA���T�A�T�K�I�̉肪�o�Ă��܂����B��������Ȃ̎��ԂɁA�q�ǂ������́A�o�Ă�����̊ώ@�����܂����B�u�肪�A3���o�Ă�����v�u�t���ς̌`�́A�ۂ��ˁB�v�u���̉�������o��Ƃ����ȁB�v�Ȃǂ̋C�t�������܂�܂����B���̗l�q���A���J�Ɋώ@�J�[�h�ɂ����āA�F���h��܂����B
�@1�N�����̘L���ɂ́A���X�́u���������̂��v�L�^���\���Ă���܂��B�q�ǂ������Ɠ������A�A�T�K�I���ǂ�ǂ�傫���������Ă������Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N5��27���i���j |
| 2�N���A��̕c��A���܂��� |
 |
 |
|
�@���26���i�j�ɁA2�N���͐����ȁu�킽�������̂₳�������v�̊w�K�Ŗ�̕c��A���܂����B���N�̔��̏ꏊ�́A����蓙�Ǘ������₷���悤�ɁA�k�Z�ɂƖk�^����̊Ԃł��B
�@�q�ǂ������́A�~�j�g�}�g�₫�イ���i�X�ȂǁA�����̊�]������̕c�����܂����B�����āA���̎���̑����Ă���A�|�b�g�����錊���@���Ă���A���J�ɐA���܂����B�q�ǂ������́A�u��̎�ނɂ���āA�t���ς̌`��F���Ⴄ�ˁv�u���̐[���͂��ꂭ�炢���ȁv�c�Ƃ�������������܂����B
�@�A������A�u�����������Ȃ���v�u�傫�Ȏ����ł���悤�ɂ����b���Ȃ��Ɓv�c�ƁA�肢���������q�ǂ������B���ꂩ�炸���ƁA�����̖�̐��b���A����������Ă������Ă���邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N5��26���i�j |
| 5�N���A�����̎��� |
 |
 |
|
�@�����́A5�N���̓����u20���Ԃ̏o�����v�Ƃ����w�K�ɂ��Ă��`�����܂��B���̋��ނ́A�����{��k�Ђ̎��A2�l�̏���������Ă����d�Ԃ̏�q�̎��ۂɂ��������b�ł��B
�@�u�Ôg����A��l�ł������̖������������A�Ǝv�����Ǝv���v�u���̂܂܂����ɂ���ƁA�Ôg�Ɉ��ݍ��܂�Ă��܂��B���̂Ă����Ȃ��I�v�ƁA5�N���̎q�ǂ������́A�댯���ڂ݂����̐l����������悤�Ƃ��������̎v�����l���܂����B�����āA���̌�u�����̖����댯�Ȃ̂ɁA�����Ȃ�����������������悤�Ƃ��鏄������̍s���͂͂������I�v�u�����̔��f�̂������Ŗ����~�����Ƃ��ł����I�v�ƁA�Ȃ���������̖����~�����Ƃ��ł����̂��A���̗v����F�B�ƌ𗬂��܂����B
�@�������ł́A�u������������c�ǂ�����H�ǂ��l����H�v �ƁA�������ƂƂ��ĔY�݁A�F�B�̈ӌ��Ǝ����̈ӌ��Ƃ��ׂ邱�Ƃ��A���ɑ厖�ɂ��Ă��܂��B�����āA���ۂ̂��낢��ȏ�ʂŁA�����̓��ōl���s���ł���q�ǂ��ɂȂ��ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N5��25���i���j |
| 3�N���A�y�n�̗��p�����ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@3�N���́A�Љ�ȁu�킽�������̂܂��Ǝs�v�̊w�K�ŁA�ЊL���w�Z���ӂ̓y�n���ǂ̂悤�Ɏg���Ă��邩���A���ɕ����Č��w�ɍs�����ׂĂ��܂��B��T��22���i���j���A4���ɕЊL���w�Z�̉��܂ŏオ���Ē������܂����B
�@�u���̕ӂ�̎R�̎Ζʂ́A����т��L�����Ă���ˁB�v�u���̑O���ɍs�������c�̕ӂ�́A����œc��ڂ��L�����Ă����B�v���ۂɏ�ɍs���Ē��̗l�q���ώ@����ƁA�ЊL���̒n�`�Ɠy�n�̎g�����̂Ȃ��肪�����Ă��܂����B
�@�q�ǂ������́A���w��ʂ��āu�w�Z�̗��̂ق��͍₪�}���ˁv�u�ЊL�̓����͕���Ő����͍₾�ˁv�ƁA���z��U��Ԃ�Ȃǂ������܂����B����́A����ɏ���J�s�S�̂ɂ�������L���Ă����܂��B�@�@�@
|
|
|
| 2020�N5��22���i���j |
| 4�N���A������T���ɍs���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@���21���i�j�ɁA4�N���́A�����I�Ȋw�K�̎��ԁu������͂ǂ��ցv�̊w�K�ŁA�w�Z�̉��𗬂�Ă��������̏㗬�֒T���ɍs���Ă��܂����B������Ɣ������V��ł������A���C��4�N���͂���Ƃ������A�Ԃ�o�P�c��Ў�ɏo�����܂����B
�@�ЊL���w�Z�̂���������̂�����Ő�ɓ���ƁA�u�w�Z�̋߂��̗l�q�ƈ���āA�R���N���[�g�Ōł߂ĂȂ��ȁB�v�u�傫�Ȑ�D�������āA����������������B�v�@�ƁA�q�ǂ������͋C�Â��܂����B�����āA���ۂɎ��������Ń��_�J��A�u���n���A��K�j��h�W���E�Ȃǂ�߂܂��邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�w�Z�ɖ߂��Ă��Ă���u�߂��ɂ���Ȃɑ傫�ȋ�������Ƃ͎v��Ȃ������v�u�������͉���H�ׂĂ���̂��낤�v�Ƃ��������z��������܂����B���ꂩ��A����ɕЊL���⏬��J�s�̐��ӂ̊��ɂ��Ē��ׂĂ����܂��B
|
|
|
| 2020�N5��21���i�j |
| �y���݂Ȃ���O���ꊈ�������Ă��܂� |
 |
 |
|
�@���N�x�A3�E4�N����1�N�ԂŊO���ꊈ����35���ԁA1�E2�N����10���Ԓ��x���{����v��ł��B���E���ƃl�C�e�B�u�̃T���搶�i�A�����J���O���o�g�j�ƂŁA�w�K��i�߂Ă����܂��B
�@�����2�N���̊w�K�ł́A�u�o��������̂������̎d���ƁA�����̑̒��̌������v����K���Ă��܂����B�q�ǂ������́A�uhappy�E hot�E fine�E cold�c �v�Ȃǂ̌��t���g���Ȃ���A��������̗F�B�ƃR�~���j�P�[�V�������y����ł��܂����B
�@�E�̎ʐ^�́A3�N���̊O���ꊈ���ł��B���E���̂��낢��ȍ��̂������̌��t���W�F�X�`���[�����Ċw�т܂����B���ɂ��A�u�L�[���[�h�Q�[���v��`�����c�ȂǂŁA�p��ɐe���݂Ȃ���y����ł��܂����B
�@�O����ɒ�R�����Ȃ��q�ǂ������ɁA����Ă����ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N5��19���i�j |
| �H�v���Ȃ��特�y�̎��ƂɎ��g��ł��܂� |
 |
 |
|
�@�����́A���y�̎��Ƃɂ��Ă��`�����܂��B�ȑO�A���{�̐V�^�R���i�W�̃j���[�X�ŁA�����T�[�N���ŃN���X�^�[�����������Ƃ������̂�����܂����B���̂��߁A���⌧����̒ʒm�ŁA���y�ɂ����Ă����t�̔�U�����O�����u������Ԃ▧��Ԃł̉̏��w����g�̂̐ڐG�������v���̌v��ύX�����߂��Ă��܂��B
�@�����ŁA���Z�ł�1�w���ɂ����ẮA�����ł̍������K��[�R�[�_�[�E���Ճn�[���j�J�̗��K�����Ȃ��ŁA���Ƃ�i�߂Ă��܂��B���̎ʐ^�́A4�N�����蔏�q�Ń��Y���V�т����Ă���Ƃ���ł��B����ɁA�蔏�q�Ń��Y���̋Ȃ��ō���āA�݂�ȂŌq���ł����܂��B�܂��A�E�̎ʐ^�́A6�N����PC���[���ʼn��y�����Ă���l�q�ł��B�u�V���K�[�\���O���C�^�[�v�Ƃ������y�\�t�g���g���āA�u�F�B�Ȃv�ɔ��t��t���悤�Ƃ��Ă��܂��B
�@���ꂼ��A���̊��E�����̒��ŁA�ǂ�Ȏ��Ƃ��ł��邩�A��T��Ői�߂Ă���Ƃ���ł��B���q����ɁA�ǂ�ȉ��y�����Ă��邩�A�����Ă݂Ă��������B
|
|
|
| 2020�N5��18���i���j |
| �w�Z�̒��̌f���� |
 |
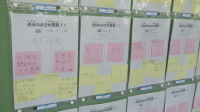 |
|
�@�ً}���Ԑ錾�̈ꕔ����������Ă��珉�߂Ă̏T���́A�S���Ől�o�����������Ƃ���������܂����B������܂˂��킯�ł͂Ȃ��ł��傤���A������1������ɁA�w�Z�̋߂��ŃC�m�V�V�̖ڌ������܂����B���̂��߁A�w�Z���������ƂƂ��ɁA���S����ɍl���ČߑO���͉����ł̊����ɐ�ւ��܂����B
�@���āA�����́A�Z���̌f�����̈ꕔ���Љ�܂��B���̎ʐ^�́A2�N���̋����ɂ������u�����Z�̌J��オ��v�̊w�K�f���ł��B�i�J��オ��̂P���A�������Y�ꂸ�ɏ������ƁB�\�̈ʂ̑����Z�̎��ɁA�J��オ��̂P��Y�ꂸ�ɑ������ƁA���|�C���g�B�j���̎ʐ^�́A5�N���́u�����̂悳�唭���I�I�v�̌f���ł��B�����̂悳��Ԃ̕tⳂɁA�F�B�̂悳�����F�̕tⳂɏ����ē\���Ă���܂����B�u���ȗL�p���v��L����悤�A�S�Z�ŔN�Ԃ�ʂ��Ď��g��ł����܂��B
�@���ꂼ��̊w�N�E�w���ŁA�q�ǂ������̐����̑��Ղ��c���Ă�����g���A���ꂩ����i�߂Ă����\��ł��B
|
|
|
| 2020�N5��15���i���j |
| �w�K�������A����O���ɏ���Ă��܂��� |
 |
 |
|
�@�����́A������Ƃɓ�����2���ڂɂȂ�܂����B�����39���ً̋}���Ԑ錾�̉������A�V�����ɂ����Ă��������Ɠ����܂߂���c���J�����悤�ł��B
�@���āA�e�w�N�ł́A�w�Z���ĊJ���A�����g��h�~�ɔz�����Ȃ�����Ƃ�i�߂Ă���Ƃ���ł��B�Ⴆ�A�̈�͂��炭�͉��O�̊����𒆐S�ɐi�߂Ă����܂��B���̎ʐ^�́A1�N�����T�O�����̃^�C�����v���Ă���Ƃ���ł��B��������ƂɁA�Ԕ������܂�܂��B
�@�܂��A���Ȃɂ����Ă��A���C�ɋC��t���Ȃ���A�u��̓I�őΘb�I�Ȑ[���w�сv�ɂȂ�������ɂ����g��ł��܂��B�E�̎ʐ^�́A6�N���́u���̂̔R�����Ƌ�C�v�̊w�K�̗l�q�ł��B�C�̌��m�ǂ��g���āA��C�̑g���̕ω��ׂĂ��܂����B6�N���̎q�ǂ������́A�u����ς�_�f���������v�u��_���Y�f��������Ɖ͔R���Ȃ��v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B
�@���ꂩ����A�u�O���v�ɋC��t���Ȃ�����[�������w�K�ɂȂ�悤�A���g��ł��������Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N5��14���i�j |
| �������狋�H���ĊJ���܂��� |
 |
 |
�@�����̌ߌ�ɁA�ً}���Ԑ錾��39���ɂ����ĉ��������\��ł��B���邢�������łĂ��Ċ���������ł��B
�@���āA���m�点���Ă����ʂ�A�������狋�H���ĊJ����܂����B�q�ǂ��������A�v���Ԃ�̋��H�Ńj�R�j�R�Ί�ł����B�c�O�Ȃ���A�R���i�E�B���X�̊W�ŁA����O�Ɍ����Ă��܂肨����ׂ肹���ɐH�ׂ邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�ł��A���j���[�́A�q�ǂ������ɂ��l�C�́u���Ȃ��g���p���v�ƁA�`�L���T���_�E���{���p�X�^�X�[�v�E�A�Z�����[���[�ł��B
���H���ŃJ���b�Ɨg�����ĕ��p���ɁA������ƊÂ߂̂��ȕ����܂Ԃ���Ă��Ă������������ł��B
�@�q�ǂ��������A�u�v���Ԃ�̋��H�ł��ꂵ���I�v�Ɗ��z�������Ă��܂������A�E�����u���H�̗L��݂��A�����͐g�ɟ��݂܂����I�v�Ƙb���Ă��܂����B�Ȃ��Ȃ��ď��߂ċC�t�����Ƃ���������Ȃ��A�Ǝv�������ł��ˁB�@�@�@ |
|
|
| 2020�N5��13���i���j |
| ���Ƃ��������i�߂Ă��܂� |
 |
 |
|
�@�Վ��x�Z��Ɏ��Ƃ��ĊJ���āA������3���ڂɂȂ�܂����B�q�ǂ��������A3���̎��Ƃ̒��ŁA���������x�݂���w�Z�����ɓ��Ƒ̂�����������Ă����悤�ł��B
�@���ꂼ��̃N���X�ł́A�Վ��x�Z�̊Ԃ̏h�蓙���m�F������A�V�����w�K�ɂ������Ă��Ă��܂��B��̍��̎ʐ^�́A3�N�������Ȃ̎��Ԃɒ��ዾ���g���āA�q�}�����ƃz�E�Z���J�̎���ώ@���Ă���Ƃ���ł��B�܂��A�E�̎ʐ^�́A4�N�������ʂ̊w�K�ŁA�ѕM�Łu�r�v�Ƃ������������Ă���Ƃ���ł��B���̊w�N���A���ꂼ��w�K�ɐ^���Ɏ��g��ł���l�q���`����Ă��܂����B
�@��������́A���悢�拋�H���ĊJ���A����ʂ�5�E6���Ԗڂ܂Ŏ��Ƃ��s���܂��B�u����ʂ�v�̊w�Z�������A���ꂩ�炸���Ƒ����Ăق����ƐɊ���Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N4��24���i���j |
| 1�N���A2�N���Ɗw�Z�T���I |
 |
 |
|
�@���4��23���i�j�ɁA1�N����2�N���̂��Z���o����ƈꏏ�ɁA�w�Z�T�����s���܂����B�܂��n�߂ɁA�̈�ق�2�N���̑�\��������[�������������ɁA2�l1�g�܂���3�l1�g�ŃX�^�[�g���܂����B
�@2�N���̃��[�h�̂��ƁA����Ȃ��Ŋw�Z���̋���������܂��B�����āA�J�[�h�̒��̍s���������̗��ɁA�V�[����\��܂����B���̌�A1�N���́A2�N��������胁�_���ƒ���̎�E�_���X�̃v���[���g���Ƃ�܂����B
�@1�N���̎q�ǂ������́A�u�����ȋ����ɍs���Ă��ꂵ�������ł��B�v�Ƙb���Ă��܂����B�����āA2�N���̎q�ǂ��������u1�N�����j�R�j�R���Ă��āA�������ꂵ���Ȃ�܂����B�v�ƐU��Ԃ��Ă��܂����B
�@1�N�����}�����ł��܂���ł������A2�N���̊��}����C�������`����Ă悩�����ł��B
|
|
|
| 2020�N4��22���i���j |
| �O����ȁE�O���ꊈ���̎��Ƃ��n�܂�܂��� |
 |
 |
|
�@���N�x����A3�E4�N���̊O���ꊈ���A5�E6�N���̊O����Ȃ̎��Ƃ��{�i�I�Ɏn�܂�܂����B5�E6�N�̎��Ƃł́A�O�����ȋ����̒��V�搶���A�T2�Z���ċ����܂��B�܂��A���N�x���T���搶���AALT�Ƃ��đS�Z�̎q�ǂ������ɐڂ��Ă���Ă��܂��B
�@������5�N���̎��Ƃł́A�y���݂Ȃ��狳�ȏ��̊G�̒��ɉB��Ă���A���t�@�x�b�g��T������A�uWhat�@�Z�Zdo you like? I lile �����@�I�v���̂��ė��K������A�����āA�ǂ̒��ԂƓ`���������K�����܂����B�@
�@���Ƃ̍Ō�Ɏq�ǂ������́A�D���Ȃ��̂�搶�ɂ��炷��Ɠ`���邱�Ƃ��ł��܂����B���ꂩ����A�y���݂Ȃ���R�~���j�P�[�V�������Ă����ė~�����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N4��20���i���j |
| �^���Ɏ��g�A��1����P���I |
 |
 |
|
�@��T17���i���j��3���ɁA��1��̔��P�����s���܂����B���ꂼ��̋�������̔��o�H���m�F���邽�߁A�Ύ���z�肵�ăO���E���h�ɔ��܂����B
�@�ǂ̊w�N�����R�ƕ��сA���ʌ����������Ȃ����̗l�q�ł����B��������u��N�x�̔��ɂ����������ԂƔ�ׂ�ƁA30�b�قǑ����Ȃ�܂����I���h�ł����B�v�ƁA�q�ǂ������ւ̘b������܂����B����3�����́u���E���E���v�̓��e���A�q�ǂ������͂悭�o���Ă��܂����B
�@����A�u�����Ȃ��v�ɂ��āu�K�i�⋷���Ȃ�Ƃ���v�ŋC��t����K�v�������A�Ƙb���܂����B�q�ǂ������̎��ȍ̓_���S�����u90�_�E100�_�v���������̎p�����A���ꂩ��������Ƒ����Ăق����Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N4��17���i���j |
| �S�Z�i�����j������s���܂��� |
 |
 |
|
�@���16���i�j�ɁA�����ł̑S�Z������s���܂����B���e�́A3�E4�N���̑�\�����ɂ��߂��Ĕ��\�ƁA�����w����C����̎w���ł����B
�@�u�����̋��ȋ��Ȃ�^���ɂ��A���������ɂ�����đ��������v�u�͂����I�ƁA�w���x���t���悤�Ɍ��C�ɕԎ����������B�݂�Ȃ̂��߂ɁA�W�������撣�肽���v�ƁA�߂��Ă��Љ�Ă���܂����B�܂��A�����w����C�Ɓu���������ψ���v�̑�\����A�������܂߂Ă̂S�̃|�C���g�̐���������܂����B
�@��1���́A4��7���`5��25���u���ꏊ�Â���E�J�Â����i�߂悤�v�ł��B���Ԃ̖��O���o���A���[�������Ȃ���A�S�Z�݂̂�Ȃŋ��S�n�̂悢�w���E�w�Z�������Ă��������Ǝv���܂��B
|
|
|
| 2020�N4��15���i���j |
| ���瑪�蓙���n�܂�܂��� |
 |
 |
|
�@�������A���瑪��⎋�͌������n�܂�܂����B��N���w�N���Ƃ̎��ԂU���A�̈�قő҂��Ă��鎞�̊Ԋu�������čs���Ă��܂��B
�@1�N�����A�����6�N���ƃy�A�ʼn��܂����B���̊w�N�����������Č������Ă��܂��B�����̒��͌������A�ƂĂ��X���[�Y�Ɍ������i��ł��܂��B�S�����u�������g�̐�������тȂ�����A�ӎ����Đl�Ɛl�Ƃ̊Ԋu���J���āA�Â��ɑ҂��Ă���l�q���f���܂����B�v�Ƙb���Ă��܂����B
�@���낢��ȏ�ʂŁA�ƂĂ��悢�w�N�̃X�^�[�g����Ă��܂��B���ꂩ����A���ꂼ��̊w�K�ŗ͂�L���Ă���邱�Ƃł��傤�B
|
|
|
| 2020�N4��13���i���j |
| �����q�ǂ���Ɖ��Z�w�������{�I |
 |
 |
|
�@��T��10���i���j�ɁA�V1�N�����܂߂Ă̏��߂Ă̒����q�ǂ���Ɖ��Z�w�����s���܂����B
�@6�N����1�N�����}���ɍs���A���ꂼ��̒����q�ǂ���̋����Ɍ������܂����B��̒��ŁA1�N�������ȏЉ���ʂ�����܂����B��l��l���A�����̖��O��u��낵�����肢���܂��B�v���͂����茾���܂����B�㋉���������A�D�����������ڂ��Ă���Ă��܂����B
�@�����āA�������ւō��܂Ȃ��悤�ɁA�������Ƃɉ��Z�ǂŋA��܂����B�J�̒��ł������A�݂�Ȉ��S�ɉ��Z�ł��Ă悩�����ł��B
�@���݁A�t�̌�ʈ��S�^���̊��Ԃł��B���ꂩ��������ƁA���S�ɋC��t���ēo���Z�����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B
|
|
|
| 2020�N4��8���i���j |
| �����w�A���߂łƂ��������܂��I |
 |
 |
|
�@�{���A�O���E���h�̍������J�ɍ炫�ւ钆�A22���̐V�������ЊL���w�Z�ɓ��w���܂����B�����o�E�ݍZ���̎Q��͂���܂���ł������A�\��ʂ���w�������{�ł��܂����B��ς��ꂵ�����Ƃł��B
�@�V�����̌Ė��ł́A��l��l�������đ傫�Ȑ��ŕԎ������邱�Ƃ��ł��܂����B6�N���̎�����\���u�c�������玄���������������Ă��������B�݂�ȂŕЊL���w�Z�������w�Z�ɂ��Ă����܂��傤�v�ƁA���邭���X�Ƙb���Ă���܂����B�i�V�������A�����Ɩ�����������C�ɓo�Z���Ă���邱�Ƃł��傤�B�j
�@�w���w�����ł��A��������b�����Ƃ��ł����V�����̎q�ǂ������B���w���Řb�����u���悭�v�u�悭�����v�u�����Łv��3�̉Ԃ��A���ꂩ�����������炩���Ă����ė~�����Ǝv���܂��B�����w�A���߂łƂ��������܂����B
|
|
|
| 2020�N4��7���i�j |
| ��������P�w�����X�^�[�g���܂����I |
 |
 |
|
�@���J�̍����炫�ւ钆�A�q�ǂ������̖��邢�����A�v���Ԃ�ɍZ�ɒ��ɋ����n��܂����B���悢��A��������ߘa�Q�N�x�̂P�w�����X�^�[�g���܂����B
�@�����̐V�C���E�n�Ǝ��́A�e���r�����t���́u��������v�`���ōs���܂����B�W���̐V�C�̋��E���̏Љ��A�������ɍ��킹���u�߂��āv�̐ݒ�̘b���̌�A�{�싳�@���犴���Ǘ\�h�̘b������܂����B�P�w���̃X�^�[�g�ɓ�����A���Ȃ��E�L���Ȃ����߂ɋC�����邱�Ƃ��A���J�ɓ`���܂����B
�@�e�����ł́A�����ł̘b�����ƂɁA����ɋ�̓I�Ȏw�����s���܂����B�q�ǂ������́A�V�C�̐搶�����Ƃ̏o���A�v�X�̃O���E���h�ł̗F�B�Ƃ̗V�тɁA�ƂĂ����ꂵ�����ł����B���ꂩ����A���̏Ί炪�����悤�ɁA�݂�ȂŕЊL���w�Z��グ�Ă��������Ǝv���܂��B
|
|
|
|
|