| 2020年3月26日(木) |
| 祝卒業、カラフル学年! |
 |
 |
|
3月24日(火)に、名残り雪が時折舞う中、第73回卒業証書授与式を行うことができました。参加者は、卒業生と保護者の皆様、教職員で行いました。
一人一人が、大きな声で返事をし、堂々とした態度で卒業証書を受け取ることができました。また、呼びかけと合唱「最後のチャイム」によって、卒業生の思いが、参加者の皆さんの心に届けることができたと思います。
天候が回復し明るい日差しがさす中、グラウンドで祝砲の花火を、みんなで見上げました。カラフル学年31名は、立派に中学校に旅立つことができました。大変、ありがとうございました。
|
|
|
| 2020年3月9日(月) |
| 「六年生を送る会」を実施④ |
 |
 |
|
臨時休業に入ってから、今のところ子どもたちの病気・事故・事件等の連絡は入ってきておりません。これからも、臨時休業から春休みの期間を、有意義にそして無事に過ごして欲しいと願っています。
さて、「六年生を送る会」の第4弾です。今日は、教職員の出し物と卒業生の感想を紹介します。
教職員の出し物は、卒業生に送るキーワード「ワンチーム」「トライ」をもとにした、片貝小「オールブラックス」による「ハカ」です。寸劇とともに「これからも、何にでもトライして欲しい!」という思いを、卒業生に贈りました。
卒業生カラフル学年の子どもたちは、「どの学年も楽しい出し物だった」「全校のみんなにお祝いしてもらえて嬉しい」と感想を話していました。きっと、一人一人の卒業生にとって、小学校時代の大切な思い出になったのではないでしょうか。
|
|
|
| 2020年3月5日(木) |
| 「六年生を送る会」を実施③ |
 |
 |
|
「六年生を送る会」の第3弾です。今日は、卒業生と4年生の発表を紹介します。
卒業生は、劇とダンスで学校や在校生への感謝の気持ちを表現し、会場を盛り上げました。昔話をアレンジした楽しい劇を、芸達者たちが、工夫した衣装やダンスで表現しました。そして、卒業生がリードして全校で踊った「パプリカ」では、みんなの笑顔が弾けました。
4年生は、「くす玉割りと終わりの言葉」を担当しました。「ドラえもん」たちに扮装した代表が、劇をしながら卒業生への感謝の言葉を述べた後、いよいよくす玉割りです。くじ引きで決まった卒業生の代表たちがロープを引くと、見事にくす玉が割れ「カラフル学年ありがとう、中学校でもがんばって」のメッセージが開きました。
「おぉー!!」と、子どもたちは叫んでいました。くす玉がきれいに開いて、ほっとしました。(つづく)
|
|
|
| 2020年3月4日(水) |
| 「六年生を送る会」を実施② |
 |
 |
|
「六年生を送る会」の第2弾です。今日は、3年生と5年生の発表を紹介します。
3年生は、「ありがとうコール」を担当しました。卒業生一人一人の今までの行動や人柄を紹介してくれました。みんなでありがとうの手拍子をしました。卒業生は、そのメッセージを照れながらも嬉しそうに聞いていました。3年生は、「ありがとうの気持ちを大きな声で言えてよかった」と感想をもちました。
そして、5年生は、会全体の企画・運営を進めてくれました。当日は、司会をはじめとして、全校ゲームで「ドンじゃんけん」を担当したり、卒業生から引き継いだ「木遣天舞」を披露したりしました。他にも5年生は、全校の子どもたちが卒業生一人一人に書いたメッセージを児童玄関に掲示したり、給食時間に放送で紹介したりしました。自分たちが、もみの木児童会をしっかり引き継ぐぞ、という強い気持ちを感じました。(つづく)
|
|
|
| 2020年3月3日(火) |
| 2月28日(金)、「六年生を送る会」を実施① |
 |
 |
|
先週の2月28日(金)の午後に、児童会主催の「六年生を送る会」を行いました。実施のメールで保護者の方が見に来てくださった中で、マスク等を付けながら実施しました。
たくさんの見せ場があったので、プログラムに沿って少しずつ紹介していきたいと思います。
まず、「RPG」の曲に合わせて、小旗をもって2年生が両脇を踊る花道を、6年生が入場しました。そして「『すてきなえがお』と『感動のなみだ』をお届けします!」と、2年生が開会を宣言しました。
次は、1年生のダンスです。キラキラのポンポンを持った1年生は、自分たちで考えた「笑ー笑」ダンスを見せてくれました。ダンスコンテストの各チームのダンスを、アレンジして創ったそうです。
それぞれ、とても元気で楽しい踊りでした。1年生の子どもたちは、「6年生にダンスを教えてもらってうれしかった」気持ちを表そうと頑張ったそうです。(つづく)
|
|
|
| 2020年2月26日(水) |
|
 |
 |
|
2月23日(日)に、中越学童スキー大会並びに新潟県小学校クロスカントリースキー大会が、十日町市吉田クロスカントリー競技場で行われました。当校からは、4人が出場しました。
少雪でコースが普段と違う中、4人の選手は、強風に負けず精一杯の自分の力を発揮しました。満足できる滑りができた子、できなかった子がいましたが、今まで小雪で練習量が少ない中でも努力してきたことに間違いはありません。5年女子の部では、優勝した選手もいました。大会後、「満足できる滑りができたました。全国大会でもがんばります」と話していました。
今年度スキー部は、4~6年生20人で活動してきました。これまで、スキー部を支えていただきました片貝クロカンの皆様や保護者の皆様、大変ありがとうございました。
|
|
|
| 2020年2月25日(火) |
| 6年生、「さつまいも農カフェ」新谷さんのお話 |
 |
 |
|
6年生は、今日の5・6限にキャリア教育の一環として、小千谷で「さつまいも農カフェ」などを経営している新谷梨恵子様からお話を聞きました。新谷さんがさつまいも愛に目覚め、数々のチャレンジをしてきたことをお話くださいました。
まず、子どもたちは、2種類の焼き芋を食べさせていただきました。その味の違いが、焼き方・時間からきていることを皮切りに、5種類もの仕事を楽しみながら、300もの新メニューにチャレンジしたり、異業種のたくさんの人たちとコラボしながら、明るく元気に人生を歩んできたことを熱く語ってくださいました。「マツコの不思議な世界」に出演したときの映像も、見せていただきました。
子どもたちは、「たくさん失敗することもあるけれど、ちゃんと努力を続けて、くじけないでいこうと思います。」「『イモで新潟を元気にしたい』『できない言い訳よりもできる可能性を見つける』など、たくさんの名言が心に残りました。」という感想をもちました。仕事に取り組む姿勢や自分の人生をどう生きていくかなど、たくさんの刺激を受けることができました。
|
|
|
| 2020年2月21日(金) |
| スキー部壮行会がありました |
 |
 |
|
昨日の朝、中越学童スキー大会に出場する選手の壮行会を、4・5年生が中心となって行いました。今回は、インフルエンザの学年閉鎖もあったため、校内放送を使っての壮行会でした。
放送を通して、応援リーダーがエールを送ると、全校から大きなエールが返ってきました。そして、「今年は雪が少なくて、練習があまりできなかったけれど、精一杯頑張ってきます」「優勝を目指して、頑張ります」…等、4人の選手から決意発表がありました。
あさって23日(日)に、十日町市の吉田クロスカントリー競技場で、大会が行われます。「感謝の気持ち」を忘れず、自分のベスト記録からさらに「1秒をけずり出す」ことを目指して頑張って欲しいと願っています。
|
|
|
| 2020年2月20日(木) |
| 6年生、校舎ぴかぴか活動開始 |
 |
 |
|
6年生は、卒業に向けての活動の一環として、校舎ぴかぴか活動を先週から始めています。
この日は、玄関前ピロティーや児童玄関の周りを丁寧にやってくれました。日頃は、限られた時間の中での掃除ですので、なかなか細かいところまで手が回りませんが、6年生からやってもらって助かっています。
6年生に聞いてみると「学校のためにやりがいがあった」「みんなが喜んでくれて良かったです」と話してくれました。これから、階段や特別教室などもぴかぴか活動をやってくれるそうです。いよいよ「卒業生」という呼び方が似合ってきた6年生です。
|
|
|
| 2020年2月19日(水) |
| 6年生、県立歴史博物館を見学してきました |
 |
 |
|
今日の午前中に、6年生は、歴史学習のまとめとして長岡にある県立歴史博物館に見学に行ってきました。縄文時代から現代に至るまでの新潟の歴史を、学芸員の方から説明していただきました。
子どもたちは、特徴のある土器の実物やジオラマをたくさん見て、縄文人がどんな生活をしていたのか具体的にイメージを膨らませることができました。また、江戸時代や昭和初期などいろいろな時代の生活の営みを、様々な道具や家などから感じることができました。
子どもたちからは、「教科書に載っているものを間近で見ることが見ることができて、勉強になった」 「また、家族とゆっくり見に行きたい」といった感想が聞かれました。いきいきと生活してきた人々の歴史をじっくり振り返ることができて、よかったです。
|
|
|
| 2020年2月14日(金) |
| 3年生、警察署に見学に行きました |
 |
 |
|
今週の2/10(月)の午前中に、3年生は、社会科「安全を守る仕事」の学習の一環として、小千谷警察署を見学しました。以前は4年生の学習でしたが、3年生の学習となりました。
まず、子どもたちは、警察の人に仕事内容や勤務の仕方などを質問したり映像を見せてもらったりしました。そして、実際に「警察官の7つ道具」を触らせてもらいました。さらに、パトカーの中を見せてもらい、子どもたちは大喜びでした。
子どもたちは、「かっこいい!」「警察の人はがんばって小千谷の安全を守ってくれている」という感想や気付きをもちました。見学を通して、警察や住民の方々のお陰で安心・安全が守られていることに気づくことができました。
|
|
|
| 2020年2月13日(木) |
| 6年生、アナウンサーの金子様からお話を聞きました |
 |
 |
|
昨日の5時間目、6年生は、キャリア教育(総合)の学習の一環として、フリーアナウンサーの金子陽奈子様から体験談をお聞きしました。
小学校教諭を辞めて、青年海外協力隊でマーシャル諸島共和国に2年あまり滞在し、算数の学習を教えていたり、生活習慣の違いに驚いたりしたこと。帰国後、フリーアナウンサーに転身してからは、記者の気持ちになって何を伝えたいか考えて原稿読んでいること。片貝まつりの花火番付などを読むために、自分が納得いくまで練習をしてきたこと。…など、たくさんの具体的なお話をしていただきました。
子どもたちは、仕事の工夫や努力の他にも、「マイナス言葉を使わない」「闇が一番深いときは、夜明けの直前である」などの言葉から、今までの自分を振り返ったりこれからの行動を考えたりました。これから、さらにお二人のゲストティーチャーからお話を聞きます。自分の将来を考える機会になることでしょう。
|
|
|
| 2020年2月12日(水) |
| スキー授業ができました! |
 |
 |
|
先週の金曜日に1年生、今週の月曜に2年生が、スキー授業をなんとか行うことができました。そして今日は、1・2限に高学年と1年生、3・4・5限に中学年が滑ることができました。
グラウンドの積雪が20cm程度なので、スノーモービルでカッター(みぞ)を付けられませんが、スキーで雪の感触を味わうことができました。2回目の1年生は「この前は一人でスキーを履くことができなかったけど、今日はできたよ。」と何人も教えてくれました。
もう少し雪が降ると、「なかよしの坂」も滑れます。そして、中学年が白山運動公園にスキーに行けるとよいですね。
|
|
|
| 2020年2月10日(月) |
| 新1年生交流会・保護者会を実施しました |
 |
 |
|
先週2月7日(金)の午後から、新1年生交流会と保護者会を行いました。前日からの雪で天候が心配されましたが、青空の下来校いただくことができました。
交流会では、現1年生が新1年生と一緒に紙コップを使った風ぐるまを作ったり、現5年生は新1年生に手遊びを教えたり本の読み聞かせや鬼ごっこをしたりしました。新1年生の子どもたちも、かざぐるまのお土産や先輩たちとのかかわりをとても喜んでいました。
保護者会では、家庭教育講座として「アドラー心理学 褒めない叱らない 勇気づけの子育て」という演題で、講師の多田歩美様からお話いただきました。家庭が、子どもにとって「心の安全基地」になるための、関わり方のいろいろなヒントをお話いただきました。
2ヶ月後には入学してくる新1年生の子どもたちを、みんなで温かく迎える準備をさらにしていきます。
|
|
|
| 2020年2月6日(木) |
| 児童会引継式が行われました |
 |
 |
|
今日の児童朝会の折に、児童会引継式が行われました。
まず、児童会の歌を歌った後、6年生の旧委員長から5年生の新委員長に委員会ファイルが引き継がれました。そして、校長から新委員長に任命書が手渡されました。
「すごく大変なこともあったけど、自分が成長できたと思います。」「カラフル学年の頑張ってきたところを引き継いで、さらにいい児童会にしていきたいと思います。」…旧委員長と新委員長が、自分の成長やこれからの決意など、一人一人自分の思いを堂々と話してくれました。
4・5年生の新委員会のメンバーでの活動が、今週から始まりました。2月末までは、6年生も一緒に活動して、仕事を教えてくれます。来年度に向けて、「もみの木児童会」もさらにパワーアップしていくことでしょう。
|
|
|
| 2020年2月4日(火) |
| 3年生、「片貝さくら」を訪問してきました |
 |
 |
|
昨日の2~3限に、3年生は、総合的な学習の「大好き 片貝さくらのおじちゃん、おばあちゃん」の一環として特別養護老人ホーム「片貝さくら」に行ってきました。暮らしている皆さんや所員の方々と、一緒の時間を過ごすことができました。
まず、笛の合奏や合唱を聴いていただいた後、子どもたちが用意していった遊びを一緒に楽しみました。福笑いや坊主めくり・将棋・花札・ちぎり絵…など、各グループに分かれて2つぐらいのゲームを楽しみました。所員の方は、「皆さん、とっても生き生きしていらっしゃいますね」と話していらっしゃいました。
子どもたちは「よろこんでくれてよかった」という感想をもちました。再来週にもう一度訪問します。自分たちがそこで何をしたいか、これから調べたり話し合ったりして決めていきます。
|
|
|
| 2020年2月3日(月) |
| 4年生、十日町の織物工場へ見学に行きました |
 |
 |
|
先週の金曜日の1/31に、4年生は、社会科「特色あるまちづくり」の学習の一環として、十日町市にある織物工場に見学に行ってきました。伝統産業である着物について説明を聞いたり、たくさんの工程を通して丁寧に作っている様子を見せてもらったりしました。
子どもたちは、実際に糸から布になっていく様子や、型紙を使って染めている様子、検品の様子など、詳しく見せていただきました。そして、多くの人々の努力から、1つの着物ができあがることを理解することができました。「大人になったら赤い着物を着てみたい」「着物を着るのが楽しみになってきた」という思いを、子どもたちはもちました。
それぞれの地域で歴史や伝統を生かしながら、日々工夫と努力を続けて仕事をしている人々がいることに気づくことができました。
|
|
|
| 2020年1月31日(金) |
| 2年生、1年生をあそび広場に招待 |
 |
 |
|
今日の3限に、2年生が、生活科で準備してきた「あそび広場」に1年生を招待しました。2年生教室と視聴覚室に分かれて、自分たちが準備してきたお店を開きました。
磁石を使った魚釣りや、輪ゴムと電池を使って動くコトコト車、ペットボトルと輪ゴムを使ったビュンビュンカーなど、身の回りにある物で作ったおもちゃで遊びます。2年生は、お店に来た1年生の子どもたちに、遊び方やルールを熱心に説明していました。そして、ストップウォッチで時間を計ったり、1年生のゲームの得点を計算したりして、自分たちで作った賞品を渡しました。
1年生の子どもたちは、終わった時に「楽しかった!もっとやりたい。」「こんなにたくさん、賞品をもらったよ」と、大変喜んでいました。きっと、これからも2年生と1年生との交流が引き継がれていくことでしょう。
|
|
|
| 2020年1月30日(木) |
| 3年生担当の音楽朝会で、ダンスを楽しみました |
 |
 |
|
今日の朝、3年生担当の音楽朝会がありました。「歌のお兄さん・お姉さん」は、いつもと違って、たくさんの子どもたちが入れ替わりながらあいさつをリードしてくれました。
「これから歌うので、特にサビの部分のダンスを、見て覚えてください。…」最初に、3年生だけで「元気100%」の歌の発表をしました。緊張していて、はじめ多少声が小さかった3年生も、だんだん大きな声で生き生きと発表しました。
そして、全校の子どもたちも、大きな声で歌いながら3年生のダンスを真似ることができました。この前経験したダンスコンテストのお陰か、みんなが楽しそうに踊っていたことが、とても印象深かったです。
|
|
|
| 2020年1月28日(火) |
| 新委員会活動説明会がありました |
 |
 |
|
今日の6時間目、4~6年生が参加しての新委員会活動説明会が、視聴覚室で行われました。各委員会の5年生から、今年度の活動をもとに引き継ぐ点・改善する点、・新しい活動等の説明と勧誘がありました。
「片小オリンピックとは、どんな活動ですか?」「番組づくりの例の学年代表クイズは、どのようにやるのですか?」… 4年生は、自分がどの委員会に入りたいか考えながら、それぞれの説明にたくさんの質問をしていました。
5年生の発表の仕方や4年生の質問など、来年度の児童会をより良くしようとする意欲が表れていました。これも、今年度委員会活動をリードしてくれた6年生のお陰でもあります。これからも「利他の心」を忘れず、全校のために頑張って欲しいと思います。
|
|
|
| 2020年1月27日(月) |
| たくさんの方に、招待給食に来ていただきました |
 |
 |
|
先週1/24(金)に、給食週間の一環として招待給食を実施しました。今年度、子どもたちが大変お世話になった方々を中心にご案内したところ、公民館長さんやいろいろなボランティアの皆様、伝統芸能保存会や「あいさつし隊」など、40人もの方々にお越しいただくことができました。
「○○さんが特に好きだった給食のメニューは、次のうちどれでしょう。…」「□□さん、毎日道路に立って私たちを見守っていただき、ありがとうございます。…」 特にかかわりのあった学年で会食していただき、一緒にクイズをしたり 日頃から感じていることを話していただいたりしました。
改めて、子どもたちが多くの片貝町の皆様に日頃からお世話になっていることを実感しました。今後もお世話になりますが、よろしくお願いいたします。
|
|
|
| 2020年1月24日(金) |
| 児童朝会で、伝言ゲームをしました |
 |
 |
|
昨日23日(木)に、放送委員会主催のもみの木朝会が行われました。内容は、放送委員会が朝紹介している「早口言葉」を使った伝言ゲームです。
チーム分けは、ダンスコンテストやドッジボール大会でも使った10チームです。各チームの班長が、ボックスから「早口言葉」を選んでチャレンジしました。終わったチームから、司会に報告に行きます。
「赤巻紙・青巻紙・黄巻紙」「にわとりが二羽、庭にいた」… 頭を寄せ合って、早口言葉を伝える姿が、微笑ましかったです。縦割りチームのかかわりも、これでまた一つ深まったことでしょう。
|
|
|
| 2020年1月23日(木) |
| 授業参観、ありがとうございました |
 |
 |
|
春のような青空の下、昨日22日(水)の5限に低学年、6限に高学年の授業参観を行いました。各学年の廊下には、校内書き初め展の作品が掲示されています。
「今度は、ぼうぼうゲームをお母さんとしたいなあ」…「ミシンの上糸を掛けるのが難しいから、手伝って欲しい~。」…国語や算数・学活・家庭科・プログラミング教育など、各学年の学習の様子を見ていただきました。学年によっては、授業に参加していただき、ありがとうございました。
子どもたちの今までの学習の成果が、随所に見られたのではないかと思います。残り約2ヶ月、一人一人の子どもが、様々なかかわりの中で更に成長するように、支援していきたいと思います。ご協力ください。
|
|
|
| 2020年1月20日(月) |
| スポーツ委員会主催、スーパードッジボール大会① |
 |
 |
|
今日の昼休みに、スポーツ委員会主催のスーパードッチボール大会の1日目がありました。チームは、もみのキッズダンスコンテストの時の、縦割りの10チームです。
先週の昼休みにルール説明とトーナメントの抽選会があり、今日から南運動場・北運動場に分かれて対戦が始まりました。①全員が、ボールを1回は投げる。②ボールをキャッチしたら、同じチームの当たっていた人(外野)が復活できる。③頭や顔に当たっても、セーフ。④試合時間は5分間で、延長1分。…等、委員会が決めた6つのルールで行っています。
ボールを投げるのも大切ですが、強いボールをキャッチすると、「ウォー!」と観客から歓声が上がります。いろいろな子がヒーローになる場面があって、子どもたちも大盛り上がりです。明日は、準決勝や決勝が行われる予定です。
|
|
|
| 2020年1月17日(金) |
| 新しい清掃班でがんばっています |
 |
 |
|
今週の14日(火)から、3学期の新しい清掃班で掃除を行っています。3学期は、5年生がいるところは5年生が清掃班長をします。(5年生がいないところは,6年生がします)6年生から5年生への引継が、清掃でも行われているのです。
新しいメンバーと新しい場所で、一人一人が新鮮な気持ちで清掃に取り組んでいます。清掃活動は、校舎を磨くだけでなく、自分の心も磨く活動だと思っています。特に水拭きは、足腰も疲れますし、自分の手も汚れてしまいます。でも、だからこそ一生懸命にやれる子になって欲しいと願っています。
いつでも清掃にきちんと取り組める子は、それだけで信頼される人になれると思うからです。ずっと、今の気持ちを忘れずに続けて欲しいと思います。
|
|
|
| 2020年1月16日(木) |
| 冬期間の避難訓練を行いました |
 |
 |
|
今日の3時間目に、第3回避難訓練を行いました。今年は雪が大変少ないですが、降雪がたくさんあることを想定しての避難場所や避難経路で行いました。
子どもたちは、非常ベルと避難開始の校内放送を聞いた後、防寒着と長靴・防災ずきんを身につけて、外に避難を開始しました。避難場所は、片貝小学校から浅原神社に向かう道路です。子どもたちはどの学年も、避難の時だけでなく、待機している時も校舎に戻るときも、無駄口が聞こえませんでした。大変立派な態度でした。
教室に戻った後に、校内放送等を通じて指導・講評や振り返りを行いました。様々なことを予めイメージして、少しでも冷静に対処できる人になって欲しいと願っています。
明日は、阪神大震災が発生した日です。大きな災害が、これからずっと世界中で起こらないことを願ってやみません。
|
|
|
| 2020年1月15日(水) |
| 5年生、JR東日本の出前授業 |
 |
 |
|
昨日14日(火)の5・6限に、5年生は、社会科の「広がる情報ネットワーク」の学習の一環として、JR東日本の方々から出前授業をしていただきました。
まず、昔の切符とSuicaを比較して、Suicaを使うとどんな良いことがあるかを考えました。そして、そこにたくさんの情報がつまっていて、その情報を活用して便利さや快適さを生み出していることがわかりました。次に、列車を安全に時間どおりに動かすために、どのような工夫をしているか教えてもらいました。そして、鉄道の「安全」「安心」「正確さ」のためにJRの方々が情報ネットワークを上手に活用していることがわかりました。
子どもたちは、「今度Suicaを使ってみたい。」 「カード1枚にすごい情報がたくさんつまっていて、びっくりした。」といった感想や気づきをもつことができました。様々な場面で、安全・安心のために、正確な情報が必要であることを学ぶことができました。
|
|
|
| 2020年1月14日(火) |
| 低学年、コーディネーショントレーニング①実施 |
 |
 |
|
本日の2・3限に、低学年は、第1回目のコーディネーショントレーニングをしました。講師は、小千谷市の体育指導員でもあるPTA会長様です。それぞれの学年ごとに、いろいろな動きを体験しました。
まず、どのくらいの基礎体力があるか、バランス感覚や柔軟性・筋力の強さなどがわかる動きにチャレンジしました。後半は、3チームに分かれての助け鬼です。2年生は、1年生よりちょっと難しいルールで、各チームで相談して3人の王様を決めてやりました。「頭と足がついたよ!」「片足じゃ難しくて、立てないよ」「チームワークがよかったから、うちのチームが一番だったよ!」…など、歓声を上げながら、みんなで様々な運動を楽しみました。
次回は、道具も使いながら、いろいろな運動にチャレンジするそうです。子どもたちの「おもしろい!もっとやりたい!」という気持ちを引き出す指導法を、今後も参考にしたいと思います。
|
|
|
| 2020年1月10日(金) |
| 校内書き初め大会を行いました |
 |
 |
|
昨日の2時間目に、校内書き初め大会を実施しました。各学年が、冬休みに練習してきた文字を書きました。1・2年生は硬筆、3~6年生は毛筆です。
各教室では、静かな雰囲気の中でそれぞれの子どもが、集中して書き初めに取り組んでいました。学年に応じて、「とめ・はね・はらい」や文字の組み立てに注意して書きました。「一年せいの年となまえがむずかしかったけど、がんばれたからうれしかったです。」などの感想がありました。
校内書き初め展が、1月17日(金)~22日(水)に予定されています。(22日は授業参観です。)各教室の廊下に掲示してありますので、是非、子どもたちが一生懸命取り組んだ作品をご覧ください。
|
|
|
| 2020年1月9日(木) |
| 3学期が始まりました |
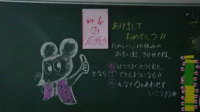 |
 |
|
あけましておめでとうございます。ありがたいことに、冬休み中に大きな怪我や病気・事故事件等の連絡が特になく、昨日より3学期がスタートしました。例年に比べて降雪が極端に少ない中、子どもたちが元気に登校してきました。
「算数の学習と走ることを、がんばりたいです!」「算数が得意になることと、縄跳びが上達したいです。」始業式では、2年生と4年生の代表が、それぞれ自分の3学期のめあてを、大きな声で発表しました。校長からは、自分の夢や願いを達成するために、目標を立てたり努力を続けたりする時の大切な点を伝えました。
3学期は、51日間と大変短い学期です。一人一人が自分の目標をしっかりもち、充実した学校生活を送りながら、次の学年の準備ができるようにしていきたいと思います。
|
|
|
| 2019年12月24日(火) |
| 2学期が今日終わりました |
 |
 |
|
8月27日から始まった81日間の2学期が、本日終わりました。2学期には、片貝まつりや学びランドなど多くの行事等もある中で、子どもたち一人一人が大きく成長しました。
4限に行った終業式では、まず、中越教育美術展やジュニア展、県のいきいきワクワク科学賞の表彰をした後、2人の代表児童から2学期を振り返っての発表がありました。「ダンスコンテストでは、1~6年生のみんなで考えたダンスを一緒に踊ることができて、とても楽しかったです。…」「マラソン大会では、去年の記録を塗り替えようと、朝マラソンなどでがんばって練習してきました。…」2人は、原稿を見ずに堂々と発表してくれました。
その後、各学年等で取り組んできた2学期の様子を、写真で振り返りました。子どもたちの素敵な笑顔と真剣な表情を、みんなで確かめ合うことができました。
保護者の皆様方には、各活動でたくさん支えていただき、大変ありがとうございました。 良いお年をお迎えください。
|
|
|
| 2019年12月20日(金) |
| 2年生、「九九マスター」に向かってがんばっています |
 |
 |
|
2年生は、12月に入って九九の練習に力が入っています。「九九マスター」になるために、1~9の各段を①確認②上がり③下がり④ばらばら…と、チェックを受けていきます。①の確認は12秒で合格ですが、②~③は10秒で合格になります。
「○○先生に用があってきました。今、九九を聞いてもらっていいですか?」…20分休みや昼休みに、2年生の子どもたちが、教務室や校長室を訪れて、一人一人チェックを受けます。担任だけなく校長・教頭・教務主任なども、ストップウォッチ片手に九九を聞きます。
「今度は、○の段の一つ飛ばしをお願いします」…最近は、「九九マスター」をクリアして「スペシャル九九」にチャレンジし、合格する子も出てきました。友達同士でもチェックをし合い、お互いに高め合っている姿が素敵です。
|
|
|
| 2019年12月18日(水) |
| 6年生、片貝中新入生説明会に行ってきました |
 |
 |
|
昨日の午後、6年生は、新入生説明会に片貝中学校に行きました。
最初に、各学年の学習している様子を見せていただきました。先輩の中学生が、実際に英語や理科や国語などの学習をどんな風に進めているか、知ることができました。また、文化部の生徒から、1日の流れや年間行事についても教えてもらいました。そして、放課後には、様々な部活動の練習の様子も見せてもらいました。
6年生は、「部活の見学をして、部活が楽しみになった」「先輩が、分かりやすく説明してくれて良かった」と感じました。4ヶ月後の中学入学に向かって、少しずつ準備を進めていきます。
|
|
|
| 2019年12月17日(火) |
| 低学年、読み聞かせをしていただきました |
 |
 |
|
先週の金曜日に、3人のボランティアの方々から、今年最後の読み聞かせをしていただきました。低学年の3つの学級で、「かさこじぞう」などの絵本を読んでもらいました。
それぞれの方が、子どもたちに読み聞かせたい本を選んでもって来てくださいます。場合によっては、読みやすいように、ご自身で本文を全部PCで打ち直してくださっていることを知り、とても驚きしました。
子どもたちは、ゆったりとした表情豊かな語り口に、物語の世界に引き込まれて聞いていました。当校の子どもたちが、給食の時間に校内放送で自分たちで進んで読み聞かせをするのも、ボランティアの皆様の影響かもしれませんね。
|
|
|
| 2019年12月13日(金) |
| 4年生、片貝の偉人の話を聞きました |
 |
 |
|
12日と5日に、社会科の「昔から今へ続くまちづくり」の一環として、片貝町の観光ボランティアの方から、片貝の偉人の話をお聞きしました。
先週は、朝陽館・講読道をどんな人たちが作ったのか、そこでどんな学問がされていたか、学んだ人たちがその後どんな役割を果たしたのか、…等を学びました。今週は、佐藤佐平治翁が津南にある結東村を助けたエピソードを中心に、お話しくださいました。そして、現在もその遺徳を偲んで、佐平治まつりが行われていることを学びました。
それぞれの話から「朝陽館は、片貝の子どもに立派な学問を学ばせたいという村人の思いから、人々の協力で建てられた」「佐藤佐平治は誰にでも分け隔て無く私財を投じ、貧しい人々を助けてあげた」と、子どもたちは気づきました。「利他」の心を、子どもたちにも受け継いで欲しいと願っています。
|
|
|
| 2019年12月12日(木) |
| 6年生、税金の学習をしました |
 |
 |
|
昨日11日に、6年生は、社会科の学習の一環として、小千谷法人会の方々に租税教室をしていただきました。
子どもたちは、税金の中で聞いたことがある種類を発表した後、税金で作られているものにはどんなものがあるか、子ども一人あたり12年間でどのくらいの税金が使われているか、…などを教えていただきました。また、1つのプールの建設費である1億円の重みを、実際に体験させていただいたり、税金がなくなったらどんな世界になるか、をDVDで見せてもらったりしました。
子どもたちは、学習の振り返りで「税金によって暮らしが支えられていることが分かった。」「自分たちの学校生活のためにも税金が使われていることを知り、びっくりした。」といった感想が、多く見られました。3学期には、政治の学習の中でさらに学習を深めていきます。
|
|
|
| 2019年12月11日(水) |
| 5年生、西脇順三郎出前授業 |
 |
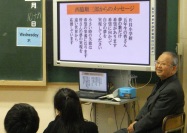 |
|
本日、6時間目に「西脇順三郎を偲ぶ会」の3名の方々から、5年生は、順三郎の足跡を教えていただきました。
小千谷市出身で、幼少の頃は体が弱く友達とも遊ばなかったこと。英語や絵の勉強を一生懸命がんばるようになったこと。大学を卒業する時には、ラテン語で論文を書けるようになったこと。イギリスに留学して勉強した後、ノーベル文学賞候補に何回もなったこと…、など教えていただきました。子どもたちは、クイズに答えながら順三郎のすごさを知ることができました。
子どもたちは、「すごい人なんだな」「夢って大切だなあ」と感想をもちました。子どもたちは、世界で活躍した小千谷出身の偉人の一端を知り、夢や志の大切さを学ぶことができました。
|
|
|
| 2019年12月10日(火) |
| 道徳の授業公開を行いました |
 |
 |
|
先週の金曜日、鼓笛引継式の後に、授業参観を実施しました。今回は、全学年で道徳授業の公開を行いました。
それぞれの学年では、発達段階に合わせて、人権やいじめ・不撓不屈などのテーマに沿って心の学習をしました。「いじめられている子の家の人は、嫌な気持ちになったり知らなくてショックだったりすると思います」…「見て見ぬふりの傍観者も、いじめに加わっていることになるのか。」… なにが問題なのか、自分はどう思うのか、自分ならどうするか、一人一人が一生懸命考えました。
様々な問題場面を自分ごととしてとらえ、相手の気持ちになって考えるようになって欲しいと思います。そして、日常生活でも、実際に自分で考え行動しようとする子どもたちに育てていきたいと考えます。ご協力をお願いします。
|
|
|
| 2019年12月9日(月) |
| 鼓笛隊、立派に引き継がれました! |
 |
 |
|
先週金曜日の6日、授業参観前の昼休みに、南運動場で鼓笛引継式が行われました。6年カラフル学年から、4・5年ひまわり・ひかり学年に引き継ぎが行われる様子を、1~3年生やたくさんの保護者の方々も、見守ってくださいました。
カラフル学年最後の演奏の後、楽器や衣装の引き継ぎが行われ、ひまわり・ひかり学年の初めての演奏も披露されました。6年生の総指揮のあいさつでは、たくさんの困難を乗り越えた自分たちの成長が語られました。そして、5年の新総指揮から6年生への感謝の言葉と、これからの決意が述べられました。
今まで放課後や昼休みを使って、6年生は、4・5年生に演奏以外にもたくさん教えてくれていました。素敵な先輩の姿を、後輩は受け継いでくれることでしょう。
|
|
|
| 2019年12月5日(木) |
| 2年生、音楽朝会をリードしました |
 |
 |
|
今日の朝、あられの降る中、2年生がリードする音楽朝会がありました。今月の歌は、「山の音楽家」です。
まず、2年生の「かがやきあいさつ隊」が、高学年の「歌のお兄さん・お姉さん」を目標に、リズムよく全校のあいさつをリードしてくれました。そして、歌いながら大きくふりをつけて、2年生が発表しました。その後、全校で振り付きで楽しく歌いました。
2年生の子どもたちは、「上手くできて、楽しかった。」「緊張したけど、ちゃんとできて良かった!」と喜んでいました。自分たちも楽しみながら、大きな声で歌えたことに、子どもたちの大きな成長を感じています。保護者の方々も見に来ていただき、大変ありがとうございました。
|
|
|
| 2019年12月4日(水) |
| 5年生、新潟市に社会科見学! |
 |
 |
|
昨日、5年生は、社会科の「暮らしを伝える情報」の学習で新潟市に行ってきました。午前中に新潟日報おもしろ新聞館、昼食を新潟ふるさと村、午後にTENYを見学しました。
おもしろ新聞館では、片貝出身の方に案内していただき、「取材」から始まって、新聞が家庭に届くまでの仕事内容を教えていただきました。また「新聞百人一首」で楽しみながら見出しや写真の大切さを学びました。
TENYでも、テレビ番組の作り方だけではなく、実際のスタジオに入れていただき、アナウンサーの方から質問に答えていただいたり、テレビカメラを操作させてもらったりしました。
子どもたちは、「これまで知らなかった裏方の仕事があって驚いた」「今度新聞をもっと読んでみよう」などとつぶやいていました。 発見の多かった1日になりました。
|
|
|
| 2019年12月3日(火) |
| 6年生、薬物乱用防止教室を受講しました |
 |
 |
本日5限に、6年生は、小千谷ライオンズクラブの6人の皆さんから、薬物乱用防止教室を実施していただきました。主な内容は、アルコール・たばこや、大麻や覚醒剤などの薬物の害についてでした。
アルコールやたばこが、依存を引き起こし、止めたいと思っても、自分の意思ではなかなか止められなくなること。若い時に始めると、体や脳の障害がさらに大きくなること。薬物は、さらに依存が強くなり、幻聴・幻覚・精神異常などから、犯罪などを引き起こすことがあること。周りの家族等も振り回され、不幸になることなどを、教えていただきました。
子どもたちは、薬物の模型なども見せてもらい、「大人になったら、人から誘われても絶対断りたい!」「薬物乱用によって、体のいろいろなところに影響が出ることが分かりました。」といった感想をもちました。是非、生涯に渡って、「薬物乱用はダメ。ゼッタイ。」を心に刻んでいて欲しいと願っています。 |
|
|
| 2019年12月2日(月) |
| 小千谷学童相撲大会、がんばりました! |
 |
 |
|
先週土曜日に小千谷市総合体育館で、小千谷学童相撲大会が、行われました。当校からも17人の子どもたちが出場してきました。
今まで昼休みなどに練習してきた子どもたちは、それぞれ学年男女別の個人戦と、男子はさらに団体戦にも出場しました。「集中力」と「気合い・気迫」を大切に、一人一人が精一杯戦いました。
たくさんの「真剣な眼差し」や「笑顔」、「悔し涙」などから、子どもたちの確かな成長を感じることができました。この経験から、さらに強い体・強い心を鍛えていって欲しいと思います。
|
|
|
| 2019年11月29日(金) |
| 笑顔があふれたダンスコンテスト! |
 |
 |
|
昨日の午後1時30分から、児童会主催のダンスコンテストが行われました。テーマ「心おどるダンスコンテスト みんなで楽しく盛り上げろ!」のもと、10チームに分かれてダンスを披露しました。
審査の観点は、①ダンスに切れがあるか、②みんなの振りがそろっているか、③振りが大きいか、④オリジナル性があるか、の4つです。審査員は、子どもたちが、ダンスの先生や地域ボランティアコン-ディネーターのお二人など、6人の方にお願いして、厳正な審査をしていただきました。
審査員の方々も「どのチームもとってもかっこよくて、審査が難しいです」「自分たちでダンスを考えて練習して、がんばったのがよく分かります」と話していらっしゃいました。それぞれ賞をもらったチームや子どもたちはもちろんのこと、みんなの素敵な笑顔があふれたコンテストになりました。そして、練習などを通して、4・5・6年生の子どもたちの成長が、たくさん見られた会になりました。
|
|
|
| 2019年11月27日(水) |
| 1年生、「あきのあそびランド」を開きました |
 |
 |
|
今日の3限に、1年生の1・2組一緒に「秋のあそびランド」を行いました。今まで、自分たちが生活科で作ってきたいろいろなものを使って、お店やさんを出しました。
ドングリごまやけん玉などのおもちゃ、葉っぱを使ったこすり出しや秋のファッション、木の実を利用したマラカスや的当てなど、グループごとにお店の準備をしました。お客様は、2年生や先生方です。1年生は、お客さんにルールを教えたり時間を計ったりして、お店を運営しました。
子どもたちは、「パチンコ屋さんで、声を出してお客さんを呼ぶことをがんばった。」「最初はすっかすかだったけど、2年生の男の子たちがたくさん来てくれた!」「2年生が、そろばんがしたいとかコマがしたいとか、いろいろ話しかけてくれて嬉しかった。」と感想をもちました。「秋」の学習が一段落して、いよいよ冬の季節が始まりますね。
|
|
|
| 2019年11月26日(火) |
| ダンスコンテストに向けて! |
 |
 |
|
今日の朝活動の時間、ダンスコンテストに向けての練習が行われました。曲ごとに北運・南運に分かれて、チームごとに6年生を中心に練習しました。
何回も曲を流した後にミーティングタイムを取って、出だしや決めポーズをどうするか考えました。また、さらにダンスがかっこよくなるように、手拍子やかけ声を入れたり、動きを変更したり、各チームで工夫しています。
「ここで3秒、しっかり止まるよ」「男子と女子と交互に立ったり、しゃがんだりするからね」 子どもたちの笑顔が増えて、いろいろな工夫も生まれてきています。明後日のコンテスト本番が、とても楽しみです。
|
|
|
| 2019年11月25日(月) |
| 2年生、授業研究会がありました |
 |
 |
|
先週の金曜日に、2年生のクラスで道徳の授業研究会が行われました。校内の職員だけでなく、片貝中学校や中越教育事務所の指導主事の先生方も参加されました。
授業では、「公園のおにごっこ」という資料をもとに、自分の考える親切と相手の願っていることについて考えました。幼稚園に通う足の不自由な子と一緒にする「鬼ごっこ」の場面で、どう行動することが本当の意味の「思いやり」なのか、子どもたちは自分ごととして悩みました。子どもたちは、「鬼ごっこではなく、手つなぎ鬼にする」「手を抜かないで、一生懸命追いかける」「相手の気持ちを聞いて、そのようにやってあげる」など、友達と意見を交流させながら、自分の考えをまとめることができました。
是非、日常の生活場面でも、相手の気持ちを考えることを活かしていって欲しいと思います。
|
|
|
| 2019年11月22日(金) |
| ありがとうございました!読み聞かせ |
 |
 |
|
今日の朝活動の時間、読み聞かせボランティアの方々が、高学年に読み聞かせをしてくださいました。
今回は、 「ハナミズキのみち」と「葉っぱのフレディー」という本を読んでくださいました。1つは、東日本大震災であった実際にあったことを絵本にした絵本です。もう一つは、葉っぱを人に例えた「命・死・輪廻」をテーマにした絵本でした。それぞれの学年とも、読み手の方の語り口に引き込まれて聞いていました。
子どもたちは、「ハナミズキの街路樹が、避難の目印のために植えられていたと初めて知りました」「葉たちが日陰を作っている所がおもしろかったです。葉っぱも仕事をしっかりしていて『人と少し似ているなあ』と思いました」といった感想をもちました。子どもたちは、得がたい経験をすることができました。本に興味をさらにもつようになって欲しいと思います。
|
|
|
| 2019年11月20日(水) |
| 「小千谷の食と歴史探検ランチ」、美味しかったです |
 |
 |
|
11月は和食月間で、県内で「和食」がテーマの給食を実施しています。小千谷市では、8月に行われた調理コンクールで優秀賞を受賞した「小千谷の食と歴史探検ランチ」が、昨日市内の学校で提供されました。
当校では、小千谷市教育委員会の松井教育長様をはじめ3人のお客様をお迎えしました。お客様からは、1年と3年の各クラスに分かれて、子どもたちと一緒に給食を食べていただきました。主なメニューは、「鱈のせんべい揚げけんさんソース」「雪国小千谷のつけもんごっつぉ」「布海苔汁」「泳ぐ宝石豆乳寒天」です。
お客様からも「せんべい揚げ、初めて食べました。美味しいですね」「豆乳を使っていて、ヘルシーでいいですね」という感想をいただきました。レシピも配られましたので、ご家庭でもいかがでしょうか?
|
|
|
| 2019年11月19日(火) |
| 5年生、工場見学に行ってきました |
 |
 |
|
昨日、5年生は、社会科学習「自動車づくりにはげむ人々」で、小千谷にあるNSアドバンテックに、工場見学に行ってきました。
工場では、最初に、あらかじめ送っていた質問事項に答えていただきながら、会社の概要を教えてもらいました。そして、環境に配慮しながら、信頼される製品づくりに努めていることを、具体的に教えていただきました。
そして次に、実際に工場の中を見学させていただきました。働いている方々が、不良品が出ないように常に「整理・整頓・清掃」に気を配りながら集中して仕事をしている様子を、実際に見せていただきました。子どもたちは「ロボットと人の役割分担ができていてすごい」「働く人にやさしい工場だ」といった感想をもっていました。
これから、日本の工業生産全体に学習を広げ、どんな特色があるか、これから世界の中でどんな製品を開発しようとしているか学んでいきます。
|
|
|
| 2019年11月14日(木) |
| 3年生、原信の見学に行ってきました |
 |
 |
|
今日の午前中に、3年生は社会科の学習「すごいぞ!野菜を売る仕事」で、小千谷にある原信に見学に行ってきました。
子どもたちは、まずお店の中で、商品の値段や生産地を調べたり、店員さんがどんな仕事をしているかを観察したりしました。次に、商品を梱包したりシールを貼ったりしているバックヤードも見せていただきました。その後、お店の方にお客様をたくさん集めるための工夫をいろいろ質問し、丁寧に答えていただきました。4つの原則(品切れをしない・明るいあいさつ・味の追求・清潔な店内)の大切さを、子どもたちも理解したようです。
子どもたちは「品揃えがすごい!」「みんな手作りで美味しそう!」「たくさんの工夫があってびっくりした。」と、感想をもちました。これから、お客様の様々なニーズに応えながら野菜の販売を増やすための、お店の工夫や努力について深めていきます。
|
|
|
| 2019年11月13日(水) |
| 巫女爺クラブに、大きなプレゼントが届きました |
 |
 |
|
11月12日(火)は、それぞれのクラブの今年度最終活動日でした。年間10回の活動でしたが、巫女爺クラブは夏休みの活動やいろいろな会での発表も合わせると、20回の活動を行いました。
前日に時事通信社から、片貝小学校に大きなプレゼントが届きました。第34回時事通信社「教育奨励賞」の努力賞を受賞したということで、新潟支局長さんが賞状と盾を届けてくださいました。片貝伝統芸能保存会の方々が、長年に渡り「巫女爺」を当校で子どもたちに教え、次世代も指導者として育ってきたこと。巫女爺だけでなく、郷土の人材・素材を活かしたキャリア教育に力を入れていること。それらをまとめた研究レポートを、評価いただいた結果です。
活動の最後に、指導者の方々も含めてみんなで、賞状や盾と一緒に写真を撮りました。子どもたちは「今年、3曲マスターできてうれしかった。」「来年はもっと上手になりたい。」などの感想を話していました。来年度以降も、「片貝町の宝」としてずっと続いていくことでしょう。
|
|
|
| 2019年11月12日(火) |
| 6年生、むし歯予防教室で学習 |
 |
 |
|
本日午後に、鈴木学校歯科医様が、6年生にむし歯予防教室で指導してくださいました。子どもたちは、3年生で一度むし歯予防について教えていただき、今回さらに深く学ぶことができました。
8020運動など将来に渡ってむし歯予防が大切であることや、歯周病が歯を失う大きな原因であることなど、映像を交えて教えていただきました。また、歯ブラシだけでなくデンタルフロスの使い方も学習しました。鈴木様は、「夜の歯みがきが一番大切です。」 と強調なさっていました。子どもたちは、「普段食べているおやつや飲み物に、こんなに砂糖が入ってるなんて知らなかった。これからはおやつの取り方にも気をつけたい。」といった感想をもちました。
鈴木様からは、毎年学習ボランティアとして2回、子どもたちに教えていただいています。大変ありがとうございます。
|
|
|
| 2019年11月11日(月) |
| 休憩時の避難訓練を行いました |
 |
 |
|
本日、昼休みに火事の想定で避難訓練を実施しました。当校では、近年実施時間を教えないで行う休憩時の訓練をしていなかったので、教職員も子どもたちもドキドキしながら実施しました。
子どもたちは、体育館やグラウンドで遊んでいたり、ウサギの世話や係の仕事・鼓笛の練習をしていたりと様々で、それぞれの場所から避難しました。そして、わくわくハウス前で点呼をとって、全員の避難を確認しました。
「今までの地震をみても、天災や人災は、いつ起こるかわからない。『おかしも』を守って、自分の身をしっかり守れるようになろう。」と話しました。生涯に渡り、自分の命は自分で守れるようになって欲しいと考えます。
|
|
|
| 2019年11月7日(木) |
| ダンスコンテストに向けて練習開始! |
 |
 |
|
本日5・6時間目に、ダンスコンテストに向けての練習がスタートしました。今日までに、2つの縦割りグループから1つのチームを作り、チームごとに2曲の課題曲から1つを選択しています。
今日は、4~6年生が5時間目にダンスの講師の方から来ていただき、基本的な9つのステップと隊形移動を教えていただきました。そして、6時間目は曲ごとにそれぞれのチームに分かれ、振り付けを考えました。それぞれの学年で自分たちの担当の部分を考え、チームごとにアドバイスし合いました。
子どもたちは、最初は恥ずかしそうに踊っていましたが、段々動きも大きくなり、教えてもらったステップをアレンジしていきました。子どもたちからは「プロはかっこいいなあ!」「明日も練習していいですか?もっと、工夫しよう!」といった感想が聞かれました。来週は、振り付けを1~3年生に教えます。
|
|
|
| 2019年11月6日(水) |
| ありがとうございました、友愛バザー |
 |
 |
|
先週11月2日(土)の「学びランド」の午後に、PTA友愛バザーがありました。今年度は恵贈品の収集方法が大きく変わり、品数が揃うか心配しましたが、町内や保護者の皆様のご協力のお陰で、たくさんの品物も揃いました。
当日は、30分前には玄関の外に行列ができはじめ、町民の方も含めたくさんの皆様に、買いに来ていただきました。子どもたちも、大人に混じって日用雑貨や文房具・食料などを買ったり、5年生は総合で作ったお米を「ひまわり米」として販売したりしました。
収益金も、予想を上回る額になったようです。(詳しくは後ほど、PTAから報告があります。)役員さんをはじめとして、大変お疲れ様でした。そして、台風19号の義援金も、たくさんの方からご協力いただき、誠にありがとうございました。
|
|
|
| 2019年11月2日(土) |
| もみのキッズ学びランド、大成功! |
 |
 |
|
本日秋晴れの下、片貝小学校の文化祭である「もみのキッズ学びランド」を行いました。ご来賓・保護者・地域の方々を、南運動場いっぱいにお迎えして、「笑顔で元気よく堂々と」を目指して発表しました。
1年生のファンファーレ付きの開会の言葉から始まり、1年:ぼくらはなんだってできるんだ、2年:大好き片貝かがやきたんけんたい、3年:歌のすきなまほうつかい、4年:よりよい生活を目指して、5年:奉納木遣・おけさ・さかのぼり、6年:佐藤佐平治の心を伝える、を発表しました。他にも、巫女爺クラブの演技や、6年生の閉会の言葉、全校合唱「ふるさと」などもありました。
子どもたちは、各学年全力で演じ、歌い、合唱し、ダンスしました。ご来賓の方々からも、「とっても素敵な発表でしたね。」「子どもたちが堂々としていましたね。」といった感想をいただきました。今までの学習の集大成の1つであるもみの「キッズ学びランド」が大成功に終わり、子どもたちも充実感をもって終えることができたと思います。保護者・地域の皆様の今までのご支援等、大変ありがとうございました。
|
|
|
| 2019年10月31日(木) |
| 1年生、授業研究会がありました |
 |
 |
|
今週火曜日に、1年1組で生活科の授業研究会がありました。校外からも高校の先生1名、中学校の先生が2名参加して、研修を行いました。
「あきとなかよし」の学習は、季節の変化に気づいたり、自分たちの作ったおもちゃで遊び広場を作ったりする学習です。この日は、ドングリごまを自分たちで作りながら、どうしたら長く回るか、班ごとに研究員になって調べました。
子どもたちは、違う条件でいくつものドングリごまを作りながら、「丸いドングリで、短くまっすぐな軸だと、長く回る」ことをつきとめました。子どもたちは「長い軸だと回すのが難しい。」「自分と友達のこまを比べたら、回しやすいものがあった。」と感じました。これから、「研究成果」を活かしておもちゃを工夫したり、遊び広場を作ったりしていきます。
|
|
|
| 2019年10月30日(水) |
| 5・6年生、ハロウィンウォークラリーを楽しみました |
 |
 |
|
今日の3・4限に5・6年生が、外国語学習の一環としてハロウィンウォークラリーを行いました。それぞれの学年が、5つのチェックポイントを回りながら、チェックポイントにいるボランティアさんやサラ先生・教員と、今まで学習した英語の表現を使って会話したり、クイズに答えたりしました。
クイズの中には「ハロウィンは、日本でいうどんな行事? A:運動会、B:こどもの日、C:お盆」という答えからひとつ選びます。答えは、…Cですが、Bと考える子どもたちがたくさんいました。他のクイズでも、グループで相談しながら楽しみながら答えていました。
子どもたちは「初めてこういうラリーをやりましたが、とても楽しかったです。先生たちの仮装もおもしろいし、英語もちょっとだけわかってうれしかったです。」といった感想をもちました。楽しみながら、学習してきたことを活用できて良かったと思います。
|
|
|
| 2019年10月29日(火) |
| 4年生、1/2成人式を行いました |
 |
 |
|
先週金曜日の午後に、4年生は1/2成人式と合わせて学年PTA行事を行いました。
前半の1/2成人式では、一人一人が「家族への感謝」や「将来の夢」を自分の言葉で発表したり、全員で「あなたにありがとう」を合唱したりしました。涙を流す子どもたちや保護者の方々もいました。
後半のPTA行事では、、親子で写真立て作りを行ったり、親子のスキンシップゲームをしたりしました。子どもたちは「感謝をお母さんに伝えられて良かった!」「親子でかわいい写真立てが作ることができた!」、保護者の方からは「とてもいい式典で、思い出に残る1日になりました。」といった感想が聞かれました。
同じ体験をすることによって、親子の絆が深まったのではないでしょうか?
|
|
|
| 2019年10月24日(木) |
| 5年生、親善音楽会で発表してきました |
 |
 |
|
今日、午前中に小千谷小学校で、市親善音楽会の1日目が開催され、片貝小の5年生が参加してきました。他には、吉谷小、小千谷小、片貝中、小千谷中、南小・南中が参加し、音楽発表を通じて交流しました。
片貝小は、斉唱「奉納木遣」と合奏シャギリ「おけさ・さかのぼり」を発表してきました。子どもたちは、心を一つに合わせて、堂々と唄ったり演奏したりしました。普通の木遣やシャギリと違って、ソロパートをつくったり強弱をつけたりして、曲を盛り上げました。
子どもたちは他校の演奏も聴いて、「自分も、ジュピターの合奏をやってみたい。」「中学生の演奏はCDみたいだった。」などの感想をもちました。5年生にとって、次の演奏会は、もみのキッズ学びランドです。さらに、すばらしい演奏を聴かせてくれることでしょう。
|
|
|
| 2019年10月23日(水) |
| 4年生、新潟市へ小旅行に行ってきました |
 |
 |
|
先週金曜日に、4年生は、社会科の学習の一環として、新潟市へ校外学習に行ってきました。行った見学先は、自然科学館・新潟空港・県庁・ウォーターシャトルの4つです。
特に子どもたちが興味をもったのは、自然科学館とウォーターシャトルでした。自然科学館では、プラネタリウムを見たり、ロボットを操作したり、台風の風の強さなどを体験したりしました。また、ウォーターシャトルで、県庁脇から新潟ふるさと村まで信濃川をさかのぼりました。
子どもたちは、新潟市に行って「高いビルや車が多いね。」「県庁には、たくさんの県の機関が入っている。」…といった感想をもちました。体験を通して、小千谷・長岡市と違った新潟市の特徴を知ることができました。これからさらに、県全体についても学んでいきます。
|
|
|
| 2019年10月21日(月) |
| 1・2年生、丘陵公園里山フィールドミュージアムに行ってきました |
 |
 |
|
今日、1・2年生は、国営越後丘陵公園里山フィールドミュージアムにバスで行ってきました。1・2年混合の10グループを編成し、2年生が活動をリードして秋の自然を楽しみました。
主に取り組んだ活動の1つは、「クイズラリーで里山散策」です。子どもたちは、7・8人のグループで、8つのチェックポイントのクイズを解きながら、ゴールをめざしました。「切り株にある輪の数が木の歳だから、イの方が若いんだよ。」…など、相談しながら答えを書いていきました。2つめの活動は、「里山生きもの観察」です。草むらにいる昆虫と水辺の魚・イモリなどを、自分たちで捕まえました。それぞれの生きものの特徴を、実物を見ながら学ぶことができました。
子どもたちは、「イモリの腹の模様で見分けられるんだ!」 「歩いて手を出すと、トンボが捕まえられた!」 といった感想をもちました。秋の里山を満喫できた子どもたちでした。
|
|
|
| 2019年10月18日(金) |
| 6年生、そなえ館で防災の学習をしてきました |
 |
 |
|
本日、6年生が小千谷市上ノ山にある「おぢや震災ミュージアムそなえ館」に行って、防災について学習してきました。テレビ局や新聞社の人たちも、子どもたちの学習の様子を取材に来ていました。
まず、子どもたちは、中越大震災のデータを基に、地震の怖さやライフラインの大切さ、避難所での生活の様子などを、クイズに答えながら学習しました。次に、大がかりな「地震シミュレーター」等を使って、地震の疑似体験をさせてもらいました。子どもたちは、その揺れの大きさと実際に倒れる家具の映像などにとても驚いていました。
その後、語り部の方から「想定外を想定して命を守る」というテーマのお話を聞きながら、グループワークで感想や意見の交流をしました。
今日の学習で、子どもたちは「実際の写真を見て、地震の怖さが分かった。」「耐震工事の大切さを、家族にも伝えていきたい。」などの感想をもちました。生涯に渡って、「想定外を想定して、自分や大切な人たちの命を守れる」ようになって欲しいと思います。
|
|
|
| 2019年10月16日(水) |
| 留学生の人たちと交流しました |
 |
 |
|
本日、小千谷市国際理解教育推進事業の一環として、3人の外国の方が、当校に来てくださいました。アメリカ出身の方1名と、イギリス出身の方2名です。各学年1時間ずつ、外国の方々と楽しみながら交流する学習を行いました。
中・低学年は、3人の方々のパソコンを使っての自己紹介と、それに対する質問のやりとりを中心に、コミュニケーションを楽しみました。また、高学年は、自己紹介の他にも、自分たちの取り組んでいるシャギリや木遣天舞を披露したり、英語で自己紹介したり、小千谷市や片貝町を紹介したりして、今までの学習の成果を確かめました。
活動を通して子どもたちは、「外国でも日本のマンガとかアニメが有名なんだね。」「イギリスって4つの国からできてるんだ。」…といった感想をもちました。異文化交流にもなり、とても良い体験になりました。これからもものおじせず、積極的に人とかかわれる人間になって欲しいと思います。
|
|
|
| 2019年10月15日(火) |
| 東京片貝会教育講演会に6年生が参加しました |
 |
 |
|
先週金曜日の午後に、東京片貝会主催の教育講演会が開催されました。講師は、片貝中学校の卒業生である安達ロベルトさんでした。写真家、作曲家、アーティストでいらっしゃるロベルトさんから、片中生と片貝小6年生・町内の方々が、お話とピアノ演奏を聞くことができました。
ロベルトさんは、「ノイズがアートをつくる」という演題で、50歳の花火を一緒に揚げた「一心会」の写真と共にピアノを弾いたり、同級生の演奏するシャギリの「にへんがえし」の曲に、ピアノで伴奏をつけたりしてくださいました。「自分も片貝にとっては『ノイズ』だったかもしれないけれど、今はそんな自分も居場所が見つかった気がする。」と、熱いメッセージをくださいました。
3人の感想発表では、「自分の個性(ノイズ)を大事にしながら、自分の将来を考えていきたい。」などの感想がありました。一人一人が自分の将来を考える、大切な機会になったと思います。ありがとうございました。
|
|
|
| 2019年10月10日(木) |
| マラソン記録会、みんなががんばりました! |
 |
 |
|
一昨日雨のため延期したマラソン記録会を、今日青空のもと、実施することができました。一人一人の子どもたちが、自分のめあてに向かって、一生懸命走りました。
「ぼく、この前よりも○○秒も速くなったよ。」「○○さん、新記録でたんだって!」…ゴールした後、教師のところに、自分の記録を聞きに行く子どもたちがたくさんいました。仲間と競い合いながら、タイムを格段に縮めるすてきな姿がたくさん見ることができました。学校全体としても、新記録が2年男子と6年男子、タイ記録が1年男子と4年男子で更新されました。
ほとんどの子どもたちが自分のベスト記録を更新し、充実感とともに記録会を終えることができましたのも、平日にもかかわらずたくさんの保護者の皆様に応援に来ていただいたお陰です。ありがとうございました。
|
|
|
| 2019年10月7日(月) |
| 第2回あいさつキャンペーンが始まりました |
 |
 |
|
今日から、2回目のあいさつキャンペーンが、小中連携の一環として始まりました。町内各所で、地域の方や中学生が、子どもたちを見守りながらあいさつしてくださっています。
先週の金曜日には、片貝中生徒会の代表がキャンペーンの意識付けに来てくれたり、あいあい委員会から「ベストあいさつグランプリ」の取組の説明をしたりしました。①元気でおおきな声②明るい笑顔③相手の目を見る、を重点にあいさつをします。
相手を大切に思う気持ちも、あいさつと一緒に届けられるといいと思います。キャンペーンの期間に限らず、ずっと続けて欲しいと願っています。
|
|
|
| 2019年10月4日(金) |
| マラソン記録会の練習、がんばっています! |
 |
 |
|
9月下旬から始まったマラソン練習、朝活動の時間や体育の時間を使って、全校で取り組んでいます。朝活動の時間にはグラウンドで、スポーツ委員会が準備した音楽に合わせて、8分間走をしています。
今日は2限に、1年生と6年生がマラソンの合同練習をしました。6年生が走る時は、1年生が「掃除の班長、○○、かんばれ~」などの声援が、ひっきりなしに飛びます。また、1年生が走る時には、速い6年生の男子3人が伴走についたり、ゴールで1年生の世話をしたりしてくれました。それぞれの学年にとって、とても意味のある練習会になりました。
来週10月8日(火)が、マラソン記録会当日です。一人一人が、3つの観点(①めざすタイム②自分のライバル③めざす順位)から、自分のめあてをしっかりもって、チャレンジして欲しいと考えています。
|
|
|
| 2019年10月3日(木) |
| 5年生、就学時健康診断のサポートをしました。 |
 |
 |
|
昨日、来年度1年生に入学する子どもたちの就学時健診が、午後にありました。前日に「ぼくが年長の頃に行ったとき、優しく笑顔で案内してくれたので、とても楽しくいられました。次は僕の番なので、がんばりたいです。」と、日記に書いていた5年生もいました。
そして当日は、来年度6年生になる5年生が、本当に活躍してくれました。受付でのお迎えから、各種検査場所への移動など、一人一人に5年生がついて、優しくサポートしました。長い待ち時間には図書室で「読み聞かせをしてくれました。
サポートが終わった後、5年生の子どもたちは、「春に新1年生が入学したら、もっと仲良くなりたいです。」といった感想をもちました。来年度も、立派な6年生として活躍してくれることでしょう。
|
|
|
| 2019年9月30日(月) |
| 2年生、動物とふれ合ってきました! |
 |
 |
|
9月27日(金)に、2年生は、長岡市の関原にある「動物愛護センター」に行ってきました。
最初に、愛護センターの方からセンターの役割や、保護された犬や猫の数、兎やモルモットとの上手なつきあい方を教えてもらいました。その後、実際に一人一人が、モルモットや兎を抱いたりなでたりさせてもらいました。
また、「ゆっくり手をグーで近付けて、犬がにおいを嗅いで、なでていいよとなってから触ってね」と教えてもらった後、実際に犬を触らせてもらいました。他にも、リードにつながれていない犬に出会った時の対処法なども、実際に体験しました。
動物を飼う前に、自分が責任をもって「命」を最後まで大事にできるか、考えらる子どもたちになって欲しいと思います。
|
|
|
| 2019年9月27日(金) |
| 片貝小・中学校保健員会講演会がありました |
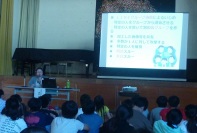 |
 |
|
9月26日(木)の午後に、祖父母参観と片貝小・中学校学校保健員会講演会がありました。講演会には、片貝小5・6年生と片貝中1年生、祖父母の方とPTA役員の方々が参加しました。
前半は、弁護士の方から「スマホやインターネットに潜む危険性」という演題で講演してもらいました。豊富な事例をもとに、個人情報の管理、ネットで人と知り合うことの危険性、ネットいじめなどについて、お話いただきました。子どもたちは「気をつけないと、人を傷つけたり、事件に巻き込まれたりすることもあるんだな」と感じました。また、後半のワークショップでは、5・6年と中学1年生が混ざってグループを作り、メディアの観点から生活の見直しをしました。一人一人が自分の考えを付せんに書いた後、中学生のリードで、グループの意見をまとめたり発表したりしました。
事件等に巻き込まれたりメディア依存症になったりしないように、自己管理能力を身につけていって欲しいと考えます。
|
|
|
| 2019年9月25日(水) |
| 5年生、音楽朝会をリードしました |
 |
 |
|
今日の朝、5年生主催の音楽朝会がありました。最初、みんなの呼び声に応えて「歌のお兄さん」が登場し、世界の各国の言葉を使って、挨拶を交わししました。「歌のお兄さん」もノリノリで、全校をリードしてくれました。
次に、5年生が、見本として「この星に生まれて」を二部合唱で歌いました。途中の独唱もすてきでした。その後、5年生が低音パートを歌い、全校児童できれいなハーモニーを響かすことができました。聞きに来てくださった保護者の方々に、たくさんの拍手をいただきました。
今日の朝会では、他にも、先日実施した市親善陸上大会の表彰や、スポ少野球部の活躍の紹介などもありました。子どもたちの頑張りがたくさん見えた朝会になって、よかったです。
|
|
|
| 2019年9月24日(火) |
| 3年生、製菓工場に見学に行ってきました |
 |
 |
|
先週の金曜日に、3年生は社会科の「ものを作る仕事」の学習で、越後製菓に工場見学に行きました。池津にある片貝工場に、歩いて行ってきました。
まず、子どもたちは、工場の担当の方から会社の概略や、せんべいやあられの作り方の違い、どんなところに気をつけて作っているか、などを教えていただきました。特に、ごみを持ち込まないために服装に気を配っていることを、実際に代表の子どもに着せてもらいながら、教えていただきました。次に、子どもたちは、実際に工場の人がたくさんの機械を使いながらせんべい等を作っている様子を、ガラス越しに見せていただきました。
子どもたちは、「買ってくれた人に、いつもおいしく食べてもらえるように、工夫しているんだな」といった感想をもつことができました。これから見学のまとめをしながら、さらに学習を深めていきます。
|
|
|
| 2019年9月20日(金) |
| 2年生、2回目の町探検に行ってきました |
 |
 |
|
先日、2年生は、グループに分かれて2回目の町探検に行ってきました。今回の行き先は、スーパーと豆腐屋さんと写真屋さんです。それぞれ、見てきたいことや質問したいことを一人一人がもって行ってきました。
豆腐屋さんでは、作り方を教えてもらう中で、豆腐になる前の豆乳を飲ませてもらいました。また、写真屋さんでは「ぼくたちの卒園写真が飾ってある!写真を撮りに来てくれていたんだね」とびっくりしました。
子どもたちは、それぞれのお店屋さんを見学する中で、お店の人たちの工夫や気をつけていること・頑張っていることを知ることができました。これから、それぞれのお店の特徴をまとめて、発表につなげていきます。
|
|
|
| 2019年9月19日(木) |
| 6年生、親善陸上大会をんばりました |
 |
 |
|
昨日、9月18日(水)に市親善陸上大会が行われました。10時頃まで強い雨が降り、グラウンドコンディションが良くない中でしたが、役員の皆様のお陰で最後まで実施することができました。
6年生の子どもたちは、今まで練習してきた自分の出場種目に全力で取り組みました。仲間が一生懸命応援する中で、ほとんど子どもたちが、自己ベストを出すことができました。詳しい結果については、学校だより等をご覧ください。
子どもたちは「みんなの応援で、がんばって走ることができた」「途中で滑ってしまったので、走れるならもう1回走りたい」といった感想をもちました。これからの日常生活でも、集中力を発揮して、充実した学校生活を送って欲しいと考えます。
|
|
|
| 2019年9月18日(水) |
| 5年生、稲刈り体験をさせてもらいました |
 |
 |
|
9月17日(火)に、5年生は総合学習「達人に学ぶ」の一環として、稲刈り体験をさせていただきました。雨上がりの気ぜわしい中、稲の刈り方とまとめ方を教えていただいた後、実際に一人一人が刈り始めました。
稲の露を払いながら、一束一束丁寧に刈って、いくつかまとめてしばります。そして、脱穀しやすいように田んぼの外にまとめて運びました。「刈り残しの穂や落ちている穂も、集めてね。」と言われ、運んでいる途中で落ちてしまった穂を、さらにみんなで拾いました。
子どもたちは「稲刈りは、力を合わせてやる仕事なんだな」「お米一粒一粒を大切にしていきたいな」といった感想をもちました。魚沼米の収穫を体験させていただき、子どもたちは農家の人たちの苦労と喜びの一端を知ることができました。
|
|
|
| 2019年9月17日(火) |
| 4年生、ごみ清掃工場等の見学に行ってきました |
 |
 |
|
9月13日(金)、4年生は、清掃工場とリサイクルセンターに、社会科の見学で行ってきました。「ごみの行方」の学習で、ごみがそれぞれの場所でどのように処理されているか、教えていただいたり、実際に見せていただいたりしました。
時水の清掃工場では、ごみ焼却炉の仕組みやごみの量だけでなく、実際にクレーンを使ってごみポットから焼却炉に入れる様子や、中央管制室でごみの燃焼を24時間コントロールしている様子なども見せてもらいました。また、大原のリサイクルセンターでは、リサイクルごみや埋め立てごみが、ベルトコンベアで自動的に分別さたり、手作業で再分別されたりしている様子なども見ることができました。子どもたちは「多くのごみが出ているんだな。」「水と同じように、繰り返し使われているんだな」といった感想をもちました。
子どもたちは、最終処分場で燃焼灰などを埋め立てている様子も見せてもらいました。これから見学をまとめながら、さらに学習を深めていきます。
|
|
|
| 2019年9月13日(金) |
| まつりの後で嬉しいことがありました! |
 |
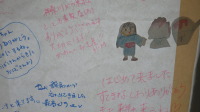 |
|
昨日9月12日(木)に、嬉しいことが2つありました。
1つ目は、図書ボランティアに来てくださった方々からの話です。本の修理をしながら教えてくださいました。「片貝まつりのSNSを見ていたら、県外の方の『知らない私にたくさんの子が挨拶を返してくれたから、是非皆さんも挨拶してね』『止まってくれた車に、登校班の子がきちんとお礼の挨拶をしてくれて、気持ちよかった!』という書き込みがあって、私も嬉しかったです。」外部の方からいただく評価の言葉は、特に重みがあってありがたいです。
2つ目は、片貝総合センターの玄関に貼らせていただいた1年生の「片貝まつりしおり」です。返ってきたしおりが貼ってあった台紙には、たくさんの感謝のメッセージが書いてありました。「三重から来ました。かわいいので大切に使います。(^_^)」「初めて来ました。すてきなしおりありがとう。また来年も来るね 。」…今、児童玄関に貼ってあり、全校の子どもたちもメッセージを読んで、とても喜んでいます。
|
|
|
| 2019年9月12日(木) |
| 5・6年生、鼓笛パレードで片貝まつりに貢献! |
 |
 |
|
9月10日(火)の午前中に、5・6年生が片貝まつりに鼓笛パレードで参加してきました。暑い日ざしが照りつける中、1之町のはじから八島の入り口までパレードをしました。
今まで練習してきた4曲を演奏しました。途中、に組総合センターや浅原神社前で静止演奏をしてまつりを盛り上げました。沿道の観光客や保護者の皆さんから、たくさんの拍手をいただくことができました。
この前のまつり屋台曳き回しや今日の鼓笛パレードの他にも、各町内で「小若」などの活動をしている子どもたちもいました。まつりを楽しみながら、片貝町のために活躍し、人の役に立つことのできる自分が自覚できるといいなあと思っています。
|
|
|
| 2019年9月9日(月) |
| 片貝まつり前夜祭が始まりました! |
 |
 |
|
昨日9月8日(日)に、片貝まつりの前夜祭が行われました。その一つとして、子どもたちや伝統芸能保存会の皆さんが中心となって、祭り屋台を一之町から四之町、そして浅原神社まで曳き回しました。
途中の「に組総合センター」で、巫女爺クラブの子どもたちが、3曲を披露して、多くの拍手をいただきました。また、後半の屋台引き回しでは、6年生の子どもたちが、道中木遣りの音頭とりをさせてもらい、周りの子どもたちも、はやしで盛り上げていました。
片貝まつりは、今日・明日と続きます。子どもたち自身が、町内を通じてまつりに主体的に参加し、楽しみながらまつりを盛り上げる体験をして欲しいと思っています。
|
|
|
| 2019年9月8日(日) |
| 1年、片貝総合センターにしおりを届けました |
 |
 |
|
今日、1年生全員で歩いて、片貝総合センターに「片貝まつりしおり」を届けに行ってきました。しおりは、一人一人が朝顔のしぼり汁で染めた紙を折ってはさみで切って、花火のデザインにしました。自分で育てた朝顔を使って、作りました。
総合センターの玄関に、限定40このしおりが、大洋紙に張った状態で飾らせてもらっています。しおりの作品をご覧いただいた後、一人1作品までですが、もらっていただけるとありがたいです。
作品をもらっていただけた方は、できましたら、大洋紙の開いているところなどに、メッセージをいただけると嬉しいです。子どもたちも喜ぶと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
|
|
|
| 2019年9月6日(金) |
| 全校で道中木遣りを教えていただきました |
 |
 |
|
9月5日(木)の5限に、片貝伝統芸能保存会の方々から道中木遣りの唄い方を教えていただきました。今年が3回目ですが、奉納木遣りと全く違った節回しなので、覚えるのが難しいのです。
まずは、保存会の方々に木遣りが復活した歴史を話していただいたり、見本に唄っていただいたりしました。「めでた~ めでた~のや」「いよ~や いよ~いよ~いせ …」独唱の「音頭」の部分と、大人数で唄う「はやし」の部分があります。
そして、6人の音頭取りと、全校で唄う「はやし」に分かれて練習しました。最後は、子どもたちの「音頭」と「はやし」を合わせました。短い時間の練習だったのですが、とても上手になりました。本番の9月8日の前夜祭では、町内の大人の皆様も一緒に唄っていただけるとありがたいです。
|
|
|
| 2019年9月5日(木) |
| 6年、陸上競技場練習に行ってきました |
 |
 |
|
昨日9月4日(水)に、6年生が白山運動公園の陸上競技場で練習を行いました。朝方は雨が残っていて一度は延期を決定したのですが、市教育委員会のご配慮もあり、実施することができました。
子どもたちは、1周400mの競技場の広さと芝生の緑や水はけの良い土などを実感しながら、種目に分かれて練習しました。それそれ基礎練習をした後、タイムトライアルや計測にチャレンジしました。「そう、そのリズムで最後まで行け~」「ラストスパート、しっかり手を振って~!」
今回の自分の記録を土台に、子どもたちは、今後どのくらいベスト記録を伸ばしていけるか、取り組んでいきます。ご家庭でも、「本気で」取り組み続けられるよう励ましていただけるとありがたいです。
|
|
|
| 2019年9月3日(火) |
| 校内科学研究発表会を行いました |
 |
 |
|
今日の2限に中学年、3限に高学年の科学研究発表会を視聴覚室で行いました。それぞれの学年から2~3名の代表が、夏休みに取り組んだ科学研究を発表しました。
「どれが一番溶けやすいか」「ジュースと水の引っ越し実験」「生分解プラスチックの実験」…など、いろいろなテーマがありました。「トビは、3種類の羽で上昇気流をつかまえるから、羽ばたかないでも飛べるのです。…」「エゴマ油で作ったマヨネーズは、サラダ油で作ったマヨネーズと似ていて、僕は5つのマヨネーズの中で、一番好きでした。…」など、研究をまとめてみんなに伝えていました。
それぞれの研究では、比較実験をしたり、グラフにまとめたり、実験から生まれた新たな疑問をもとに追加実験をしたりと、他の子どもたちの参考にもなりました。理科の学習や来年の科学研究等に、是非活かしていって欲しいと思います。
|
|
|
| 2019年9月2日(月) |
| 陸上練習を外でしました |
  |
|
8月は陸上競技練習があった日がずっと雨で、外での練習ができませんでした。しかし、今日は晴れ間を見て、何とか外で練習をしたりタイム計測をしたりしました。
子どもたちは、全体練習でちょっと湿った土の感触を確かめた後、それぞれの種目にわかれました。「1周○○秒平均でいくと、○○秒になるから・・・」長距離のこどもたちは、自分の目標タイムを決めてから、タイムの計測をしました。また、ハードルや走り幅跳びは、土の上でのハードリングや踏み切り板を使っての計測に初めてチャレンジしました。
これからも、天候に左右されながらの練習となります。自分の目標をしっかりもって、限られた期間の練習に真剣に取り組めるよう、支援していきます。
|
|
|
| 2019年8月29日(木) |
| 夏休みの自由研究パート2 |
 |
 |
|
一人一人が取り組んだ夏休みの自由研究の作品が、各教室の廊下に飾られています。休み時間や昼休みなどに、自分の学年以外の作品を見に行く子どもたちもたくさんいます。
「見て、見て!○○さんのはね、クラス全員の顔も描いてある102枚のカルタなんだよ!」…「この人のはね、自動販売機のここからカンが出てくるんだよ」…「僕のはね、モーターとギアが2つずつ付いていて、回転するうちにスピードが速くなるんだよ」…「○○さんの髪留めと小物入れ、とっても丁寧できれい!」
自分もがんばったからこそ、他の人の作品にも興味をもつのだろうなと思います。友達の頑張りにも、温かい目を向けられる子どもたちが多く、嬉しく感じました。
|
|
|
| 2019年8月28日(水) |
| 夏休みの自由研究発表会が行われています |
 |
 |
|
2学期が順調にスタートしました。子どもたちが夏休みに取り組んだ自由研究の発表会が、各クラスで行われています。自分が作ってきた作品を前に、自分が取り組んだこと・作ったもの、がんばったこと、見て欲しいこと、質問への回答などを発表しました。
「たくさんのトンボをつかまえて、昆虫標本を作りました。真ん中に大きなトンボが来るように、工夫しました。…」「屋根の一番てっぺんから玉を転がせて、一番下まで来ると成功です。…」「どうしてスライムにいろいろなものを混ぜようと思ったかというと、…」…など、学年によっても様々な発表がありました。
夏休み中に、家族の皆さんの支援も受けながら、がんばって取り組んだ様子が、それぞれの作品から伝わってきました。きっと、一人一人にとって、充実した夏休みだったことでしょう。ご協力、大変ありがとうございました。
|
|
|
| 2019年8月27日(火) |
| 今日から2学期がスタートしました |
 |
 |
|
今日8月27日(火)に、2学期が始まりました。朝、子どもたちは、夏休みの学習の成果を、たくさん抱えて登校しました。嬉しいことに、今日は欠席0でした。
始業式では、新しく赴任された先生の紹介の後、夏休みに行われた親善水泳大会の表彰を行いました。そして、学年代表の2名の子どもたちが、2学期の決意発表をしました。「算数の計算をがんばりたい」「校歌のピアノの伴奏をがんばりたい」…それぞれ、堂々と発表することができました。
校長講話では、夏休みに登った北アルプスの話から、片貝小の教育目標や2学期の生活期の話をしました。一人一人の子どもが、自分のめあてをしっかりもち、一歩一歩前進して欲しいと思います。そして、子どもたちの「笑顔と真剣な表情」がたくさん見られる2学期になるよう、支援していきたいと思います。
|
|
|
| 2019年8月22日(木) |
| 5・6年、陸上練習が始まりました |
 |
 |
|
夏休み中の8月20日(火)から、陸上練習が始まりました。今年度から、5年生も練習に参加して、朝の時間に3日間行います。
1・2日目は、外部の専門家の方に来ていただき、子どもたちに指導してもらいました。楽しい運動を取り入れながら、走るときに大切なポイントを動きの中で教えていただきました。「背筋を伸ばす、胸を張る、アキレス腱を使ってかかとをあげる…」など、姿勢の大切さです。
2日目からは、種目練習も少しずつ始まりました。2学期に入ると、6年生が出場する親善陸上大会がすぐ迫ってきます。一人一人が自分のめあてをしっかりもち、主体的に練習に取り組んで力を伸ばして欲しいと思います。
|
|
|
| 2019年8月20日(火) |
| 巫女爺子供クラブ、那由多まつりに出演! |
 |
 |
|
8月19日(月)に、小千谷市坪野にあるデイサービスセンター那由多の家の「夏祭り」で、巫女爺子供クラブのメンバーが発表してきました。昨年までも参加させてもらい、今年度も声をかけていただきました。
しゃぎり・唄・踊りに分かれて、子どもたちが3曲を披露した後、片貝伝統芸能保存会の方々も「品玉」という演目を行いました。また、利用者の皆さんの周りを、大花火音頭で踊ったりもしました。 子どもたちは、アンコールをいただいたり、「とっても良かったよ」という感想をもらったりして、満足して発表を終えることができました。他にも、焼きそばや綿あめをもらったり、射的や水風船づりをさせていただいたりと、楽しい思い出になりました。
これから、さらに片貝まつり本番やもみのキッズ学びランドに向けて練習していきます。たくさんの皆さんに見ていただきながら、一人一人の自己有用感を育んでいきたいと思っています。
|
|
|
| 2019年8月1日(木) |
| のびっこ教室、がんばりました |
 |
 |
|
7月30日~8月1日の3日間、のびっこ教室を行いました。国語・算数を中心に、各教室で1学期の復習を行いました。
今年は、エアコンが普通教室に設置してもらっているので、快適な環境の中で学習ができて助かっています。一人一人が集中して、自分のめあての学習に取り組むことができました。ただ、プールの施設の故障のため、イルカ教室ができなくなってしまったことが大変残念です。
いよいよ8月です。残りの夏休みも、楽しく元気に充実した生活を送って欲しいと願っています。
|
|
|
| 2019年7月29日(月) |
| 片貝小らしさの表れた親善水泳大会 |
 |
 |
|
先週7月27日(土)に、小千谷市親善水泳大会が市営プールで行われました。5・6年の子どもたち6人と、4年生以下のスイミングスクールとして出場した3人が出場しました。
それぞれの子どもたちが、自分の今までの限界を超えようと飛び込みやラストスパートなど、自分ががんばるところを決めて取り組みました。「…クロール・背泳ぎ・バタフライ・エビフライ・あじフライ…」子どもたちは、自分たちで考えたオリジナル応援で、自校の仲間だけでなく他のがんばっている他校の子どもたちも応援しました。
個人種目やリレーなど、ほとんどの種目でベスト記録が出たことと同時に、どこの学校にも負けない応援ができたことが片貝小らしさだと感じています。来年度は、さらにたくさんの子どもがチャレンジできるように、支援していきます。
|
|
|
| 2019年7月26日(金) |
| 1学期が無事終了しました |
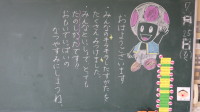 |
 |
|
昨日の7月25日に、1学期の終業式がありました。各クラスで1学期を振り返った後、担任から通知表が一人一人に渡されました。一人一人の成長はもちろんのこと、クラスとして大きな成長も見られました。
4限の終業式では、校長が、子どもたちの活躍している1学期の写真をたくさん見せました。子どもたちは、自分や友達の笑顔や真剣な表情を見ながら、充実した1学期を振り返ることができました。
いよいよ今日から夏休みです。安全・安心で楽しい夏休みを過ごして欲しいと思います。そして、8月27日(火)の2学期始業式には、子どもたち全員が元気な姿を見せて欲しいと願っています。
|
|
|
| 2019年7月25日(木) |
| 朝Englishに、英語で読み聞かせ |
 |
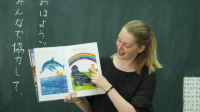 |
|
ALTの先生が朝からいらっしゃるときに、「朝English」で英語の本の読み聞かせをしてくださっています。昨日は、3年生の教室で行われました。
英語で書かれている絵本を、全部英語で読んでくださるのですが、ときどき子どもたちが聞き知っている外来語が出てきます。「ドルフィンって、イルカかな?」「フラミンゴは、そのままフラミンゴだよね」・・・。
絵本の絵とALTの先生の発音を手がかりに、本のあらすじを類推します。子どもたちも集中して聞いていると、内容がなんとなく分かります。ネイティブの英語を身近に聞く機会を、これからも大切にしていきたいと思います。
|
|
|
| 2019年7月24日(水) |
| 6年、理科で魚の解剖にチャレンジ |
 |
 |
|
7月23日(火)に、6年生は理科「体のつくりと働き」の学習で、魚の解剖を行いました。人間の体について学習した後、他の動物でも、似たようなつくりがあるか、を実験で確かめました。
子どもたちは、一人一匹の魚を丁寧に解剖しました。「やっぱり、消化管が口から肛門までつながっているんだ」「胃の中に、まだ消化されていない虫がいた!」とびっくりしていました。
動物の体は、生きていくための様々な機能が組み合わさっていることや、呼吸や消化・血液の循環など、多くの点で動物の体に共通点があることに気づくことができました。
|
|
|
| 2019年7月23日(火) |
| 育てている植物、随分大きくなりました |
 |
 |
|
各学年が春に植えた植物も、大分大きく育ってきています。6年生のジャガイモは、実験を終えてすでに収穫されました。今年は今のところ、どの学年も順調に育っています。
朝学校に来ると、低学年の子どもたちは、学年園に行って水をやります。そのおかげか、1年生の朝顔がどんどん花が咲いています。2年生の野菜もでき始めました。3年生のひまわりは、3mを越しました。
夏休みに植物を家に持って帰る学年や、学校まで収穫に来る学年もあります。「命」ある植物を最後まで世話できるよう、支援していきたいと思います。
|
|
|
| 2019年7月22日(月) |
| 昆虫標本ガイダンスがありました |
 |
 |
|
夏休み中に昆虫採集にチャレンジしたい子どもたちが、今日の昼休みに会議室に集まりました。30人ぐらい集まりました。子どもたちは、事前に保護者の方と相談してOKをもらってあります。
担当してくれる職員から「少なくとも20匹くらい、捕まえられるといいね」「捕まえた昆虫は、冷凍庫の中に入れます」・・・といった、手順や道具についての話がありました。
いよいよ夏休みは、今週末からです。昆虫採集に限らず、一人一人が、充実した夏休みを送って欲しいなと思います。
|
|
|
| 2019年7月19日(金) |
| 1学期のまとめの町内子ども会 |
 |
 |
|
今日の3限に、それぞれの町内に分かれて、町内子ども会を行いました。1学期の登校班の反省と、夏休みに向けての各町内の行事等を確認しました。
まずは、各登校班ごとの振り返りです。集合時刻やあいさつ・交差点の渡り方等の、どんな点がよかったかまたは悪かったか、意見を出し合いました。次に、夏休みのラジオ体操や町内行事・町内水泳などの日時や場所などを、確認しました。
1週間後には夏休みが始まります。一人一人が登校班等の1学期のまとめをしっかりするとともに、安全で楽しく・規則正しい夏休みになって欲しいと願っています。
|
|
|
| 2019年7月18日(木) |
| 4年、音楽朝会をおこないました |
 |
 |
|
今日、7月18日(木)に4年生主催の音楽朝会がありました。後ろにはたくさんの保護者の皆さんが、見に来てくださっていました。
最初に、本家「歌のお姉さん」が登場して、世界の言葉で「おはよう」の挨拶をみんなでしました。そして、次は4年生の歌と合奏による「子どもの世界」の発表です。元気な歌声が、体育館に響きました。
そして、4年生が、学年ごとにサビの部分の振り付けを教えてくれました。最後に、全員で「子どもの世界」を振り付きで楽しく歌うことができて、よかったです。次回は、5年生の発表です。
|
|
|
| 2019年7月17日(水) |
| 着衣泳教室を実施しました |
 |
 |
|
7月16日(火)、低・中・高学年に分かれて着衣泳を実施しました。暖かい日差しの中、ゲストティーチャーの方から教えていただきながらプールに入りました。
低学年の子どもたちは、「水に入っただけで、とっても動きづらい。」「体が重くて、水から上がれないよ。」と、自分の体験を基に話していました。水の中に落ちた時の怖さを、実感したようです。
そして、ペットボトルを使って浮く練習をしました。何回か繰り返すうちに、上手に浮ける子どもがどんどん増えてきました。夏休みを迎える前に、自分の命を守るための貴重な体験になりました。
|
|
|
| 2019年7月16日(火) |
| 6年生、 社会科授業研究会がありました |
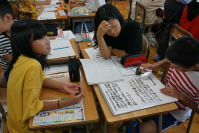 |
 |
|
先週の金曜日に、6年生社会科の授業研究会がありました。「幕府の政治と人々の暮らし」という江戸時代の学習を行いました。修学旅行でも訪れた佐渡金山が、江戸幕府にとってどんな場所であったかを考えました。
子どもたちは、幕府が佐渡で小判を作った根拠を、三つの資料から探し、話し合いました。「他の金山と比べて、たくさんの金が出たからだ」「海も渡り、江戸までの輸送が20日間もかかって、大変だったから」・・・
他のグループの発表や他の資料からも、佐渡金山が幕府にとってとても重要な場所だったので、佐渡を直轄地にしていたことが子どもたちも理解することができました。
|
|
|
| 2019年7月11日(木) |
| 5年、救急法講習会を行いました |
 |
 |
|
今日の5限に、5年生は、消防署の方から救急法講習会をしていただきました。最初に、実際にあったできごとを基にしたビデオを見ました。亡くなってしまった方や、AEDのおかげで助かった方々の写真を見ながら、救急法の大切さを学びました。
次は、具合の悪くなった人が出た場合の、救急車の呼び方を練習しました。何人かの代表の子どもたちが、消防署員の方と実際に会話をしながら、落ち着いてたくさんの情報を伝えました。
さらに、グループごとに人形を使いながら、胸骨圧迫とAEDの練習も行いました。実際の時は、心臓マッサージをしながら届いたAEDを装着して,救急隊が到着するまで続けることを教えてもらいました。
命の大切さを活動を通して学ぶ、大事な学習になりました。
|
|
|
| 2019年7月10日(水) |
| 3年、学級活動の公開授業を行いました |
 |
 |
昨日、今年度最初の校内授業研究会が行われました。3年生の学級で、「クラス会議」の様子を教職員が参観し、放課後協議会をもちました。
「子どもたちは、自分たちのクラスの課題について、一人一人が自分なりの意見をしっかりもって、話し合いが進みましたね。」「一人→グループ→全体、という他の子と関わり合うなかで、お互いを認め合おうとする姿が、少しずつ出てきていました」「時間が足りなかったので、時間配分を考えると良いと思います」・・・等、様々な意見が出されました。そして、成果と課題が明らかになってきました。
今後も、お互いの授業を公開することを通して、教職員が自分の授業力アップに、全校で取り組んでいきます。 |
|
|
| 2019年7月8日(月) |
| PTA救急法講習会を実施しました |
 |
 |
|
先週7月5日(金)に、PTA救急法講習会が行われました。今年度の町内プールの監視者に当たっている方々が、南運動場に集まりました。そして、PTA保体部の方が講師をやってくださいました。
人工呼吸と心臓マッサージ、AEDを使った心肺蘇生法です。体育館に電子音のリズムが流れる中、参加者全員が、交代交代に行いました。保体部の皆様からは、消防署の事前講習を受けていただき、当日も講師役をやっていただきました。誠にありがとうございました。
今年の夏の町内プールも、安全で楽しく実施できるように、学校でも指導していきたいと思います。
|
|
|
| 2019年7月5日(金) |
| 一日フリー参観、ありがとうございます |
 |
 |
|
7月5日(金)に、一日フリー参観を行いました。午前からたくさんの保護者の皆様から参観に来ていただき、ありがとうございました。
それぞれの学年の、様々な学習している姿を見ていただきました。一人一人の子どもが、春から随分成長している姿を見ていただけたのではないでしょうか。
午後にも授業参観と学年懇談会、救急法講習会と続きました。安全・安心な夏休みになるよう、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
|
|
|
| 2019年7月4日(木) |
| 七夕かざりを作ろう! |
 |
 |
|
パワーアップ1組の子どもたちの呼びかけで、7月2・3・4日の昼休みに、七夕かざり作りをしました。希望する子どもたちが、はさみとノリをもってパワーアップ1組に集まりました。
材料がそろえてあり、いろいろなかざりの作り方が紙に書いてあったり、実際に説明したりしてくれました。集まった子どもたちは、自分で作ったいろいろな種類のかざりをつなげて楽しみました。
できたかざりは、自分の家にもって帰りました。今年の七夕は、日曜日。大雨で水害が心配される地域も、天気が良くなるといいですね。
|
|
|
| 2019年7月2日(火) |
| 浄水場見学に行ってきました |
 |
 |
|
4年生は、7月1日(月)に社会科の学習で、小千谷浄水場と北部取水場に見学に行ってきました。学校で蛇口の数を調べた子どもたちは、「たくさんの水を、どこでどのようにつくっているのだろう」という問いをもって出かけました。
浄水場では、信濃川の水をきれいにしていくための施設や方法などを、実際に見ながら教えてもらいました。「片貝の水は井戸水を使っているので、冷たくておいしい」ということも、分かりました。
子どもたちは、安全でおいしい水を安定して作り出すための所員の方々の工夫と努力の一端を知ることができました。今後はさらに、水道水の秘密を探るともに、水を大事に使っていくことでしょう。
|
|
|
| 2019年7月1日(月) |
| 講師をお招きしての放射線教育 |
 |
 |
|
先週、6年生は、外部講師をお招きして、放射線について学びました。放射線の基礎知識を教えてもらった後、身の回りのものからも放射線が出ていることを、自分たちで計測しながら知ることができました。
また、放射線にはいろいろな種類があることや、どのくらいの放射線の量に当たるかが体にとって重要であることなどを教えてもらいました。
日常的に放射線の情報を得る事ができることも、教えてもらいました。もしもの事態の時にも、冷静に対処できることを目指していきたいと思います。
|
|
|
| 2019年6月27日(木) |
| むし歯予防教室を行いました |
 |
 |
|
今年度も、6月27日(木)に学校歯科医さんから、3年生の子どもたちにむし歯予防教室をしていただきました。噛むことが健康にとって大変大事なことや、むし歯ができる仕組み、むし歯を予防するための方法などを教えてもらいました。
そして、歯の上手な磨き方を歯科衛生士さんから、実際に教えていただきました。子どもたちから「むし歯になりやすい歯の場所がよく分かった!」「寝る前の歯みがきを、特にがんばりたい」といった感想が聞かれました。
6月は、歯の衛生月間ですが、今月に限らず、これからの生活に是非活かしていって欲しいと願っています。
|
|
|
| 2019年6月26日(水) |
| きれいな歌声が響いた音楽朝会 |
 |
 |
|
6月26日(水)に、6年生が担当した音楽朝会がありました。6年生の「歌のお姉さん」のリードのもと、リズムに合わせて”あいさつ”をして朝会が始まりました。
そして、「翼をください」を、まずは6年生がきれいな2部合唱で聞かせてくれました。独唱も含めたきれいな歌声に、全校の子どもたちは「さすが、6年生!」の思いを強くしました。
その後、全校で「翼をください」を、2部に分かれて歌いました。とても素敵な歌声に、聞きに来てくださっていた保護者の皆様も、笑顔になりました。とても、気持ちのよい音楽朝会になりました。次回の4年生の音楽朝会も、楽しみです。
|
|
|
| 2019年6月25日(火) |
| 講師の方を招いて水泳教室 |
 |
 |
|
6月25日(火)、5・6年生は外部の講師の方をお招きにして、水泳教室を行いました。先々週、悪天候のため延期しましたが、今回は何とか実施することができました。クロールの姿勢や手のかき方を教えてもらったり、平泳ぎの脚を練習したりしました。
「手は耳の後ろだよ」「まず、かかとと小指を壁に付けます。・・・」と、具体的に教えていただきながら練習しました。子どもたちからは「平泳ぎの脚は難しい~!」といった感想が聞かれました。
来週、2回目の水泳教室が予定されています。専門家の方に教えてもらうことによって、さらに上達することでしょう。
|
|
|
| 2019年6月21日(金) |
| 5年生、自然教室に行ってきました |
 |
 |
|
5年生は、6月19・20日と妙高青少年自然の家へ自然教室に行ってきました。妙高アドベンチャーや野外炊飯、キャンプファイヤー、源流体験などたくさんの体験活動を行いました。
仲間と協力しながら、失敗を乗り越えたところに成長があることを実感できた2日間でした。様々な活動や親元を離れて宿泊する体験を通して、一回りたくましくなって戻ってきたひまわり学年です。
|
|
|
| 2019年5月10日(金) |
| <3年生>スポフェスに向かって応援練習スタート! |
 |
 |
|
月曜日の朝活動から、応援団が3年生の教室に来て、応援歌を教えてくれました。休日疲れなんて感じさせない元気な声で練習に取り組んでいました。片貝小学校の子どもたちは、元気でやる気があって最高ですね。普通最初の応援練習では、教師が「もっと声を出しなさい!」なんて小言を言ってしまいがちですが、そんなことは言う必要はありません。片貝小学校の伝統のすばらしさを感じたひとときでした。
|
|
|
| 2019年5月9日(木) |
| <6年生>一年生を迎える会 |
|
|
|
| 2019年4月5日(金) |
| 平成ラストの年度、スタートです。 |
 |
 |
|
4月5日(金)、31年度の新任式と1学期の始業式が行われました。
新任式では、新たに9名の職員を迎え、全校のみんながそれぞれの自己紹介を真剣に聞いていました。
今年度も片貝小WEB日記をどうぞよろしくお願いします。
|
|
|
|
|