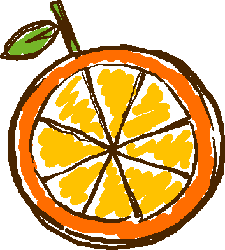 |
|
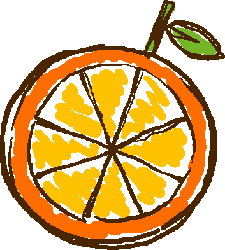 |
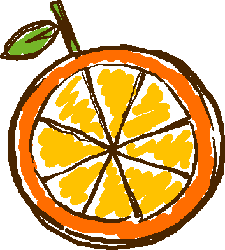 |
|
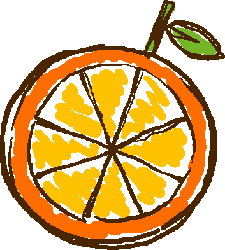 |

| 5月15日、出張授業「写真と言葉で『想い』を届けよう」がありました。 前日の午後から20人以上の方が東京から学校にいらっしゃり、会場となる視聴覚室に机を運び込んだり、プリンターをセッティングしたり、校舎周りを撮影したり、当日の撮影の構図を確認したりと、大がかりな準備が行われました。 当日は、県内のメディア関係の方も加わり、およそ30人の方々に囲まれての学習になりました。 まず、学習の進め方の説明を受け、次に、デジカメの操作方法を教えてもらいました。そして、いざ、撮影へ。お天気が少し心配でしたが、幸いにも曇り。眩しすぎず、ちょうどよかったようです。ブランコやターザンロープ、滑り台などの遊具を使ったり、なかよしの坂を背景にしたりしながら、いろいろな構図で撮影しました。 そのあと、視聴覚室に戻り、プリンターの操作方法を教えてもらい、写真を選んで、メッセージを書き込みました。メッセージは「手書きナビシート」(画像が薄く印刷されている紙)に書き込みました。それをスキャンすると、フォトレターのできあがりです。 できあがったフォトシートをみんなに見せ、誰に書いたのか、どんな気持ちで作成したのかなどを発表しました。 デジカメやプリンターの操作方法が覚えられたことももちろん、感謝の気持ちを表す方法が1つ増えたこと、そして、スタッフの方々のプロとしての仕事ぶり等学ぶことがたくさんありました。 |
 |
 |

| 5月25日、オレンジ学年にとって最後になるスポーツフェスティバル(=運動会 以下「スポフェス」)がありました。 ゴールデンウィークが終わると、本格的にスポフェスの準備や練習が始まりました。お天気に恵まれ、順調に進んでいました。しかし、直前の週は、全体練習こそできたものの、その後の3日間は雨で、グラウンドでの最終練習ができないものが多くありました。鼓笛に至っては、お天気のめぐりが悪く、当日朝、初めてグラウンドで練習したという状況でした。 しかし、子どもたちは見事にやってくれました! 鼓笛も、当日朝、1回だけしか練習できなかったとは思えないほどのできばえだったと思います。総指揮の子は、あいさつの中で、「夢」「進化」という言葉を使って、自分の思いを語ってくれました。6年生は、事前にそのあいさつを聞いています。その思いに賛同し、共感を覚え、鼓笛練習に取り組んできました。「夢」「進化」は、鼓笛練習に留まらず、これからも大切にしていきたいと思います。 |
 |
競技を振り返ると、騎馬戦では赤が2連勝しました。でも、実は、騎馬戦の練習では、赤は1度も勝つことができませんでした。練習後、赤は作戦会議を開きました。それが功を奏したのか、本番では、赤の2連勝という結果になりました。
リレーでは、白バトンに転倒者が出るというアクシデントがありましたが、タイムは、4チームとも、ベスト記録を大幅に更新するという結果でした。1位のチームはもちろん、4位のチームもタイムを聞いて、みんなが喜んでいました。その様子は、グラウンドにいた全ての人が目にした光景です。ある先生が、「感動して、涙が出そうになった。」と話してくれました。
発表された得点だけを見ると、赤組の先行逃げ切りのようですが、実はそうではありませんでした。
競技では、午後に入るとすぐに白が逆転したそうです。そのあと、また赤が逆転するというシーソーゲームでした。騎馬戦だけでなく、練習とは違う結果がでた競技も複数あったそうです。ある先生はスポフェスのことを「メイクドラマ」と評していました。
応援では、応援合戦で、午前も午後も、1点差が赤が勝ちましたが、競技中の応援では、白が勝っていました。それだけいい勝負だったということです。また、片貝小学校に数年いらっしゃるある先生が、「今までで一番おもしろい応援合戦だった。話してくださいました。応援団だけでなく、みんなで心を一つにしてがんばった成果です。
 |
 |
実行委員会では、実行委員長だけでなく、オレンジ全員が、6年生として自分の仕事を立派に成し遂げてくれました。今年から片貝小学校に勤めているある先生は「6年生のリーダーシップがすごかった。」と話してくださいました。目立つところだけでなく、影での、縁の下での準備もありました。別の先生は「6年生が仕事を進めてくれるからから助かる」と話してくださいました。この様子は、4、5年生もしっかり見ていたはずです。来年のスポフェスでは、オレンジの仕事ぶりを思い出しながら、実行委員会の仕事を進めてくれることでしょう。オレンジたちが先輩方から受け継いだ伝統をしっかり引き継ぐことができました。
これらのことから、いえ、これらだけではなく、みんながあまり知らないところでもメイクドラマがあり、縁の下の力もちがいたことでしょう。スポフェスが大成功だったことも大きい成果ですが、スポフェスを通して子どもたちが成長、進化したことのほうが大きい成果かもしれません。総合優勝を赤に取られた白の団長英俊さんが最後に「楽しかった」と言っていました。それだけ充実したスポフェスと言えるのだと思います。今年のスポフェスは、間違いなく、「みんなが主役 汗と感動 世界一のスポフェス」でした!

6月12・13日、修学旅行で佐渡に行ってきました。
修学旅行のスローガンは、「オ・レ・ン・ジ」(お客さんに迷惑をかけない れんたいかん きけんなことはしない じかんを守る)。でした。また、「佐渡の文化に触れ、歴史に学ぼう!」「めざせ!
世界一の修学旅行!!」「そして、オレンジは進化する!!!」という目標も掲げ、修学旅行に行ってきました。
お天気が心配されましたが、日頃の行いのよさからか、バスに乗っているときは雨が降っていても活動を始めると雨が止むなど、全ての活動を予定通り行うことができました。また、佐渡の歴史や文化、そして社会のルール等もしっかり学んでくることができました。
 <たらい舟> 班毎にたらい舟に乗って、交代でたらい舟を漕いでみました。同じところをぐるぐる回ったり、後ろに進んだりとなかなか上手く漕げませんでしたが、岸壁に生息している貝などを観察することもできました。 |
 <漁船遊覧> 漁船で港を出て、海岸沿いに遊覧しました。少し雨が降っていましたが、海底の様子を見ることもできました。また、岩の海岸が多く、自然の創る造形美も堪能しました。洞窟にも入ってもらい、神秘的な雰囲気も味わえました。 |
 <イカ裂き> まず、イカの胴に包丁を入れ、胴を真っ二つに裂きます。次に、目と内臓を取ります。そして、真水で洗い、塩水を通したものを網の上で干します。 一夜干しされたイカは、翌週、学校に届きました。とてもおいしかったです。 |
 <砂金採り> 旅行会社の方は、当初、中級コース(人工の川の中で砂金採りをするコース)を設定してくださいましたが、子どもたちの要望で初級コース(水深5㎝程度のプールの砂の中から砂金採りをするコース)に変更しました。理由は、砂金をガッポリ採りたいから。みんな夢中になって、時間いっぱい砂金を探しました。さて、結果は...!? |
 <刺し網> 地元の漁師さんが、前日、仕掛けてくださった刺し網を引き上げます。真鯛やトビウオなどが捕れました。水揚げした魚は、夕飯に刺身や魚の唐揚げにしてもらいましたが、食べきれないほどの量になりました。自分たちで水揚げしたものだと思うと。より一層おいしく感じました。 |
 <佐渡金山> 佐渡金山の資料はたくさんありましたので、事前にある程度、学習することができました。そして坑道の中で、復元された道具などを見たり、坑道の中の涼しさ(年間と通して11℃)を肌で感じたりして、金山で働く人の苦労を実感できたようです。 実は、子どもたちの一番のお目当ては12.5㎏の金塊。ガラスのケースに入っている金塊を直径10㎝程度の丸い穴から取り出すと、記念品がもらえるとか。みんな必死にがんばりました。しかし、12.5㎏とは予想以上に重く、さらに掴みにくく、残念ながら全員失敗...。この日の金の値段は、1gおよそ4,500円。子どもたちは、5,600万円以上の金塊に触ったのです! それだけでもすごいことですね。 |
 <佐渡奉行所跡> テレビの時代劇でしか見たことのない奉行所。テレビの時代劇も番組数があまり多くないため、行く前は子どもたちもあまり興味を示していない様子でした。しかし、佐渡奉行所は、テレビで見る奉行所とは、ちょっと違いました。裁判所のような役目も果たしていましたが、何よりも、佐渡で採れる金銀を管理するために置かれた奉行所でした。ですから、金銀を精製する工場(勝場=せりば)の様子も復元されており、作業を体験することもできました。子どもたちにとっては、予想以上に学び多い見学となりました。 また、今の奉行所跡は、日本で唯一、以前の場所に復元されたとのこと。ほかにも、 「大人たちは勘違いしていることもあるが、子どもたちには正しい認識をもってほしい」と説明された方の熱い思いが子どもたちに伝わったようです。 |
 <無名異焼> 佐渡金銀山の山中より産出する酸化鉄を含む赤土を無名異と言い、それに粘土を混ぜたもので形成します。無名異は、粒子が非常に細かいため、焼き上がると約3割も収縮します。そのため非常に硬く、たたくと澄んだ金属音を発し、使用するに従って光沢を増してきます。無名異は元来、薬効にすぐれており、中風・胃腸病・やけど・止血剤などに効果がありました。また、無名異焼の器は、お茶、酒、ビール、コーヒーなどの味がおいしくなると注目を集めているそうです。 今回、子どもたちが挑戦したのは手びねり。お茶碗やカップ状のものを作るのは難しい(割れやすい)ため、お皿状のものを作りました。出来上がるのは、1か月半後。ガイドさんによれば、焼く前よりも焼き上がったもののほうが味わい深いよい作品になるとか。送られてくるのが楽しみです。 |
 <ときの森公園> ときが自然界に放鳥されて8年目。自然界での雛の誕生も3年連続で確認されています。「ときの森公園」では、トキを観察することができますが、昨年春から「トキまで2センチ!」をキャッチコピーに新しい施設もできました。オレンジが見学に行ったとき、2cmとまではいきませんでしたが、数十cmのという至近距離で、トキを観察することができました。また、「ときの森公園」を出るとすぐ、何と、放鳥されているトキに遭遇することができました。近くの田んぼから飛び立ったところで、トキ色の翼を見ることができました。修学旅行の最後を締めくくるにふさわしい出来事でした。 |