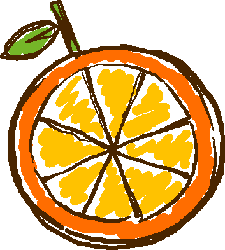 |
|
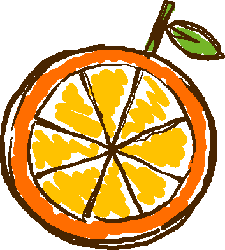 |
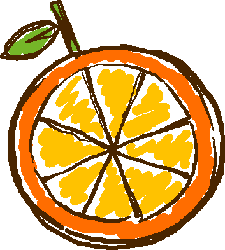 |
|
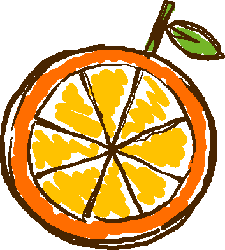 |

11月20日(水)、新潟県立近代美術館に行ってきました。開催されていたのは、「館長 庵野秀明 特撮博物館 ミニチュアで見る昭和平成の技」です。展覧会の概要は以下の通りです。
| 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」の大ヒットも記憶に新しい、映画監督・庵野秀明。その創作活動の原点であり、多大な影響を与えてきたのが「特撮」です。円谷英二が始めた日本の特撮は、世界に誇る高い技術を有していましたが、デジタル技術の発展とともに岐路に立たされ、貴重なミニチュア類は散逸しつつあります。本展ではこの状況を憂慮した庵野秀明自らが館長となり、実際に使用されたミニチュアやデザイン画など約500点を紹介します。また、庵野秀明企画、樋口真嗣監督によるスタジオジブリ製作オリジナル特撮短編映画(展覧会版)「巨神兵東京に現わる」を併せて公開します。 (新潟県立近代美術館HPより) |
「巨神兵」は、『天空の城ラピュタ』にも出てくるため、子どもたちは短編映画を興味深く見ていました。また、短編映画のメイキング映像もあり、特撮映画のしくみがよく分かりました。
プロの技に触れ、工作等に生かそうと思ったり、将来の夢になったりした子もいたようです。
* 「マナーがよい」と、美術館の方からほめていただきました。
 |
 |

11月29日(金)に、お米パーティーをしました。田植えと稲刈りをさせていただいたお米を炊いて、お世話になった方を招待しました。おみそ汁も作りました。
ほとんどの家庭で、お米は炊飯器で炊いていると思います。自然教室では、飯盒でお米を炊きましたが、今回は、鍋の中の様子がよく見えるように、ガラス製の透明なお鍋で炊きました。おみそ汁は、煮干しからだしをとって作りました。
ご飯も、おみそ汁もなかなかのできで、来ていただいた方々にも喜んでもらえました。
お米は、全部で30㎏いただきました。お米パーティーで使った分と、家に持ち帰った分のほかに、
12月3日(火)の給食にも使ってもらいました。全校のみんなから、おいしいと言ってもらえました。
 |
 |
 |
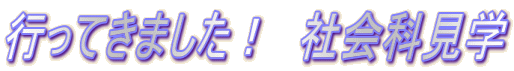
12月4日(水)に社会科見学に行ってきました。 午前中は新潟日報に行きました。新潟日報では、黒崎にある印刷センターと言われるところを見学してきました。 まず、鉛版が巻き付けられている柱を見ました。鉛版とは、鉛製の新聞の版です。昭和57年まで使われていたそうです。今では、玄関ホールの柱にオブジェとして巻き付けられていました。次に、昭和57年の11月1日の第1号や、歴史的な出来事の記事が掲載されている新聞を見ました。それらは、壁に飾られていました。 それから、インキや、巻き取り紙(新聞を印刷する紙)の説明をしてもらいました。そのあと、高速輪転機が動いている様子を見学しました。新聞自体の話だけでなく、新聞社で働いている人たちがどんな仕事をしているかということも教えてもらいました。見学できない仕事の様子などは、ビデオで説明してもらいました。 もちろん、学校で事前に学習をしていきましたが、実物の規模の大きさ、最新鋭のシステム等を目にし、子どもたちは驚いたというよりも感動していました。 実は、見学の前に記念写真を撮影しました。見学後、記念にもらえるということでした。見学後にもらったのは、見学前に撮影した写真が印刷された、まるで新聞の号外のような形式のものでした。とてもよい記念になりました。 |
|
 |
![]()
12月4日(水)の午後は、NHKに行きました。NHKでは、『キミが主役だ! NHK放送体験クラブ』という企画に参加する形の見学でした。内容は、以下の3部構成でした。
第1部 オリエンテーション
①スタジオや副調整室の仕組みの説明
②「プロンプター」体験
…キャスターの原稿は、キャスターの頭上にあるカメラで撮影し、キャスターを映すカメラに
送られています。キャスターを映すカメラは、マジックミラーになっていて、キャスターは、
カメラを見ると、そこには、原稿が写っている仕組みです。
③「クロマキー」体験
…青い色を映さない設定のカメラを使い、ブルーバックのシートの前でいろいろな動きをしました。 そこに写真や映像を合わせると、忍者のように石垣に隠れたり、空飛ぶ絨毯に乗ったりなど、 おもしろい体験ができました。
④CGキャラクター操作
…マスターモニというCGキャラクターを操作したり、それに合わせた台詞を言ったりしました。
⑤模擬ニュース番組づくり
…NHKが用意してくれた台本で模擬番組を仮設にスタジオで撮影しました。│
キャスターやリポーターだけでなく、カメラマンやディレクターなどの仕事│
も担当しました。 │
第2部 挑戦! 番組づくり │
…学校で事前に用意したテーマ(「片貝まつり」と「創立140周年記念式典」)で、ニュース番組を
撮影しました。第1部の模擬ニュース番組よりも、さらに子どもたちの仕事の量は増えました。
第3部 納得! NHKなんでも学習 │
…実際のニュース番組で使われているスタジオで、機材やセットの説明をしてもらいました。その後、
「ニュース番組ができるまで」というビデオを見て、見学では見ることのできなかった部分も見る
ことができました。最後は、子どもたちの質問に答えてもらいました。
はじめは、緊張気味の様子でしたが、NHKの方のリードで次第に調子が出てきて、楽しみながら活動ができました。また、どの子も自分の仕事に真剣に取り組んでいました。いろいろな体験を通して放送の仕組みが分かっただけでなく、仕事の厳しさやあこがれも感じることができたようです。
 |
 |
 |
 |
![]()
2月6日(木)に、社会科見学で日本精機さんに行ってきました。
今回は、「工業生産を支える人々」という学習の一貫で、主にスピードメーターを製造している日本精機さんに、「自動車部品を作る工場の見学を通して、自動車生産の仕組み、生産を高める工夫や努力等を理解するとともに、日本の工業の現状と課題をとらえる。」という目標で、見学をしてきました。
はじめに、ビデオを見せていただき、そのあと工場を見学させてもらいました。工場内は大きな機械がたくさんあること、オートメーション化されていること、細かい部品も機械が製造していること、手の込んだ仕事もあっという間にできてしまうことなどを目の当たりにし、時代の最先端を行く部品も作っていることを知った子どもたちは、その迫力に圧倒されたようでした。(今回は工場の見学のため、撮影はできませんでした。)
事前に送っておいた質問事項にもていねいに答えていただき、見学の目標もほぼ達成できました。最後に、おみやげにとして、スピードメーターの部品をいただきました。
この見学を通して、これからも日本の工業について関心をもち続けたり、地元の企業ががんばっていること理解したり、将来の夢につなげたりしてほしいと思います。

| 12月13日に、鼓笛引継式がありました。この引継式に備え、11月から練習を始めました。 鼓笛隊で引き継ぐもの。それは、楽器の演奏技術だけでなく、片貝の伝統です。心を一つにすること、しっかりあいさつをすること、礼儀正しい態度をとること...。鼓笛隊は、「もみのキッズ」を象徴しているといっても過言ではありません。 5年生は「オレンジ・フラワー鼓笛隊」の中心となり、4年生をリードし、先輩方、後輩たち、誰に見られても恥ずかしくない姿を見せていかなければなりません。子どもたちは、その重圧を感じながらも、やる気に満ちあふれていました。 6年生といっしょに演奏していたときは、「ついていくのが精一杯」といった感じでしたが、鼓笛隊の中心となった今回の演奏は、とても堂々としていました。「オレンジ・フラワー鼓笛隊」として、すばらしいスタートを切ることができました。 |
 |

1月23日、出張授業「自分たちの学校をテーマにプレゼンテーションを学ぼう!」がありました。東京から最新のパソコンを持って、8人の方々が学校に来てくださり、パソコンの使い方、プレゼンの仕方等を教えてくださいました。
まずは、「プレゼン」とは何か、「プレゼン」で大切なことは何か、「プレゼン」のコツなどを教えていただきました。
次に、パソコンでできることを簡単に説明してもらいました。
いよいよ作業開始。10のグループで、あらかじめ、自分たちで考えたテーマに沿って、伝えたいこと(自慢したいこと)、理由(3つ)を考えました。
そして、これもあらかじめ用意しておいた画像を貼り付けたり、文字を打ち込んだりしました。見ている人が興味をもってくれるように、文字は、色や大きさを工夫したり、画像にはアニメーションを設定したりしました。相手に対して分かりやすく、かつインパクトのある言葉を吟味したり、アニメーション等に凝ったりしていると、あっという間に、制限時間の35分間がたってしまいました。(できあがったプレゼンは、自動的に「プレゼンコンテスト」に応募することになっています。そのため、子どもたちの強い希望で、翌日、学校のパソコンで修正を加えました。)
最後に、できあがった作品を見せながら、1分間のプレゼンをしました。
この出張授業を通して、最新のパソコンに触れることができたこと、パソコンの操作に慣れたこと、プレゼンテーションソフトの使い方が分かったことなどの技術的なことと、限られた時間の中で最善を尽くすこと、友達と協力することという作業的なこと、さらには伝える相手のことや分かりやすい伝え方を考えたり、人前で発表することのプレッシャーと戦ったり、友達のプレゼンを真剣に聴くことが友達を応援することにもなるということを感じたりと、たいへん多くのことを学ぶことができました。これらのことは、学校で役立つことが多いと思います。この体験をすぐにでも生かしていこうと思います。
 |
 |

2月28日(金)に6年生を送る会がありました。6年生を送る会は、5年生が運営する最大のイベントです。6年生を送る会に向けて、みんなで協力しながら、以下のような準備を進めてきました。
①原案作成(代表委員会):総務委員会
5年生みんなで考えた6送会の原案を、総務委員会が代表委員会で提案しました。みんなで知恵を 絞った甲斐あって、原案がそのまま通りました。ここから、具体的は活動 がスタートしました。
②メッセージ書き:Kスポーツ委員会
たてわり班でいっしょの6年生に、感謝の気持ちを伝えるために、メッセージを書きます。今年も昨年 同様、色紙にメッセージカードを書いて渡すことにしました。全校で集まってメッセージを書く時間が
取りにくいため、1~4年生の名前を書いた封筒に、6年生の人数分のメッセージカードを入れ、
各クラスに配りました。その後回収し、1枚1枚、誤字脱字等の確認をしました。そして、2月6日の
もみの木朝会の際に撮影したたてわり班で撮った集合写真を色紙の中央、その周りにメッセージを
貼りました。メッセージカードを切り、封筒に入れ、チェックし、色紙に貼る作業は、みんなで協力して 行いました。
③思い出ビデオ:放送委員会
6年生の「思い出ビデオ」は毎年恒例です。昼休みを使って、毎日撮影しました。今年は6年生の
人数が多いため時間がかかりましたが、およそ1か月間、毎日のようにがんばりました。
④ありがとう給食:ヘルスランチ委員会
6年生が下学年のクラスで給食をいっしょに食べる「ありがとう給食」も毎年恒例です。6年生の行く 教室を決めたり、当日は会食風景を撮影したりしました。
⑤飾りつけ:ヘルスランチ委員会
6年生を送る会当日の飾りつけも、ヘルスランチ委員会が中心になって行いました。1~4年生にも お花を作ってもらいました。
⑥音楽朝会:エコ・ベル委員会
2月の音楽朝会は5年生担当で、六送会で歌う歌の練習をします。今年の六送会で6年生に贈った 歌は、FUNKY MONKEY BABYSの「サヨナラじゃない」でした。この歌も5年生が話し合いで決め
ました。
音楽朝会では、ただ歌うだけではなく、学年ごとに歌ってもらったり、歌合戦形式にして歌って
もらったりしました。その結果、当日はとてもいい声で、心のこもった歌を6年生に贈ることができ
ました。「ともだちなんさ」も元気よく歌えました。
⑦垂れ幕計画:図書委員会
各学年から6年生へのメッセージを垂れ幕にかくのも、片貝小学校の六送会の特徴の一つです。
くす玉のように、ひもを引くと、垂れ幕が開き、文字が見えるしくみです。取り付けは、管理員の
廣井さんに手伝っていただきました。
⑧全校ゲーム:あいあい委員会
今年の全校ゲームは、頭を使うゲームでした。題して「並べ替えて言葉を作れ!」。
30文字程度の言葉を並べ替えると、6年生へのメッセージができあがります。あいあい委員会が
原案を考え、5年生で実際にやってみて、修正しました。
⑨6年生を送る会の進行:総務委員会
各学年と密に連絡を取り合いながら、進行の原稿を考えました。当日は、シナリオ通りとは
いきませんでしたが、その場の状況に応じて進めることができました。
六送会、大成功の裏には、1~4年生の協力が不可欠でした。1~4年生は、ダンスや劇、くす玉作りんなど、5年生がお願いしたことを、それぞれ工夫を加えて準備をしてくれました。垂れ幕作り、メッセージ書き、歌の練習等も各教室、各学年でいっしょうけんめいやってくれました。
そのおかげで、当日、6年生は涙を流すほど喜んでくれましたし、1~4年生のみんなも6年生に感謝の気持ちが伝えられて満足していると思います。
そして、何よりも5年生が一番満足しています。子どもたちからは、「大変だったけれど、やりがいがあった」「みんなで協力しなければ、成功しなかったと思う」「感謝されてうれしかった」「準備をしっかりしておけば、当日、予定通りにいかなくても何とかなると思った」という声が聞かれました。
実は、6年生を送る会の準備を始めたばかりの頃は、まだまだ人任せなところがありました。しかし、次第に「自分がやらなければ!」と思う子が増えていきました。準備の途中で、うまくいかなかったり、計画を変更しなければならないこともありましたが、その都度、友達と相談したり、協力したりしながら、一つ一つの問題を乗り越えていきました。
当日も、ピンチヒッターをしたり、一人一役以上の仕事をしたりと、全員がフル回転でがんばりました。木遣天舞もキマリました!
この一大イベントを大成功に導いたオレンジたちの姿を見て、6年生も、先生方も「来年の片貝小学校もこれで大丈夫!」と思ってくれたに違いありません。これからも、期待にそえるよう、がんばります!!
 |
 |