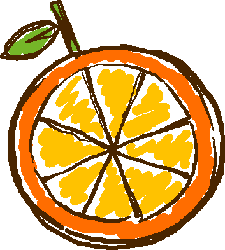 |
|
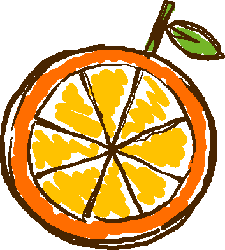 |
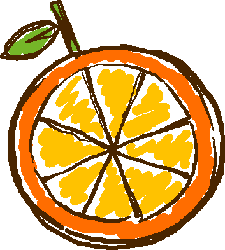 |
|
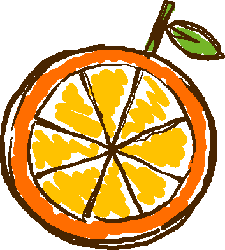 |
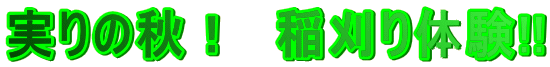
5年生は、社会科の学習で、農業について学習しました。それに伴い、地域の方の田んぼをお借りして、稲作を体験させていただいています。
秋になり、春に植えた稲の苗が頭を垂れましたので、9月30日に稲刈りをしました。
鎌を使うのは初めて、という子が多くいましたが、地域の方や手伝いに来てくださったお家の方々に教えていただきながら、稲を刈りました。数日前の台風の影響で倒れている稲もありましたが、上の方の稲から順番に、一株ずつ刈っていきました。はじめは恐る恐る刈っていた子どもたちでしたが、次第に調子が出てきました。稲を刈るのと同時に、刈った稲を束ねる作業もあります。そして、束ねた稲を一箇所に集めます。また、刈り残した稲を刈ったり、運ぶ途中で落とした稲穂を拾ったりもしました。子どもたちと、お家の方々を合わせて40人で稲刈りをすると、あっという間に終わりました。
子どもたちは、楽しく稲刈りをすることができましたが、「腰が痛い」「疲れた」という子も多くいました。農家の方や先人の苦労、そして、お米の大切さを実感できたようです。
 |
 |

| 10月17日(木)に、親善音楽会がありました。親善音楽会には、毎年5年生が参加していて、「木遣り」「八木節」を発表しています。 「木遣」は、片貝伝統芸能保存会の皆様から教えていただきました。「八木節」は6年生から教えてもらいました。「木遣」は、片貝の伝統を大切にし、「八木節」は、オレンジ学年の心を一つにするように練習を重ねてきました。 本番は少し緊張していましたが、精一杯唄い、そして演奏しました。 親善音楽会を無事に終えたということは、「片貝の伝統を守る」という意味では、大きな一歩です。「木遣」と「八木節」は、今度はフラワー学年に引き継ぐことになります。 |
 |

10月23日(水)に、「南極クラス」がありました。「南極クラス」とは、南極観測隊参加経験のある方が学校を訪問し、南極の自然や経験されたことを話してくださる学習です。
| ・子どもの将来に夢を与えたい、希望を持ってもらいたい。 ・南極の動物、オーロラなど南極の大自然の画像を多くみせたい。 ・エコエネルギーの話、その他、環境エコに関することを伝えたい。 ・仲間の大切さ、人と人が支えあっていくことの大切さを伝えたい。 (「南極クラス」HPより) |
という目的で開催されています。
今回、「南極先生」をしてくださったのは、井熊 英治(いくま えいじ)さんです。
お話の内容は、以下の通りです。
| ・ ?南極はどこにある? …南極は日本からどのくらい離れていて、どのようにして行くのか。荒海を越え、氷海を進む砕氷艦しらせの動画やスライドで説明。 ・南極観測隊はどんな人たち? …観測担当、設営担当など、様々な職種の人がお互いに支えあっている。観測隊の活動期間、それぞれの仕事の内容、役割などを説明。 ・南極の自然は? …極寒の厳しい自然環境はどのようなものなのか。 マイナス35度でも息が白くならないことや、氷に閉じ込められた大気を説明。 ・なぜ、南極で観測するの? │ …南極での観測活動、地球温暖化、オーロラなどについて説明。 ・南極昭和基地ではどんな暮らしをしているの? │ …過酷な環境で隊員たちはどのように過ごしているのか。ブリザードの脅威、居室のことなど、隊員の生活を説明。 │ ・質問タイム (「南極クラス」HPより) |
子どもたちは、南極という「未知の世界」での活動を知るだけでなく、夢と希望をもつこと、チームワークの大切さ(南極隊員の方々は限られた人数で支え合ってミッションをこなしていきます)なども感じてくれたことと思います。
 |
 |